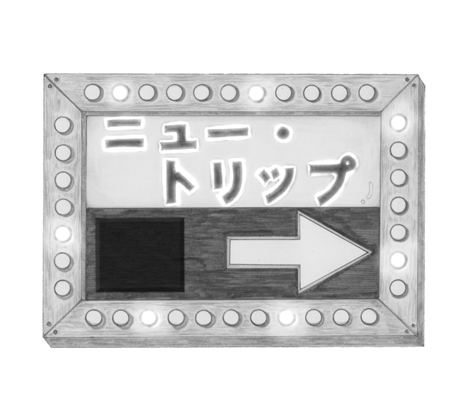第31話『ニュー・トリップ2 コンプのコンプ』
守衛所に入る条件が、イヤシちゃんの奪還。
あれほど嬉しそうにはしゃいでいた大人から、物を取り上げろって。
「豊川さん、返してくれるわけないっすよね」
「大丈夫なんじゃないかなぁ。豊川さんにわけを話してみようよ。今からいっちゃおうよ」
「絶対ムリですって。もし怒らせたでもしたらなにされるかわからないですって」
「ハルノキくん! 思い立ったが吉日だよ! たけしさんもいってたじゃない! ダーっといっちゃおうよ!」
まだ、少し酔っているんじゃないかこの人。
「いや、たけしさんて……。正直あの人いってること間違ってましたからね」
「そうかなあ、たけしさん、本当はいい人なんだよ」
「まもるさん、クビだったじゃないですか」
「違うよ! 依願退職になっ──」
「オメーら、うるせぇぞ! いつまで店の周りでゴチャついてるつもりだ!」
突然ドアが開き、熊野が顔をだした。
「す、すみません! まもるさん行──」
声を掛けようとしたら、まもるさんはすでに上空へ浮かびあがっていた。
「まもるさん、逃げるの速すぎますよ」
「ごめんね、ごめん。気がついたら飛んでたんだよぉ」
「あー俺も逃げてーっす。豊川さんに頼みに行くの怖いっすよー」
「がんばろう! ハルノキくん。一緒に守衛所で働こう! あー、でもボク、痩せるのムリだなぁ……お腹すくのやだな」
無意味に非難するのはやめておこう。「それこそ、なんとかしろよ」といいかけ、心に留めた。
「ところでハルノキくん、豊川さんの連絡先、しってるの?」
「はい。いちおう教えてもらってます」
視野内に豊川さんの連絡先を呼び出して確かめてみると『豊川個人事務所』のアドレスはVRスペース内になっていた。
「あ、“AFL-3”か。そりゃそうだよな」
「なぁに? それ?」
「
「知らない」
「VR空間の機能によって必要なレベルがあるんですよ。
「は、ハルノキくんは物知りなんだね」
「imaGe使ってたら普通じゃないですか?」
「ボク、imaGeを手に入れたの先月なんだ」
「嘘ですよね? いままでどうやって生きてたんですか?」
「スマートフォン使ってたよ! いまでもimaGeホルダーにしてる!」
湾曲した薄っぺらい板のようなものが、まもるさんのムクムクとした手の中に収まっていた。
「な、なんすかこれ?」
「ハルノキくん、スマホしらないの?」
「聞いたことはありますけど、はじめてみました、ちゃんと使えるんですか?」
「あたりまえだよ。前までは、音声通話もネットも……あ! 大変! ホバーベルトのバッテリーがなくなりそう」
画面の中でホバーベルトのシルエットが赤く点滅していた。
「充電しないと。飛べなくなっちゃうよ」
確かにまもるさんの足が接地しかけている。
「充電式なんすか? そのベルト?」
「うん。充電しないとうまく操縦できなくて」
「それじゃあ、近場のVRカフェを探してみましょうか。VRチェアも電源もあるだろうし、ああ、でもやだなぁ、豊川さんに連絡するの」
「ハルノキくん。前に進もうよ! ベルトの充電もしたいからそこに連れてってよ」
「連絡するのは明日にしましょうよ」
「ねえ。ところで、VRカフェって甘い物もおいてるの?」
思わず「うるせえデブ!」と叫びそうになった。自分の中にそんな邪悪な感情がわき上がったことに驚く。
甘味の有無をしきりに気にしているまもるさんに適当な返事をしながら、misaを呼び出した。
「misa、近くにあるVRカフェ探して」
『やっっっと行く気になったの? まったくさ、ウダウダ、ウダウダ、いい歳した男がさ』
「だ、だってさあんなに喜んでたし、そ、それにもうこの時間は寝てるかもしれないし」
『ないない。あれは夜まともに寝てる顔じゃないって。絶対起きてるから』
「やーヤダよ、やっぱりヤダ」
『アンタさ、病院怖がる小学生じゃないんだからさ…………よし。近くのVRカフェ予約したから早く、行く!』
「え、なに勝手に……」
『いいから、はいはい。そのまままっすぐ進んで』
視野内に
このアシスタントの対応はなんなんだ。むこうが主みたいじゃないか。しかし見知らぬ街で有能なA/Pを失うわけにはいかない。不興を買うわけには。
「まもるさん、こっちみたいです」
「えー歩くのぉ?」
『はいはい。その人を黙らせて。次の角を右、その次は左。で、そこの突き当たりのビルの3階だよ。エレベーター壊れてるから階段ね』
のっそり、のっそり歩くまもるさんとたどり着いたのは、古い雑居ビルだった。
3階の窓に『V-カフェ』のホログラムがぼんやりと投影されていた。
「この階段上るみたいです」
「えー!? 階段なのー? ボク、ムリだよ。ヤダよー」
「『満』の階段はすいすい上ってたじゃないですか」
「あれは、ホバーベルト使ってたからだよー」
「とにかく、がんばってください」
浮かない老人の手をとり階段を踏みしめた。
「ご予約のお客様ですね、こちらへ」
案内してくれる店員さんを目の当たりにして、思わず視野内の左上を確認してしまった。まだ、ログインしてないよな。
狭い通路内にひしめくドアの間を縫って歩く店員さんは屈強な肩幅、体中にイラストのように筋肉の線が走っている。
やっぱりこの時間に働くには、舐められない体格が必要なんだろうか。コンビニの深夜勤務しようとした自分が恥ずかしくなった。
こういう人ならば“深夜スタッフ検定”とか受けなくても信頼を勝ち取れるんだろうな。
「こちらです」
店員さんは1番奥の部屋のドアを静かに開けてくれた。ルーム内は2人掛けのVRチェアが一脚だけ置かれた狭い個室だった。VRチェアはベンチ型のカップルシート。
「え? カップルシート!?」
「さきほど、アシスタントプログラムの方より承っておりますが……」
「あ、あ、はい。あのイイっす。あのこっちの問題なんで。ありがとうございます」
「ネットカフェみたいなとこなんだね! VRカフェって。うわーなんか狭いねハルノキくん」
大声を出さないでくれ。
狭小な密室に男2人が入ることを周囲に知られたくない。
「それではごゆっくり」
なんだか意味深に聞こえる言い方をして店員は去って行った。誤解されていないといいけど。
「周りの部屋もぜんぶこうなってるのかなー」
入口でまだキョロキョロしてるまもるさんを放って。席へ着いた。
「まもるさん。廊下にいてもらえますか」
「え、なんで? やだよ、変な人だと思われたら恥ずかしいよ。ボクも座らせてよ」
無理矢理シートに座り込んできた。
「いや、その、少し狭いなって」
「大丈夫だよ! ボク充電しながら浮かんでるから! よい……しょっと」
まもるさんが、ベルトに細いコードをつけ先端をコンセントに差し込むと、少しずつ体が浮き始めた。
「天井のあたりで充電しているから」
まもるさんが浮かんだ分、ソファにはだいぶ余裕がでた。
「じゃあ、まもるさんはそこで静かに浮いててください」
「ボクも行かなくて平気?」
「はい」
話がややこしくなりそうだと直感した。
「このベルトさ、たまに暴れるから、頭低くしておいてね」
確かに。頭上に浮かぶ巨体がときおり思い出したように上下に揺れている。気が散る。
「あれ、お店専用のVRだって、すごいな行ってみようかなー」
「あの……」
「え、これなに? 冒険物かぁー」
「あの……」
「喉渇いたなぁ」
「まもるさん。そういえば入口にドリンクバーありましたよ。ジュースとか飲み放題だから好きなの持ってきたらいいんじゃないですか?」
「ホントに!? ちょっと行ってこようかな」
そういって、ベルトを外して、まもるさんが降りてきた。
「ハルノキくん、何か飲む?」
「いや、自分はちょっと潜るんで」
「そっか、それじゃあ行ってくるね」
靴の踵をつぶしたまま廊下へ出て行った。
「子供みたいね人だな」
ドアに鍵を掛けた。
さて……。
セルフレームのメガネ型バイザーを取り出して装着すると、imaGe視野がコンタクトレンズからメガネに移った。
ここまで来たら行くしかないか……。
『豊川個人事務所』のアドレスを呼び出した。
視界がホワイトアウトしてアラートが
『“豊川個人事務所”へようこそ
これから先のスペースにはアダルトコンテンツが含まれます。アクセスを続行しますか?』
魔境だ。
この先はファンタジー世界か? 事務所用のチャットルームがアダルト指定されるている相手から女をもぎ取りにいくのか。
『YES』を選択する指が震える。
「くふぅぅ!」
決死のタップを合図にチャットルームの
ホワイトアウト、ホワイトイン。
薄目を開けると予想外の空間だった。
無難な応接室。
調和の取れたインテリア。
デザイン関連の仕事を手がけるラボのようにモダンな空間。
「あ、あれ?」
自分が異物のようだ。
時刻設定は
そんなわけがあるか?
アダルトコンテンツ指定のチャットルームが?
自分は『ブリンカー』の荒れ果てた空間に毒されすぎているのか。
左上のログイン名を何度も確認している自分に気がつく。そういえば前にも、こんな気分で相手のログインを待っていたことが──
『AM 00:46 豊川さんがログインしました』
早い。
自分のログインが告知されて、まだ1分そこらの時間しか経っていないはずなのに。
目の前のソファに“白いバスローブ”をまとった『豊川さん』が現れた。
岩のりのようにうねるロングヘアにサングラス。現実と寸分たがわないアバター。
自分でチャットルームを所有する人物というのはリアルと同じ容姿を晒すという共通の
「待ってたよー桜くん」
「え?」
「イヤシちゃんのことでしょ?」
「は、はい! そうっす! ……なんでわかったんですか」
「この時間に来るってことは、もうそれしか無いじゃないですか。いやあ、桜くんは絶対に来ると思ってましたね。目覚めたんですね。ダッチワイフへの愛に」
「その、あの……」
「あ、いい。いいよいいよ。いい。わかってるから。ね、最初はみんなそうです。いわなくていい。ねっ。まずは、うん。乾杯しよう」
豊川さんが空中に拳を2回打ち付けた。
デリカーが2本降りてくる。
「もー、デリカー飲み放題にしちゃうからぁーうん」
上機嫌な発砲音をたてて栓をあけ、豊川さんがデリカーを差し出しきた。
「今日は桜くんが“シリコニスト”デビューするお祝いだから」
「し、シリコニスト!? なんすかそれ」
予想外の方向に巻き込まれようとしている。
目の前に突如、竜巻が現れたような。
「桜くんのイヤシちゃんへの想いと同じように、シリコンに代表される、人工的な素材によって
「倶楽部……、自分はそういうのじゃなくて」
「もう隠さなくて、いいんじゃないですか。ごく自然な結論です。それ。ハルノキくんの“シリコニスト”デビューに乾杯しましょう」
高らかにデリカーが掲げられた。
「そうじゃないんです。自分、イヤシちゃんをどうしても……」
「うん。大丈夫。いいいいよ、いい。全部いわなくてもちゃーんとわかってますから」
「あ、あの、耳元でささやくのやめてもらっていいっすか」
「いいから、いいから恥ずかしがらなくて」
ぐっ、と力のこもる感触で肩へ手を置かれた。
「ボクも桜くんぐらいの頃は、そういうことあったから」
「豊川さんは、そのし、シリコニストじゃないんですか?」
「おかげさまで、ボクは“シリコネスタ”の称号を拝受しています」
「な、何が違うんですか? ていうか、違うんですか? それ」
「はい。公爵と侯爵くらいに違いますね。シリコニストとしてデビューしてからの活動、倶楽部への貢献度や本人の人格、向上心、心意気あらゆることが認められてはじめてシリコネスタを名乗ることが許されます。桜くんは“
「知らないっす」
「デビューするや、最速でシリコネスタまで登り詰めた伝説の人です。当時もの凄く憧れてましてね」
豊川さんの背後に、VRインピクチャーが表示され、黒々と日焼けした男の画像が出てきた。
「80年近く続く倶楽部の中でも前例のないスピードだったんです。もう、シリコネスタになるために生まれてきたような天才ですね。ボクの、心の
豊川さんが自嘲的な笑い方をしながらデリカーを口に含む。
「壊してしまったんです。毎晩、毎晩、愛し過ぎてしまって」
画像が変わった。
肩パッドのバッチリきまったショッキングピンクのスーツを身につけた、年代物ダッチワイフだった。
不覚にもスーツのシルエットだけは、イカしていると思ってしまった。
「彼女ね、クミコといいまして……、ボクがね、若すぎたんです。一緒にいれるだけでよかったハズなのに、1度だけ、1度だけと思って手を出してしまった……それからは、もう歯止めがきかなくて、もう、壊れるまで……こともあろうに“して”しまった」
次の画像の“クミコ”は、ところどころにテープが貼られた状態でボロボロになって萎んでいた。
「だ、だって、元々、使うためにあるんじゃないんですか」
「シリコニストはそれでいいんです。でも、やがて気がつくんです。肉体だけの関係ではないことに、そのときはじめて次の扉が開きはじめます」
「じゃ、じゃあ豊川さんは、イヤシちゃんとは……」
「もちろんです。手もつないでいません」
「は、はぁ……」
この局面で、的確なリアクションを取れる人間がいたらそいつは、リアクションの天才だろう。
「飛行機であったとき、まだイヤシちゃんに触れてもいなかった桜くんにボクは、素質を感じています。桜くんはもしかしたら稀代のシリコネスタになれる器なのかもしれない」
そういいながら、豊川さんが1枚の“紙”を出してきた。
「倶楽部への入会書です。サイン、しよう」
「いやいやいやいやいや。違うんです」
「こっちの推薦状もちゃんと書くから」
「あ、あの、豊川さん、そういうことじゃなくて、イヤシちゃんを返してもらえないかって話なんですよ」
「そうだよね。そうなるよね。自分のダッチワイフがなかったらオフ会とかで恥ずかしいもんね、うん。わかるんだけど、でもね、イヤシちゃんは、ムリなんだよ」
「や、やっぱりそうっすか、でも自分も困るんですよ」
「他の娘とかには、興味でないかなぁ」
豊川さんが、指を鳴らした。
すべての窓が反転し、光が消えた。
暗転した部屋に、今度はほの暗いピンク色の照明が灯り、部屋中に、ぜ、全裸のダッチワイフ集団が現れた。
「こ、これは……」
「今までボクの支えになってくれた娘たちです。3Dスキャンでデータにして、こっちに連れてきてます」
「もしかして、発売されているダッチワイフ全部集めてるんですか?」
「ボクはコレクターじゃないから。
「いや、自分はイヤシちゃん以外は」
「そうだよね、そうだよ。でも、イヤシちゃんはダメだ。ボクも離れられない。彼女の代わりはいないんだよ」
そうか。この人の、完全にねじ曲がった方向へ突っ走っる話と、イヤシちゃんを返してもらうという話が、曲がりに曲がって噛み合ってしまったのか。
宇宙の中で絶望的に離れた空間同士が、時空の歪みでつながってしまったような奇跡で。
「……たとえば、クミコさんが現れたらどうなるんですか」
「ありえない。ありえないけど、もし、もしそうなったら」
豊川さんが声を潜めた。
「イヤシちゃんとはお別れしないとですね」
これだ。
クミコと呼ばれるダッチワイフを探せばいいんだ。画像に目をやる……ボロボロのダッチワイフ……。そうだよ。さっき気になったこと……もしかして、偶然じゃないかもしれない。
「でも、それは絶対にありえない。彼女の
年代で確信した。真っ最中じゃないか……バブルの……。
微かな閃きと希望が芽生えた。
「桜くん。だからボクからイヤシちゃんを奪うという選択肢はあきらめてほしい」
クミコのスーツスタイルからいっても、あの人に聞いてみる価値はゼロじゃない……。
懇願する豊川さんの黒々とした頭頂部に向かいおもいきって声をかけた。
「豊川さん……。もしかしたらクミコさんを連れてこれるかもしれません。ボクにチャンスをくれませんか?」
次回 12月22日掲載予定
『 ニュー・トリップ -3- 稀代の期待 』へ
つづく
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする