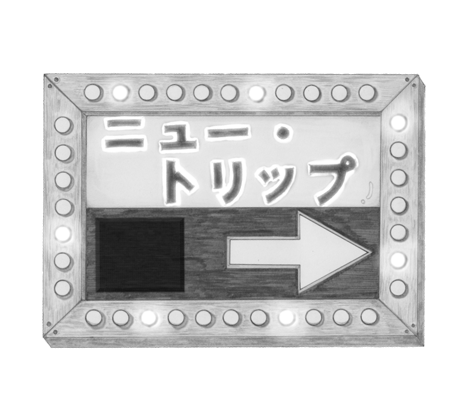第32話 『 ニュー・トリップ -3-稀代の期待』
ホワイトアウト。ホワイトイン。
薄目を開くように視界がぼんやり戻りはじめる。気は急いていても、imaGeログインの独特な間だけはいつもと変わらない。
扉も窓もない部屋。
金箔を張り巡らせた華美な壁。
しかし、初見ではないからだろうか、圧迫されるような感じは受けない。
前と変わったのは床に広がっていた“虎の敷物”は“削除”されていたことくらいだろうか。
沈み込む泥沼のような感覚を伝えてくるソファに埋もれて、相手のログインを待つ。
『ログイン名:桜 夏男
ログイン先:ショルダーパッド 応接室
AM 01:32』
無意識にログイン情報を確認していた。
少し待つことになるかもしれないが仕方ない。
金曜日のこの時間はきっと多忙だろう。
突然のアポを断られなかっただけましだ。
視野内に注目してまっていると──
『AM 01:33
軽快な告知音と共にアラートがでた。
みんな、こんなに夜遅くでもログインしてくれるんだな。
「ああ、やっぱりキミかぁー」
“泥沼”ソファに屈せず背筋をシャンと伸ばした格好で『棚田さん』が座っていた。
色黒で彫りの深い顔、黒いソフトスーツに極太の金ネックレス。記憶どおりのアバターだった。
「ご無沙汰してますっす! 週末の夜にすみません!」
「ちょうど休憩だったから大丈夫、大丈夫」
この時間に
「ハルノキって名前ですぐ思い出したよ。仕事みつかった?」
今日は面接ではない。口調がフランクだ。
「まあ、あの……まだ就職活動中っす」
「そっか、そっか。それじゃ今日は? もしかしてウチで働く気になったとか?」
全滅していた面接の中で唯一自分を気に入ってくれた店だった。
店内のスタッフ全員が特注の肩パッドを入れたジャケットを身にまとうリアルディスコ『ショルダーパッド』。
パンパンに張った、棚田さんのジャケットの肩に思わず目が行く。
「やっぱり、ジェケット、イカしてますね」
「おう、ありがとう。ホントはねリアルの方がすごいんだけどね。いつか見せたいな桜くんに」
あの時代の空気や風景を忠実に再現した、『ショルダーパッド』の支配人なら、『クミコ』のことを知っているのではないか。
直感だった。
「棚田さん。実は、探しているバブルグッズがありまして、そういうの棚田さんのお店に残ってないかなと思って」
「え? どんなの?」
「いや……なんというか、クミコっていうダ、ダッチワイフなんすけど……」
「ダッチワイフゥ!?」
きっと棚田さんの
冷静に考えてみれば、この忙しい真夏の週末、貴重な休憩時間に飛び込んでくるおかしなヤツ、勇み足が過ぎた。
「……あ、でも……それさぁ、どんなやつ?」
「もう、もろにディスコって感じのビシーっとしたピンクのスーツ着てる、ワンレンの人形なんすけど……、いや、まさかないっすよね、すみません。バブルっぽいってだけで、棚田さんのこと思い出しちゃって」
「それ、もしかしてさ……」
棚田さんが、
「このあいだ、店の倉庫かたづけてさ、レトロな物がいろいろ出てきたんだけど……あれ、どこだっけな」
画像がめくられていく、写真集でしかみたことがない、大型の“ラジカセ”や、羽の扇子などが行き交っている。
「これ全部、
「そうそう。うち結構長いからさ、お客さんが置いてったものとかもあるし」
虎の敷物も通りすぎた。
あれは現実側でも所有されていたのか。
「あ、あった。これ。どう?」
1枚突き出てきた画像に、目を奪われた。
いた。
クミコ、だった。
嘘だろ?
「違うかなこれ?」
「い、いや、あの、それ! それっす!」
パーティーで「ビンゴ!」と叫ぶような気持ちだった。ビンゴに参加したことないけど。
「あ、ほんと」
なんといえばいいのか、迷った。
あっさりと見つかり過ぎてしまった。勇み足の次は、肩透かし。
相撲じゃないんだから。
「こ、これ、譲ってもらうわけにはいかないですか?」
「そうだよね……なんかワケありみたいだし」
そりゃあ渋るだろう。あの豊川豊が
「あげたいところなんだけど、実は、来月さ、8月の最終日がちょうど金曜日だから、ダンスコンテスト開くんだけど、その賞品にしちゃったんだよね」
「だ、ダンスコンテストっすか!?」
「そうそう。倉庫の中に、けっこう珍しいものあったからさ。そうだ。桜くんも参加してみたら? ちょっと遠いかもしれないけど。確か往年のダンスステップが自慢だっていってたよね」
「あ、あれは……
「そうだっけ? でも、いい機会だから遊びにおいでよ。本物のワンレンボディコンのお客さんもたくさんくるからさ」
わ、ワンレン、ボディコン……。
憧れのフレーズだった。
肉を表する言葉でいえば“シャトーブリアン”と同格の誘い文句だ。
「わ、わかりました! 俺、参加します!」
「お! いいね。それじゃさ、待ってるよ。店の場所と招待状も送っておくからさ」
「あ、ありがとうございます!」
“誠心誠意の一礼”を残して応接室からログアウトした。
現実に戻る、と、途端に大きな音がした。
VRルームの、ドアをしきりに叩く音。
「ハルノキくーん! あけてよぉー」
そうだ、鍵をかけたままだった。
「ひどいよぉ、ハルノキくん」
ドアを開けると、まもるさんがジュースの入ったグラスを握りしめて立っていた。
「すみませんでした。つい。集中したくて」
「ジュース飲んでたら、店員さんに怒られちゃったよ。部屋で飲んでくれって」
「な、なんすか? そのドリンク?」
グラスの中には、どぎつい蛍光色の液体が揺れている。
「これね、すごいんだよ。1杯で1000キロカロリー! すごく甘いんだよ!」
「や、あの……」
「おかわり何回もしちゃったよ」
この人、やっぱりバカなのかもしれない。
まもるさんが、VRチェアに割り込んでくる。
「ふう。疲れた」
ドリンクを飲む姿に、負の感情がわく。
「ところでさ、ハルノキくん。ボク、VRしたことないんだ! 体験してみたいよぅ!」
「してみたらいいんじゃないすか?」
「そんな、つめたいよぉ。教えてよ、ねえ」
この人が、年の離れた幼い妹や弟なら、柔らかい気持ちで対応できたのだろう。
歳を考えろ。甘えるな。
「ねえねえねえねえ」
「少し調べ物してからでもいいですか?」
「調べ物? 豊川さんからの宿題?」
「いやあ、まあそれに近いんですけど」
豊川さんと、棚田さんとの話し合いのことをかいつまんで話した。
「それじゃ、そのディスコに行くの?」
「リアルのダンスコンテストなんで、行かなないと話にならないですよね。だからどうやって行こうか調べておこうかなって」
「そっか、ボクは南の方にはあんまりいったことないなぁ。どうやっていくの? 飛行機?」
「ひ、ひこうき……は、ムリです」
イヤシちゃんがいなければ、飛行機にのることはおそらく不可能だ。
「じゃあ、どうやって? リニア? 結構お金かかるね」
確かに。
そういえば、金のことをまったく考えに入れてていなかった。
往復の旅費を出してしまったら……、いや。そもそも仕事が決まらない状態で、あと1ヶ月生きていけるかすら怪しい。
「……まもるさん、俺……ダメです。あきらめます。守衛所で働くの」
「どうしたの!? 急に」
「旅費も生活費も、考えてませんでした。秋までに条件クリアするのムリです。俺、舐めてました世間のこと」
甘い。甘い。ジュースのことを揶揄している場合じゃない。もっとも激甘なのは己自身だったのだ。恥ずかしい。
「大丈夫だよハルノキくん。ボク結構お金あるからさ」
見上げると、ほころんだまもるさんの
「一緒に行こうよ。棚田さんのお店。ハルノキくんの分の旅費はボクがだすから」
「そ、そこまで甘えらんないっすよ」
「一緒に守衛所で働こうっていったじゃない。ボクも一緒に行くよ」
デブ、デブ、と内心で罵ってきたことを痛切に恥じた。“ふくよか”だ改めよう。
まもるさんの形容詞は“ふくよか”が適切だ。
恵比寿様か大黒様か、そうだ福の神と同列と考えを改めるべきだ。
「まもるさん。お言葉に甘えていいんすか」
「気を使われたらボク、緊張しちゃうからそんなに改まらなくていいよお。それより、どうやって行くか決めておいた方がいいんじゃない?」
「そうでした。mi……あ、そうか」
misaを呼び出そうとして、ひらめいた。せっかくならまもるさんにVRを体験してもらおう。
「まもるさん、せっかくならVRで調べてみませんか? 体験してみましょうよ」
「ホントに!? やったぁ!」
「まもるさんゴーグル持ってるんですか?」
「なに? ゴーグルって」
「VRチェアに座って潜るなら、
「ワーキングクロスならあるけど」
「なんすか? その手ぬぐい。それじゃあ、自分のメガネ使ってください」
「いいの? ありがとう! これ、初期化とかするの? 本人確認とか」
「メガネにはimaGeチップいれてないんで、特に認証いらないっすよ。まもるさんのチップと連動させて使ってください。俺は、コンタクトレンズでアクセスしますから」
検索するくらいなら、コンタクトでも問題はないだろう。まずは、まもるさんの気分をあげることが優先だ。
「メガネ掛けたら、たぶんimaGeの視野内に、この店のチャットルームのアイコンが出てるはずなので、それを選択してください」
「えええっと、これかな」
「じゃあ、中で会いましょう」
本日、3度目のログインだった。
『ブリンカー』に入り浸っていたころのような、もしくは“覚えたて”の中学生のような回数。
チャットルーム『VRカフェ−Room5』は、最低限の応接セットがあるだけの殺風景な内装だった。予算がつかわれていないのがすぐにわかる。
ルーム内を見渡したが、まもるさんの姿が見えない。メッセージには『現在2名 ログインしています』あるのに。
「ハルノキくん、ログインできたよ」
「ねえ、こっちだよこっち」
よくみると、点線で囲まれた人型がみえた。
「そっか、まもるさん本当にはじめてのログインなんですね」
「どういうこと?」
「いま透明人間みたいな状態ですよ」
「ハルノキくんは見えてるのに?」
「まずは、まもるさんのアバター作りましょう。視野内に“
点線の前に鏡が現れた。
「できたよ!」
「そうしたら、クレイの“
「こ、こうかな」
現実のまもるさんにそっくりなアバターが表示された。
「鏡をみてください」
「ん? だれ? この小太りじいさん」
「まもるさん、鏡みたことないんですか?」
「これボク?」
「はい。そのボタンは、本人の身体をスキャンしてそのままアバターにしてくれるんです」
「ええ、少し太めになってるよね。やだなこんなおデブちゃんなの」
デ、いや、ふくよかな体型は認識しておいて欲しい。
「もちろん、そこから髪型をかえたり、体型や顔も自由にいじれますよ。そのままいじらない強者もいますけどね、たまに」
チクリンと豊川さんの顔が浮かんだ。あの2人は単に面倒だからそのままの姿をさらしているのだろうか。
「それじゃあ、体型いじりましょう。“体”のアイコンないですか? それを選んで全体を80%くらいに縮小してみてください」
「こうかなぁ」
目の前のアバターがみるみるうちに痩身していく。
「うわぁ! かっこいいねこれ!」
細身に修正しすぎではないか。元のまもるさんからなら3人分くらい取れるほど細い。
「すごいねこれ。決めた! ボク痩せる!」
「それ、最初っから決まってたことじゃないんですか……」
「痩せる! そうだ! ハルノキくん。お店まで歩いていこうよ! いっぱい歩けば痩せられるよねきっと」
「あ、歩くんすか!? お店、九州の方ですよ」
「ボク決めたよ歩く! ねえ、ハルノキくん歩いていったらどのくらいかかるか調べてみよう」
「ほ、本気ですか?」
「うん!」
「まあ、調べてみますけど。misa聞こえる?」
『なーにー? 珍しいねこっちに呼び出しするなんて』
「あ、あのさ、ここからこの場所まで歩いたらどのくらいかかるか調べてほしいんだよ」
棚田さんの店の住所を伝えた。
『はあ? 歩くの? 2人で?』
「まもるさんが、どうしても痩せたいって」
『なかなか面白いこというね』
「ボクこの体型になれるまでがんばります!」
『元の体型から考えたら40キロくらい減量が必要だけど、歩行で消費するなら、ちょうどいいんじゃない? ここからなら20日くらいあればつくと思うし』
「20日もかかるの? まもるさんやっぱりやめません? ムリですよ」
「大丈夫! ボクやる! やるよ! misaさん、詳しいルート考えてください!」
まもるさんの目に一切の曇りはなかった。さっきまで驚異的なハイカロリードリンクを飲んでいたとは思えない決意に溢れた表情だった。
VRチェアは睡眠には適さない。
中には寝具としても使えるリクライニングタイプのものもあるけど。
うっすらと目を開けると、天井でまもるさんが浮き寝していた。
昨日、といっても数時間前、この店のVRルームで検索したあと、ログアウトもうやむやに寝落ちしてしまったようだ。
まもるさんが浮かんでくれて助かった。この狭い空間に男2人が重なって寝るのは想像するのもはばかれる光景だ。
『ねえ、そろそろ出ないと延長料金かかるけど大丈夫?』
『アンタたちさホントに、今日から歩くんだよね? アタシ本気ルート考えたんだからちゃんとやってよね』
これ、これはきっとmisaなりの“ガンバレ”なのだととらえて自分を鼓舞した。
今日から、歩くのか、片道約1000kmの道のりを。本当に?
いいだした本人はまだ眠りこけている。
「も、もちろん、やるよ」
『そっ、でもさぁ、もうそろそろ出発の予定時間なんだけど』
「まもるさん! 起きてください! 早く!」
寝ぼけて靴もまともに履いていないまもるさんをひっぱり、部屋を後にした。
店のレジに、昨夜の屈強な深夜スタッフの姿はなかった。
「ハルノキくん、まだねむいよぉ」
「出発の予定時間過ぎたら何言われるかわからないんです。目を覚ましてください。それから、あの、会計おねがいします」
「う、うーん」
寝ぼけながら会計するまもるさんの姿に多少、良心がいたんだけどそんなことをいっている場合ではない。misaのルート、プランからそれることの方がまずい。
階段を降りて外へ出ると、まだ薄暗く真夏の陽射しはまだ鳴りを潜めているようだった。
「ねえ、misa、いま何時?」
『ただいまの時刻は、5:40です』
「ま、まだ早いんじゃない?」
『5分くらいは早いね計画より』
「5分って、そんなにタイトスケジュールなの?」
『人間がよくいう、5分前行動でしょ。それじゃあ、スタートするよ、まずは、直進開始! 5時間以上道なりだよ』
なんて、雑なナビゲーションなんだろうか。
なにかに没頭すると、時が経つのは早い。
薄暗かった辺りは、いつのまにか明るくなり、太陽は真上に昇っていく。夏の暑さが猛威をふるいはじめると、衣服に覆われていない皮膚の部分は否応なしに汗が滲みはじめる。
したたる、水滴を拭いながらひたすら歩いていくと、周囲は再び夜へと向かっていく。
陽が傾き、朱くなり、やがて闇が訪れる。
飛行機にのった昨日は濃密なイベントが密集していたせいか、時間の流れが緩慢だった。
しかし、今日はどうだろうか、気がつけばもう、1日が終わろうとしてた。
ひたすらに歩いた日だった。
「ま、まって、ハルノキくん! もうだめ。少し休憩。うん。あ! アイス!」
『……ッチッ……』
あからさまな、舌打ちが脳内で聞こえた。
まずい。
『なあ、ハルノキ』
「は、はい!」
街中で、脳内音声にこれほど反応したのははじめてだった。人目も気にならなかった。
『なんだよ、あの、デブ』
「いや、あの、た、体調とかもありますし」
『限度ってものがあるでしょ、今日1日の歩行距離……』
「はい」
『9.8km……』
臨空第九都市の面積は広いが、人口は中心部に密集している。つまり「疲れたーアイスー」とコンビニに走り込めるということは、まだ中心部すら離れることができていないということだ。
『いくらなんでも、おかしいだろ?』
要因はすぐに特定できる。
コンビニからアイスを握りめて出てきたあの、デ、いやふくよかな男のせいだ。
『あの、アイスでこの1時間分の消費カロリーはチャラです。今日の摂取カロリーと、途中、目を盗んでホバーベルト使った距離を差し引いた8.7kmの歩行距離で消費したカロリーを計算すると、摂取カロリーの方がうわまわっています』
本当に、まずい。
このアシスタントプログラムの口調が、事務的になるということは、いよいよ本域の怒りをかっていることになる。
なんとかしなき──
脳内で、『ポーン』と、軽快なチャイムが突然、鳴った。
『まもなく目的地周辺です。案内を終了します』
「あ、いや、まってください」
『周囲に注意して、安全につとめてください』
「あ、ああの」
『お疲れ様でした』
もはや弁明の余地すら与えられなかった。
呼びかけても有能なアシスタントプログラムからの反応はない。
「ハルノキくんも食べる? 疲れたでしょ」
間髪いれずにこんどは、無邪気にアイスが差しだされる。無言で払いのけた。
「あああ、どうしたの?」
「まもるさん、なにしてんすか?」
「ん? 休憩だよ。休憩」
「今日、何回休憩とったかしってますか?」
「ん? 1時間に1回くらいだよ」
「そのたびに、お菓子たべたり、ジュース飲んでたら、意味、ないですよね」
「あ! そっか! でも、明日からがんばれば大丈夫だよ」
明日は、もうねーんだよ。
ナビゲーションしてもらえない状況であんたと歩くのはリスクでしかない。
「まもるさん、ここどこか知ってますか?」
「知らない」
ほらみろ。土地勘もない。
ここはどこだ? 中心部から中途半端に離れた場所だ。コンビニの他には数店の得体のしれない店しかない。どこでどうやって泊まるんだ? 飯はどうする? 引き返そうにも、同じ時間をかけたら朝になってしまう。
「こんなんじゃ絶対ムリです。やめましょうこの計画、ムリなんですよやっぱり」
「そんなこと言わないでよぉ。明日からちゃんとがんばるからさ」
「1日に10kmあるけないんじゃ、九州まであるくってムリに決まってるでしょ」
「明日はもっと歩けるから! きっと!」
「じゃあ、どこに泊まるんすか? 徹夜で歩きます? 俺、いやですよ」
「泊まるって、ホテルとか、昨日みたいにVRカフェとかでもいいよ」
「どこにあるんすか? 街灯もまばら、店もほとんどない。ここにホテルとかVRカフェとかありそうですか?」
「ほ、ほんとだ。何にもないね。misaさんに調べてもらおうよ」
「はい、そのアシスタントプログラムさんは先ほど営業終了のお知らせがありました」
「そ、そうなの? 困ったなぁ……あ、あ!」
今度は定食屋でもみつけたのか。
「あれ、ハルノキくんあそこでピカピカしてる看板」
まもるさんが指さした方向には、派手な電飾でイカした看板があった。
『ニュー・トリップ』と書かれている。
薄暗くて建物の全体はみえないが、なにかの店舗のようだ。
「トリップって、旅のことだよね?」
「危険な意味合いを除いたら、そうですね」
「もしかしたら、泊まれるところかもよ!」
確かに、泊まれそうな気はする。
でも、看板に……。
「まもなく締切って書いてありますし、ホテルとかだとしても、もう満室なんじゃないすか」
「とにかくいってみようよ!」
まもるさんが、ホバーベルトで浮遊していた。
ダメだ、あの人。
「すみません! このお店は泊まれますか?」
突撃に近いような勢いで店にはいったまもるさんの後から『ニュー・トリップ』の中に入る。
天井から垂れ下がるカーテンで仕切られた空間の奥に『受付』という立て札がおかれたカンターがあった。
カウンターの中には、ワイシャツにネクタイを締めた礼儀ただしそうな男の人が座っていた。
「い、いらっしゃいませ」
まもるさんの声に圧倒されたのか声を詰まらせた。こんな時間に申し訳ないと思う。
「ここは泊まれるところですか?」
「ま、まもるさん、いきなり大声だしちゃだめですよ」
「あ、ごめんなさい。泊まれますか?」
急に声を潜めるな。耳元で囁かれたみたいで気色が悪い。
「申し訳ございません。当店は宿泊施設ではありませんでして……」
「そうですよね。いきなり失礼いたしました」
「それじゃあ、なんのお店なんですか?」
はじめて言葉を喋りだした子供のようだ。疑問点を包み隠すこともなくまもるさんが聞いた。
「はぁ、あの、まだ店というほどの状態にはなっておりませんが、移動のお手伝いを……」
「移動? レンタホバーカーとかすか?」
つい聞いてしまった。
「いえ、あの、て、テレポーテーションで目的地へお送りするようなかたちでございまして」
まもるさんと見つめ合ってしまった。
「て、テレポーテーション!?」
まもるさんも言葉の意味を知っていたのか、声が重なってしまった。
「え、ええ。あの、テレポーテーションはご存じですか?」
「知ってます! たけしさんがいってましたよね?」
「た、たけしさんは存じ上げませんが、つい先日ニュースで取り上げられまして、それで、ここに拠点を構えていこうと、その準備中に近いかたちで細々とスタートしまして……」
失礼ながら、細々という言葉がよく似合うほど小さな声を出す人だと思った。
「す、すごいです! 好きなところにいけるんですか!」
「はい。ご指定をいただければ素早く」
「ハルノキくん! これで九州に行こうよ!」
「九州までいかれるんですか?」
「はい!」
「で、でももう締切とかなんですよね」
「確かに、その大変好評でして、お待ちになっているお客様も大勢おりまして……」
「えぇーもういっぱいなんですかぁ?」
「しかしながら、お客様は比較的近場なので、なんとかなるかもしれません。料金も抑えられるかもしれませんし……」
「いくらぐらいなんですかぁ」
「はい、ええと……」
店員さんは“電卓”と呼ばれる古風な機械で計算して金額を掲げた──
「高っ!」
「安いよ! ハルノキくん! だって、テレポーテーションだよ! かっこいいなぁ。ねえハルノキくん、テレポーテーションしてみようよ! ボク、九州についたらちゃんと痩せるから!」
「で、でも、高いっすよ」
「大丈夫だよ! 貯金も合わせればなんとか足りるから! ボク、こんなにわくわくしたのはじめてかも! 乗りたいなぁ、乗りたいよぉ」
テーマパークのアトラクション前、あるあるじゃないんだから。そんなベタな駄々をこねないで欲しい。
「確かに、今回を逃すと、次のテレポートは来月になってしまいます……申し訳ございません」
「ホラ! 今しかないよ! ボク、痩せるのはなんとかするから!」
「失礼ですが、痩せると申しますと」
「本当は九州まで歩いて痩せるつもりだったんです!」
「そ、そうでしたか、それならば、今回、テレポーテーションが普及した際に懸念される運度不足による肥満増加を危惧しまして、痩身効果のあるサプリメントもご用意しておりますが、そちらもおつけいたしますか?」
「はい! お願いします」
「か、かしこまりました。それでは、こちらのご契約書にサインをお願いいたします」
まもるさんが、契約書にサインを入れ、imaGe決裁まで速やかにすませた。
「ありがとうございます。それでは、まずは待合室でお待ちいただきます。ご案内いたします」
「はい! いこう! ハルノキくん!」
「は、はい」
細身の店員さんが受付の脇にあるカーテンをめくる。
「こちらへお願いします。順番にお呼びいたしますので、お待ち頂けますでしょうか」
カーテンの奥は、確かに混んでいて、10人くらいの人がソファに掛けている。
待合室の雰囲気は、ちょうど『ショルダーパッド』の応接室を広くしたような場所だったけど、ソファは残念ながら少し硬めだった。
次回 12月29日掲載予定
『 ニュー・トリップ -4- 暗い、フライ 』へ
つづく
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする