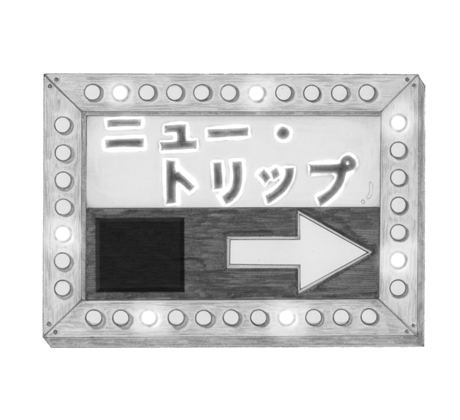第33話『 ニュー・トリップ-4-暗い、フライ』
冷房は効いていたが、壁中に張り巡らされたカーテンが暑苦しく、ソファが狭いせいか人の密度も高かった。
「でも、実際どうっやってテレポーテーションするんでしょうね? サカエさんはご存じなんですか?」
「いろいろ調べてみたんですけど、どこにも出てないんですよね。気になりますよね」
「なんか、でかい音がするらしいんすよね」
「あ、そうなの? 僕、大きな音はちょっとダメだなぁ」
「あ、オレは、テレポートする瞬間、とりあえず光るって噂っ聞いたことあるっすね」
部屋に先に入っていた人達は、コの字型のソファにそれぞれ陣取り、テレポーテーションの方法について話し込んでいるようだった。
「大昔の映画でありましたよね、テレポーテーション中に紛れ込んだ別の生物と人間が合体しちゃうって話」
「やだー、社長、ワタシこわーい」
ふくよかな体型でワンピースを身につけた女が、隣の中年に抱きついた。
「大丈夫だよ、大丈夫、ワタシがいるじゃないか」
社長と呼ばれた中年が女の腰に手を回す。
「やだー社長、だめー、まだ。みんなみてるからー」
「いいじゃないか、それも秘書のつとめだろう。もうな我慢できないんだよ。マリちゃん、もうな、あっちに着いたらスグだからな、スグ! グフフフ」
あんなに、わかりやすい下心を丸出しにしてなお女性の心を求心できるのは金の力か、それとも、社長と秘書という権力の関係なのか。こんな世界が本当にあるのか。
「まもるさん、なんかいろんな人がいますね」
「うん? ホウダ、ヌ」
まもるさんはテーブルの上に出されたお菓子を一心不乱に口に運んでいた。
「な、なんでそんな一気に食べてんすか?」
「テレポーテーションってすごくお腹がすくらしいって、……えっと」
「あ、鳥目いいます、鳥の目ってかいて鳥目です」
まもるさんの隣に座っていた、短髪の大男が名乗った。
「そう、鳥目さんがいうから」
「兄ちゃん名前は?」
「あ、は、ハルノキっす」
「おう、ハルノキくんも食った方がいいよ、とにかく腹減るらしいから」
「そ、そうなんすか?」
「なんかな、先輩がいってましてね、テレポーテーションするときは腹減るって聞いたことがあるって」
確かに、お腹はすいていた。今日一日歩きまわって何も食べていなかった。まもるさんは、散々食べておいてまだ食うのか。
「み、みなさま、お待たせいたしました!」
お菓子に手を伸ばそうとすると、部屋の中に、フロントにいた細身の店員さんが入ってきた。
「ご歓談中のことと存じますが、こ、これから、テレポーテーションに関する注意事項をお伝えいたします。わ、わたくし、ホソイです」
メガネを直しながら一生懸命話している。胸元に『細井』とかいてあった。名前もそのままだったか。
「ええと、まず、これから準備でき次第、順番にお呼びしていきます。1番目は……え、ええと、ヒビノ様」
「はい!」
元気よく返事をしたのは、ちょうど反対側の正面に座っていた好青年だった。自分とそんなに歳は変わらないようにみえる。
真夏だというのに、シャツの第1ボタンまでしっかりと止めていた。
「それではヒビノ様から、順番にお呼びいたします。そ、そこでご注意なのですが、各組様のテレポーテーションごとに準備がございますため待ち時間が発生する旨、あらかじめご容赦ください」
「ねえ、ボーイさん、どのくらい時間がかかるの? ワタシたちね、急いでるんだよ」
“社長”が、人差し指をぷるぷると震わせながら声をだした。
「明日の会議までには帰らないとだからな。マリちゃんと2人で会社休んじゃったらな、噂になっちゃうもんな、グフフ」
「やだー社長。ギリギリまで一緒だからねー」
「ホテル直行できちゃうからな直行」
「観光とかしないのー」
なんなんだあの2人は、その辺のホテルでイチャイチャしてればいいじゃないか。
「あ、あの、はい。私どもも尽力いたしますので、お時間につきましてはある程度、ご理解を……」
「ベッドの真上に頼むよ、キミぃ」
「ぜ、善処いたします。で、でも、ホテルのご手配と、チェックインだけは忘れずにお願いいたしますね。……そ、それでは、あの……次のご注意事項です。テレポーテーションの際には、大きな音がいたします」
サカエと呼ばれていた男ともう1人の男が「ホラ、ホラ」と指を差し合っていた。
「そ、そこで、当店特製の耳栓をご用意いたしておりますが、なにぶん数に限りがございまして……、あ、もちろん、耳栓なしでも問題はないのですが、ご希望の方はいらっしゃいますか?」
「ください!」
サカエがピンっと手を挙げ、立ち上がった。
「あ、ありがとうございます。5,800円です」
「え! お金とるの!?」
「は、はい。あの、申し訳ございません。なにぶん、特製なものでございまして……」
サカエが渋々、現金を取り出すと、いつの間に部屋に立っていた入口のゴツイ男がすかさず回収しに席まで歩いた。
「ほ、他にご希望のかたはいらっしゃいせんか、残り2つになります」
「ワタシとマリちゃんにくれ」
考える間もなかった。社長が即座に購入してしまった。金の力なのか、やはり。
サカエと社長の間に挟まれた、半袖の派手なシャツをヒラヒラさせた青年がうらやましそうに左右を眺めていた。
「そ、それでは続きまして、こちらもテレポーテーションの際の対策ですが、強い光を伴いますのでアイマスクをご用意いたしました……ご希望のか……」
全員が即座に手を挙げた。自分も値段を聞く間もなく手を挙げていた。これは必要だ。目は大事だ。
「み、みなさまご安心ください。こちらは全員分のご用意がございますので、1セット1万2千円になります」
「ま、まもるさん……」
「もちろん、大丈夫だよ! 任せといて」
まもるさんが、2セット受け取って手渡してくれた。た、頼りになる。本当に。
「みなさま、ありがとうございますぅ。それでは、続きまして、テレポーテーション中にはですね、あの、まれに、まれにですよ、テレポーテーション酔いになることがございます」
部屋の中が一瞬ザワついた。
「聞いてないっすよ! そんなの」
派手なシャツの青年が立ち上がったが、細井の後ろでゴツイ男が反応したのをみてゆっくり座った。
「あ、あ、もちろん、安全ですよ。なったとしても、乗り物酔いの数倍程度の……あ! 安全ですから、安全! まれに、まれにそういったことがございまして。安全ですよ! 安全!」
強調されるほど不安になる。
「そこであの、当店では専用の酔い止めをご用意しておりまして……、ツルオカさんあ、あれをお願いします」
あのゴツイ男はツルオカというのか。手に小さなドリンク瓶を持って立っている。
「少々、お値段が張るんですが……」
「いくらっすか!? あんまり高いのやめてくださいよ」
青年が声だけ威勢良く聞いた。
「え、ええ、あの、1本5万8千円で、その……申し訳ないんですが限定5本となります」
「おーい! ボーイさん、こっち2本くれ!」
社長が即座に手を挙げた。
「は、はい、ありがとうございます」
ツルオカが瓶を運んでいった。
「あ、ぼ、僕も」
栄と呼ばれていた男も手を挙げた。
「ありがとうございますぅ、ほかの方はいかがですか」
「ぼ、ボクもください!」
まもるさんが手をあげた! やっぱり頼れるなこういうとき。
「はい、2本でよろしいですか?」
「あ、あの、1本でいいです」
「え!? まもるさん?」
「ご、ごめんねハルノキくん、もう、あんまりお金、なくて。ハルノキくんは若いからきっと大丈夫だよ」
「なんすか、それ」
「あ、社長さん、オレ、順番かわるっす! だから、その……奢ってください」
「ん? そうなの? そうか順番はやくなるのか、しょうがないなぁ」
反対側の席では、派手なシャツの青年が、社長にたかりはじめていた。
「おーい、ボーイさん、彼にも1本お願い」
「社長、ありがとうございまーす!!」
青年が“社長”に深々と頭を下げ、ドリンクを受け取りっていた。
隣の席では、まもるさんがドリンクの栓をあけて口をつけている。
「ん、あ、これマズーイ。甘くないヤツだ」
子供か。
「は、ハルノキくん半分飲む?」
「い、いや、間接キスとかいいっす」
そこまでして、“乗り物酔い”を避ける意味がわからない。……いや、まて。
よく考えてみたら“乗り物酔い”ってなんだ。遠足の話題になると大人達がよく話していた気はする。「昔はバスが揺れたからー」とか「今のホバーカーは揺れないから最近の子は乗り物酔い知らないのよー」とか。
考えてみたら、経験がない。
それほど辛いものなのか。未知の感覚……、少し怖くなってきた。
「ま、まもるさんやっぱり半分くださ──」
「え! 鳥目さんにあげちゃったよ」
横で鳥目さんが一気に飲み干していた。
「おっすまんな……ちょっとなら残ってるぞ」
瓶を差しだされたが、固辞した。
それから、各種テレポーテーショングッズ販売を行って細井とツルオカは出ていった。
結局、アイマスクしか手にはいらなかった。
「いやぁ、結構かっちゃいましたね。アレ? ヒビノくんは、アイマスクも買わなかったの?」
対面の席でサカエがヒビノに話しかけていた。
サカエは、耳栓、アイマスク、ドリンクそれからテレポーテーション手袋にテレポーテーションルームウェア、ルームシューズまで買いこんでも、まだ余裕そうだ。
それに対してヒビノは、結局なにも買わなかったようだ。
「そ、そうなんです。値段きいたらびっくりしてしまって……」
「あぁーなるほどぉ。ま、まあ安全っていってましたし、ヒビノくん若そうだし大丈夫だよ、きっと」
サカエという男、完全にまもるさん理論だな。
「そ、そうですよね……」
「でもヒビノくん。そんなギリギリな予算でどこにいくの? わざわざ、テレポーテーションしてさ」
「その……、ニューヨークに留学している彼女にどうしても会いたくなってしまいまして」
「あぁ、なに、学生さんなの? ヒビノさん。しかも遠距離恋愛っていうヤツかぁ。……わかるわぁ……」
「わかってもらえる人がいて良かったです。テストも近くて時間が取れなくて、夏休みは会えないなと思っていたときに、テレポーテーションできるって聞いて。それを知ったらもう、どうしても会いたくなってしまいまして……でもプレゼントのお金だけはとっておかないとで……ハハ、貧乏学生が贅沢ですよね」
屈託なのない笑顔というのか、ヒビノが笑ったのが見えた。歳はそんなに変わらないと思うけど、しっかりしてるな。
「そうかぁ、学生さんは大変だよね」
「なんか、急にすみませんでした。……サカエさんはどちらへいかれるんですか?」
「僕はぁ、そのぉ……ラスベガス……」
「観光ですか?」
「いやぁ……カジノでひと儲けしようと思っててね……」
「すごい! 必勝法とかあるんですか?」
「10年……」
「え?」
「10年集めてきたデータね、解析してたらさ……わかっちゃったんだよ。ルーレットの赤と黒がどの順番ででるか、全部。たまに自分が怖くなるよね。明日の分なら全部わかるんだ」
「そういうことあるんですか?」
「明日の分しかわからないから、どうしても今日! 今日、ベガスに着かないと意味がない」
「そ、それで、テレポーテーションなんですね……」
「ほーん、同じ国に行くんでも、えらく目的違うもんなんですなぁ」
いきなり、鳥目さんが会話に参加していた。
気づけば周りの人達が数人ヒビノとサカエの会話を聞いていたようだ。
「あれ? 聞かれてましたぁ?」
サカエが照れ笑いするのを、無視して鳥目さんがヒビノに話しかける。
「学生くん。彼女のことが好きなんだな!」
「はい! 卒業したら結婚しようと思っています!」
その言葉で場に温かい空気が溢れた。
『……あ、えー、1番席ヒビノ様、ヒビノ様』
突然、天井からアナウンスが流れた。
『テレポーテーションのご準備をお願いいたします』
「あ、ヒビノくん呼ばれたね」
ヒビノの顔が若干、緊張したようにみえた。
『ヒビノ様 ヒビノ様、ご準備できましたら、奥のカーテンの中へお進みください』
「あ、それじゃあ、みなさま。お先に失礼いたます!」
ヒビノが立ち上がり、場に一礼した。
「おう! 行ってこいよ学生!」
なぜか一同から拍手が起こった。
「みなさまも、良い旅を!」
入口と反対側の壁のカーテンをめくり、ヒビノが中へ入っていた。
「うわぁ、いっちゃいましたね。次、僕だぁ。なんか緊張する、あっ! ヒビノくんとimaGe ID交換しとけばよかったなぁ」
サカエが独り言をつぶやきはじめた。
「あっちで会えたら彼女の友達紹介してもらえたかもしれないのに……」
小さい男だと思った。
「そういえば、トモイリくん、キミはどこへ行くんだ? エライ軽装だけど」
“社長”が派手なシャツの青年に話しかけはじめた。イチャつくのに少し飽きたのか。それとも、興奮しすぎたせいか。
「あ、自分すか? 自分、ヒマラヤっす」
「ヒマラヤぁ? そんな軽装でか。だって、足元、ビーチサンダルじゃないか!」
“社長”の怒鳴り声に、一同が注目する。
「い、いや、だってほらテレポーテーションだから一瞬じゃないですか、だからいいかなって」
トモイリがしどろもどろに、返事をする。“社長”の顔がさらに赤くなる。
「キミ! 山を舐めるな! いいかね、山はあれだ、怖いんだ! そんな、近所のコンビニに行くような格好で! ビーチサンダルはビーチに履いてく物だよ」
「まぁまぁ、社長さん、穏便に」
割って入ったのは鳥目さんだった。
「こっちの兄ちゃんにも、なにか理由あるのかもしれませんし、なぁ?」
場を取りなせるのは、大人だと思う。ああいう人になりたい。
「自分、写真撮ろうと思ってて、はじめての登山でヒマラヤ登頂した写真家っていう感じでデビューしようとおもってまし──」
「オマエ、写真舐めたらあかんぞ!」
鳥目さんが、トモイリの胸ぐらを掴んでいた。
「そんな簡単に写真家になんかなれるか! ワシがどれほど努力してきたと思っとるんじゃ!」
「あ、え、え、と、鳥目さ……んて、しゃ……しん……か……?」
「おう! 写真家じゃ! 夜景の写真撮ってるんじゃ、文句あるか!」
「な、な、ないっす」
「ま、まあまあ、あの、そのくらいで」
“社長”が、いなす側にまわっていた。
「あ、すません。つい。でもな、オマエ、トモイリ! 写真はなそんな簡単に目的地に行って、パシャッとやって終わりじゃねえぞ!」
「は、はい。すみませんした」
トモイリが土下座のような格好で座っている。
「あ、あの、それじゃ鳥目さんは、ど、どこに行かれるんですか?」
若干落ち着いてきた鳥目に、サカエがそっと尋ねる。
「ワシか? 月だ」
「月?」
「おお。月だ」
鳥目さんの格好は、テントにリュック、寝袋、ライフジャケットそのたもろもろの探検家スタイルで、軽装ではないけど……宇宙感は……ゼロのようだ……が、それを指摘する猛者は現れな──
「そんな! 死んじゃいますよ!」
まもるさんがいた。
「そんな格好で宇宙にいったらダメですよ、鳥目さん、宇宙舐めてますー?」
「え? ダメか? 一瞬、息止めてたら?」
と、鳥目さんも大概、アレのようだ。
「ダメですよ!」
「そ、そうか、一瞬、息を止めながら月の写真をこう、カシャとやって、帰ってこれればとおもったんだが」
「だって、スグに帰りのテレポーテーションできないかもしれないじゃないですか!」
まもるさんの言葉で、全員が動きを止めた。
「あれ……そういえば……」
サカエが辺りに語りかける。おそらくその疑問をみんながたった今、抱いたはずだ。
「帰りの方法、ご存じの方……いますか?」
「そ、そういえば、説明されてないな」
「もしかして、金かかるっすかね」
「時間がかかるのは、困るな」
口々に疑問がでてくるということは、誰も知らないということだ。
「おい、トモイリ、ちょっとフロントにいって聞いてこい」
鳥目さんとトモイリの間にはいつのまにか、上下関係ができあがっているようだった。
「う、うっす」
トモイリも見えない上下関係を暗黙のうちに受け入れているようだ。鳥目に対し軽く頭をさげ、小走りでドアへ駆け寄っ──
「は、はぁ?」
途端に間抜けな声を上げた。
「は、は? は?」
「お、おいどうした、トモイリ?」
「いや、鳥目さ、い、ちょ、ちょ動いてるっす。や、ちょ、ちょっと見てよ」
思わず敬語を忘れるほどのことがあったのか。
「なんじゃい、どうし──はぁ!?」
ドアに近づいた鳥目さんも奇声を上げた。
異変を感じ自分もドアへに近づ、くと……。
「はぁぁ!?」
へ、部屋、部屋が、部屋が、地上から浮いていた。いや、浮いているだけでなくそのまま、疾走感あふれるスピードで滑走中だった。
「え、え、こ、これ、ホバーカー……」
「もうね。これ以上の揉め事はこまるなぁ、ホテルの予約時間も迫ってるんだ……ああ、本当だ。動いてるねぇ」
“社長”の呑気な声がやたら耳につく。
気づけば背後に人が集まってき──
『本日の営業は終了いたしました。みなさま気をつけてお帰りください。毎度ありがとうございます。良い旅を』
天井から、ベタな“閉店のメロディ”とともにアナウンスが流れだした。misaとは違う無機質さで、明るく抑揚のある女性の
『本日の営業は終了いたしました。みなさま気をつけてお帰りください。毎度ありがとうございます。良い旅を』
アナウンスを一文違わず、2回繰り返してやんだ。瞬間、少しだけ体が揺れた。
「あ、とまった」
サカエのつぶやきで外をみると確かに、“部屋”が滑走を停止していた。周囲は暗闇に包まれているようだ。
「お、おい! 外出てみろ、トモイリ」
鳥目さんが怒鳴った。
「こ、これは一体……」
部屋の明かり以外なにもみえない。
地面が柔らかい場所ということだけは靴の裏の感触でわかった。
おそらく誰も理解できていないんだろう。みな辺りを呆然と見渡しているだけだった。
「ジョコ? ココ? ハルノキシュン、シュッシェル?」
「わ、わかるわけな……ま、まもるさん、どうしたんすか!?」
まもるさんの口元から、赤い液体がしたたっている。え、ケガ?
「ンン? シュイシャ?」
「シュイシャ? なんすか?」
もしかして話せないくらいのケガ……。
「ウン……、うん。スイカだよスイカ! ここにお落ちてたんだ」
まもるさんが両手で、穴が開いたスイカを抱えていた。野生の熊か。このごに及んで食い物で人に心配をかけるなデブ。
し、しかし、スイカが落ちていた?
「まもるさん、そ、それ落ちてたんじゃなくて……」
よくみてみると、周囲の土からは、たくさんの茎が出いていた。
「栽培されてるんじゃないっすか?」
「え、なんで? こんなところで?」
「わ、わかんないすけど、畑なんですよ!」
「確かに畑だよな」
鳥目さんが聞きつけて近くにきた。
「ニュー・トリップって街中にありましたよね? なぜ、いつのまにこんな所へ……」
……そういえば、受付の2人は退室してから、1度もみていない。そういえば、なぜ、呼出が突然アナウンス方式になったんだ……。
「も、もしかして、騙された?」
「なんだとハルノキ! 騙された?」
鳥目さんの大声で、みんなが目を見開いた。
「え? 騙されたの!?」
「うそー、マリ、怖い!」
「え? うそだぁ」
全員が混乱しはじめていた。
「どういうことだ、ハルノキ?」
「ニュー・トリップの待合室とフロント以外の部屋をみた人はこの中にいますか?」
誰も手を挙げなかった。やっぱり。
「フロントの2人が部屋をでてからずっと、建物だけ、ここまで自動運転で浮遊走行してきたんですよ。揺れもないから、中にいた自分たちが気づかない間に」
「え、そ、それじゃ、ヒビノくんは?」
サカエが間抜けな表情でいった。
「おい。トモイリ、カーテンの奥をみてこい」
トモイリが「うっす!」と発声して部屋の中に戻っていって、すぐに出てきた。
「カーテンの奥なんにもないっす! なんか穴だけあいてました!」
その穴から脱出したんだきっと。
ヒビノもグルだったのか。
「くっそぉこのボケ」
鳥目さんが“部屋”の外壁を蹴った。
「あ! あ!」
蹴られた“部屋”は、斜めに傾きはじめ、そのままペシャンと平面になった。
「あ? え? ちょ、ちょっ!」
さらに手先の器用な人が折り紙を折るように、「パタン、パタン、パタン」と音が聞こえそうなほど畳まれていく。高速で。
「おい! なんだよこれ」
折りた畳まれ、人間1人分くらいの立方体になった“部屋”の上部から、プロペラのような物があらわ……ブン……ブン……ブンブンブンブンブンブンと勢いをつけたと思ったら、急に光りだして空に舞い上がった。
「あ! 逃げるぞ!」
「ま、まもるさん! 飛んで!」
まもるさんはまだスイカを食っていた。
「え、え?」
「スイカいいから、アレ捕まえろデブ!」
思わず、いってしまった。
「え? うん? わ、わかった!」
まもるさんが、素早く地面を蹴った。
「あ! あの人、飛んでるすげー」
「逃がすなぁ! 捕まえろ!」
全員が口々にまもるさんの名前を連呼し、空を見上げる。
光は凄いスピードで離れていったが、少しして、急にガクンと光がぶれた。
「おっ! 捕まえたか!」
光が小刻みに暴れだした。
「よし! イケェ! そのままや、そのままああぁ!」
鳥目さんが競馬場のゴール前で飛び交うようなかけ声をあげた。
まもるさんを振り払おうとしているのか、ドローンの光はきりもみしながら、どんどんと上昇していく。
「ま、まもるさん!」
一緒になってまもるさんの体が上空へのぼ──
「なんだ、あれ!」
サカエが指さした方向から、けたましいサイレン音と、大量の赤い光が迫ってきた。
「あれ、上空警備隊のドローンじゃない?」
サカエがつぶやいたときには、すでに赤い光の軍団がまもるさんとドローンに絡みついていた。
「あっ、捕まった」
次回 2018年01月12日掲載予定
『
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする