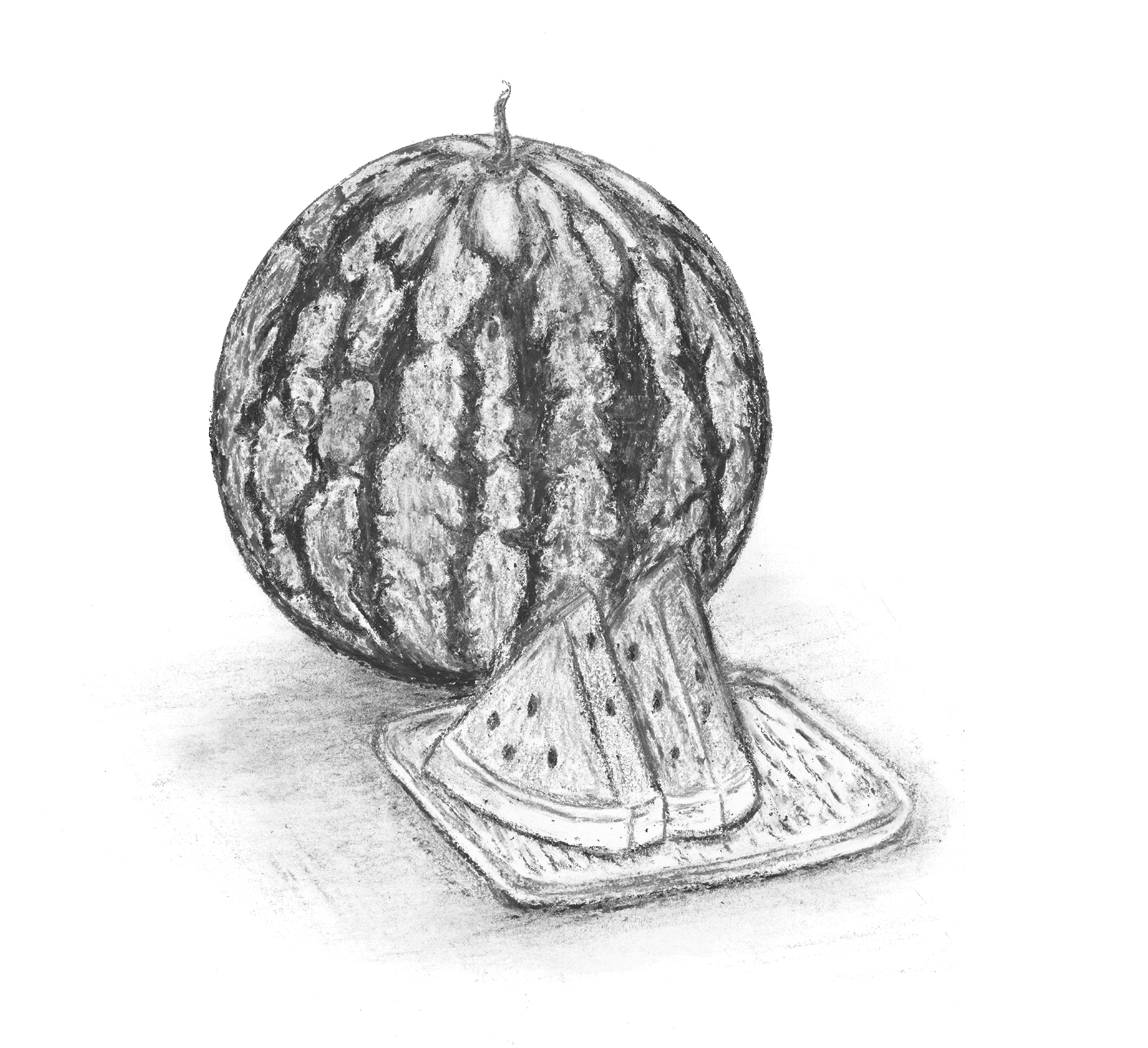第35話 『 誰何 の西瓜 -2- 』
蝉の声の騒々しさに耐えきれず目を開けると、天井がみえた。
『”
自分のimaGeが、初めて検知した物体の名前を示す“
木製の天井は“
いや、今そんなことはどうでもいい。
ど、どこだ、ここ?
布団に寝かされているようだ。
左右へ首を動かすとまもるさんと、セイジも寝ていた。
広い部屋。
”
こんなに純和風な場所になぜ、自分が横たわっていたのだろう。
そうだ、あの爆風で……。
あのまま気を失ってしまったのか。それとも、本当にどこか別の時代へ飛ばされてしまったのではないか。
まもるさんもセイジも呑気に寝息を立てている。障子が開け放たれた“
「ね、ねえ、misa、無事?」
セイジが寝たふりをしていることを警戒して小声で話しかけるとすぐに
『アタシ吹っ飛んでたら、アンタは話できてないと思うよ』
よかった。いつもの調子に戻っていた。
「ここ、どこかわかる? というか、いま何年の何月?」
『なに? そのタイムトラベル物の主人公みたいな質問。2063年7月17日11時38分。場所は“田子ノ蔵”家』
「その田子ノ蔵って人についてさ、なにか知って……る……っ!!」
叫び声を上げそうになった。
襖がいつの間にか開いて、高齢の女性が正座していたからだ。
「起きたね」
女性は、表情を変えずにいった。
見えていても、問題ないよな? 見えていていいんだよな。この人。
意表をつかれすぎたせいか、言葉を発せず頷くのが精一杯だった。
「その2人も起こしなさい。ご飯にするから」
「びっくりしたよね、ホントに! ボクもうだめかと思ったよ」
まもるさんが、ごはん粒をほとばしらせながら口を開いた。いつみても米が似合う。
「キャベツうまいっすね。これだけでご飯3杯はいけますね」
セイジも掻き込むようにご飯を口へ運ぶ。キャベツをおかずに3杯って、普段なにを食っているんだ。
それにしても、順応性の差なのだろうか。なぜ、この2人は見ず知らずの家でこれだけくつろげるんだ。
「そっちのお兄さん、おかわりは?」
さっきのお婆さんが、“お
「あ、じ、自分はもうお腹がいっぱいで……」
「ぼれなば、ぼぶがばべるよ」
口いっぱいにご飯を詰め込んだまもるさんが茶碗を差しだした。遠慮とか、恥じらいとか、警戒心とか、いろいろと爆風に吹き飛ばさてしまったのか、もともとないのか。
「はいはい。めっちゃ食べたらいいよ。イナサクにも、怪我人は殴れないから、めっちゃ食わせて元気ださせとけっいわれてるから、遠慮しないで」
お婆さんの目元と口元にやさしそうなシワが丸まった。
まもるさんが箸をとめた。
セイジはペースをかえない。
「あ、おかわりいいっすか?」
茶碗を差しだした。
「それにしてもウケるねーあんたら、わざわざ爆発の真ん中に走ってくんだもんね。ウチのじいさんも、間が悪いから、昔から」
「あ、あれは……、なんだったんですか?」
「8番さんの庭の岩の、爆破だよ」
「は、8番? ……爆破……。……爆薬……使う必要が……あるんですか」
ずいぶんと豪快な作業じゃないか。
「なんでって、そりゃ“演出”だから」
「演出? 誰かがみてるんですか?」
「上の人だよ、上」
そういって、お婆さんは人差し指を天に向かってくいくいと突き上げた。
「じょ、上空の人達ってことですか!?」
さも、こともなげに首肯された。
「それ、どういうことですか?」
そのとき、豪快に扉がひらく音がした。
「おう、帰ったぞ!」
「イナサクたちが帰ってきたね」
「ハルノキくん、は、早く謝って!」
「ちょ、ちょっと、やめてください! 自分でちゃんと謝りましょうよ!」
まもるさんをみると、口もとにごはん粒をつけたまま、目元に涙を浮かべていた。
「きっと、だ、大丈夫ですって、まずはせ、説明してみましょう」
とはいってみたが、「庭石を爆破」という言葉が重くのしかかった。危険な集団な気がしてならない。これ以上巻き込まれるのは嫌だ。
このまま2人をおいて逃げようかと思ったが遅かった。
背にしていた襖が軽快な音を立ててひらいた。
「ばあちゃん、帰ったぞ……おっと」
戸口を振り返ると、鴨居で半分くらい顔が隠れた状態で男が立っていた。で、デカイ……。
「おう、おめえら、起きたか!」
「みんなにご飯食べさせといたよ」
お婆さんの声に促されるように、のっそりと鴨居をくぐってきたのは、黒々しい短髪をツンツンにたて、髭を蓄えた男だった。
ま、まずい。表情がすでに険しい。
殴られるどころか、頭を“スイカ割り”されてもおかしくない。イナサクと呼ばれた男の首元に巻いた真っ赤なタオルが、血を連想させた。
よくみたら、頭の左右の髪の毛だけが長く、角のようにたてられている。表情だけはなく、髪型まで鬼のようだ。
イナサクは、畳にすわりこみ、こちらをみた。
「……誰だ」
「ひぇっ」
まもるさんが悲鳴のような声を上げた。
「スイカを食ったのは……誰だ?」
詰問や拷問を受けたわけでもないが、即座に「すべて白状してしまいたい」と本能が叫んだ。
セイジも同じことを感じ取ったのかもしれない。2人同時にまもるさんを指さしていた。
「ぼ、ボク、ボク、ボクではありませぬる!」
まもるさんは、態度で自白している。
「おまえじゃ、ないのか?」
まっすぐに、まもるさんを見据えた。
いまあの人の視野内には、
「ぼ、ボクじゃ……ボク、ボクが食べました」
「やっぱり、おまえが食ったのか?」
あっという間もなく、ぐっとイナサクが胸ぐらをつかみ、まもるさんに顔を寄せた。
「あ、あ、あ、あ」
「一瞬、嘘ついたな。なんでだ?」
双方の額がピタリとくっつく。
まもるさんはまっすぐに、イナサクを見つめている。男女ならラブシーンにしかみえない。
「ボクが……やり……や、やっぱりやってません!」
「やっぱりって! なんだ! ああ!」
「ぼ、ボクです! ごめんなさい! な、殴ってくださいぃぃ!」
「よし、良い度胸だ!」
スッとイナサクの右手が後方に伸びた。それこそスイカすら握りつぶしそうなほど大きな手の平だった。
「ぬぐぐぐぐ」
まもるさんが目を固く閉じて歯をくいしばる。見たこともないような皺が顔中に充満していた。
「ぬぐぐぐ」
「殴って全部が解決するとおもうのか? ああ?」
「ぬぐ、ごめんなさいいい! それじゃ殴らないでくださいぃぃ!」
手の平が近づくのがわかるのは本能なのか。手の平の距離に合わせ、まもるさんの顔面の皺が動く。
「反省してねえな! おまえ!」
「な、殴ってくださいぃ!」
「よし」
「やっぱり、やですぅ! ごめんなさいぃぃ」
まもるさんは、本格的に涙をながしていた。
「はっきりしろ! なんでスイカ食ったぁ! あのスイカがどれほど大切なものか分かってんのかぁ!」
「うっ、ぇぐっ、ご、ごめんなさい」
胸ぐらを掴まれしゃくりあげながら話す姿に少し心は痛んだが、助けられるほどの勇気は持ち合わせていない。
「おまえ、いくつだ!」
「ろ、63歳ですぅ」
「うちのじいさんとそんなに変わらねえな。それなのに、善悪の区別もつかねえのか!」
「あ、あの、お腹がすいて、あ、あの、あの、お、お、お金はちゃんと払いますぅ」
「金……? いいか。金じゃねえ! 物事がなんでも金で済むと思うなよ! いいかあのスイカはな…………imaGeだ。ちょっとまて」
まもるさんを解放して、イナサクは耳に右手の平を押し当てた。おそらく、imaGeの通話ジェスチャーなんだろう。
放心した状態のまもるさんが、口を半開きにさせたままイナサクをみていた。
「どうした? ……なんだと! さ、サマー・オブ・ロマンスが植えられてるぅ!? ホントか? それ? おっしゃー!」
イナサクが奇声をあげ体を反転した勢いで、左の手の平がまもるさんの頬にクリーンヒットした。
甲高い破裂音だった。
「うぐきゅ! いだいいい」
イナサクは「すまん。間違えた」とつぶやいてから左手も耳元に添えた。
「ばあちゃんも聞いとけ」
『んだぁよぉ、いまさっき15番の畑が急に植えだしたんだ。もうちょっとで100株になるよぉ』
相手の声が流れてきた。両手を両耳に添えるとスピーカー状態になるようだ。
「ひゃっ、100株っておい、1,000万円じゃねえかよ!」
『んだぁよ、だけど、そんだに苗あったかなと思ってぇ、それによぉ、17時のスキャンまでにオラひとりでどうやって植えっかなと思って連絡したんだ』
「苗はハウスにあっから心配すんな! あとは人だな! 人集めてすぐいくから準備しといてくれ! よっしゃよっしゃよっしゃ! 1,000万だ、1,000万! ばあちゃんデッケえ仕事はいったぞ! 金だ金ぇぇ!」
「いだいよぉぉぉ。殴られた! 駐在さぁん」
「うるせえ! ばあちゃん! 放送でみんな集めてくれ! よし、おまえらも手伝え! まずは苗を取りに行くぞ!」
「オ、オレたちもっすか?」
セイジは恐怖という感情が薄いのか、あのビンタを間近でみてよく質問ができるものだ。
「罰だ罰! スイカ食った連体責任だ! いいから全員働け! 急げ! 17時のスキャンに間に合わねえ!」
家の外にでると、陽射しが容赦なく照りつけてきた。この時間からがちょうど陽射しのピークなんじゃないか。
「ちょっと暑すぎねーっすか、オレ、倒れちゃおうかもしんねえっすよぉー」
「そういえば、おまえ……名前は?」
いくぶん落ち着いた声に戻ったイナサクが、セイジに尋ねた。
「友煎セイジっす」
「そうか。セイジ……」
「は、は──」
セイジが返事をするまもなく、平手が舞った。
「気合いがたりねーんだよ! いいか、金だ! 1,000万だぞ! それからスイカ! おまえの名前はぁ!」
イナサクの顔が、うずくまるセイジを顧みず、まもるさんに向いた。
「ぼ、ぼぼぼ、ボクはまもるですぅ」
「まもるか、よし。オマエは!」
「じ、じじ、自分は、は、ハルノキです! 桜と書いてハ、ハルノキですぅ!」
「妙な名前だな」
心を動かされるな。なにもいわなくていい。逆らうなと自分に言い聞かせた。
名前をけなされただけだ。あのビンタを喰らうほどのことじゃない!
「よし! まもると、セイジは荷台に乗れ。桜は助手席だ」
庭先に止めてあった、クルマを顎でしめされた。タ、タイヤのついた、古びた小型のトラックだった。
「ハ、ハルノキくぅん。ぼ、ボクたちどうなっちゃうの……」
「まもるさん。いまは従いましょう」
トラックはどんどん山道を登っていく。こ、こんなに揺れるのか、タイヤのあるクルマというのは。若干恐怖を覚えた。
……まあ、運転席で前方を睨みつけているこの人に対する恐怖に比べればたいしたことはない。
「いいか、桜、いまから山の上にあるハウスから苗を運ぶ。1株10万だ。絶対に落としたりしないように着いたら後ろの2人にも伝えろよ!」
「じゅ、10万もするんすか!? その苗」
「“夏苺”知らんのか? まあ良いモノ食ってなさそうだからな。夏に植える苺だ。
イナサクがタバコをくわえながらいった。
「吸うか?」
「や、じ、自分は……」
「そうか」
「あ、あの、い、イナサクさ、ん」
「なんだ?」
「苗を植えてるって、ど、どこで植えてるんですか」
「上だよ」
さっきお婆さんがやったのと同じように、イナサクは人差し指で空を指した。
「上? じょ、上空都市ですか?」
「そうだよ。この村は、みんなそれで飯くってんだよ」
「野菜や果物の販売とかですか?」
「ふんっ。そんな小せえ商売じゃねえよ」
<ガガ…… あ、あー、エマージェンシー、エマージェンシー、TA-GO内で高額課金がありましたー。植え付けのために全員15番畑“ワールドエンド”に急行されたし。エマージェンシー、エマージェンシー……>
さっきのお婆さんの声が聞こえてきた。
窓から顔を出してみると、空中にエアロスピーカーが浮かんでいるのがみえた。
「あ、あの放送は……」
「緊急招集だ。ばあちゃんは仕事が早ぇな」
クルマの速度が上がった。こ、こんな細い道であまり速度を上げないで欲しい。
「あ、あの、ターゴーっていってたのはなんなんですか?」
「T、A、G、O、
くわえタバコのままイナサクが、口の端を持ちあげた。
「“上”でよいっときVRの
「は、はぁ……そ、そうなんですか?」
「そんなことも知らねえのか? いいか? まずはよ、上のヤツらが、わーきゃーわーきゃーいいながら農業体験するんだよ」
「楽しそうな感じっすね」
「そうだよ、フィットネス感覚とかいいながらよ、“ふぅーいい汗かいたねー”とか“やっぱり自然に触れるのはいいわ”なんて、エアコンが効いた部屋でいいながらな。で、その農業体験で植えた苗やら稲を
イナサクが表情を変えず「くくく」と笑った。
「それがさっきの、苺の苗なんですか?」
「そうだよ。毎日8時と17時によ、地形の状態やら、作物の生長状態をまるごとスキャンしてデータとってVR内に反映するんだよ」
「じゃ、じゃあ、苺の苗というのは」
「17時までに植えとかねえとクレームがくる」
「そ、それを人力でやってるんですか?」
「じーちゃん、ばあちゃんが、いっぱいいるからなこの村には。最近は真似されて
まっすぐフロントガラスを睨みつけるイナサクの横顔をこっそりとみてしまった。クレイジーなだけでなくクレバー人なのかもしれない。
「そ、それにしても1,000万はすごいっすね」
「『TA-GO』のシステム自体も、フランチャイズみてえにいろんなとこに卸したけども、この
「
村の地図看板にあった“竜良村”の文字を思い出した。あの16番まであった機械的な区割りの畑それぞれに上空市民の所有者がいるということか。
「あだ名だったんだけどな」
「あ、あだ名すか?」
「昔、麻雀のトーナメントで村長決めてたんだよこの村。それで、いつのまにか竜良村ってよばれてな。まあ、そんな調子だから当時はこの村、廃れててな。若いヤツらみんな出てってよ。まあ、もれなくオレもな」
「でも、戻ってきたんですか?」
「ああ、上空でいろいろやってみてな、やっぱり地上がいいなと思ってよ」
「じょ、上空市民だったんですか!? イナサクさん!」
「ああ、歴代の村長が金貯めて市民権買ったんだよ」
「す、すごいっす!」
「そうか? そんなことねえよ」
イナサクが苦笑いをしてタバコを指に挟んだ。
「上空ネームも持ってたぞ」
「上空ネームってなんすか?」
「なにも知らねえんだな若いヤツってのは。上空市民になるとな過去のしがらみとかなんだを捨てるために名前を決められるんだよ。オレはちなみに稲穂の稲に村に漢字の百で
「は、ハンドレットって、なんかバブリーな名前っすね」
「そんなしゃれたもんじゃねえよ。米をつくるには八十八の苦労があるっていうんだけど……、まあ知らねえだろな。上じゃそれよりも苦労したからな。百なんだよ。それで、まあ、降りてきて、コネ使って仮想農業のシステムつくったんだよ」
「それで、いまは大儲なんですね」
「いや全然だ。ブームってのはいつか廃れるんだよ。最近、“畑”にでねえ所有者が増えた。あいつら飽きるのが早ええからな。だからこの仕事は絶対にしくじれねえんだ。じーちゃん、ばあちゃんが食いっぱぐれたら困るからな」
そんな、大事な農地だったのか。
「も、もしかして、あのスイカも……」
「ああ、そうだよ。、あれ作ってる畑の人がこの一帯のなかじゃいちばんいいお客さんなんだよ。まあ、1個だったから今朝のスキャンはダミーの映像差し込んでごまかしたけどな」
「す、すみません。いや、自分があやまることじゃないかもしれないんすけど」
「しっかり働いて返して貰わねえとな。っと。よし、着いた! 降りて苗を積み込んだらスグ畑にむかうからな!」
“ビニールハウス”の前でクルマが急に止まった。
シートベルトに身体が食い込んで戻った。
初めてかもしれない。
ちょっと本気で頑張ってみようと考えていた。
次回 01月26日掲載予定
『
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする