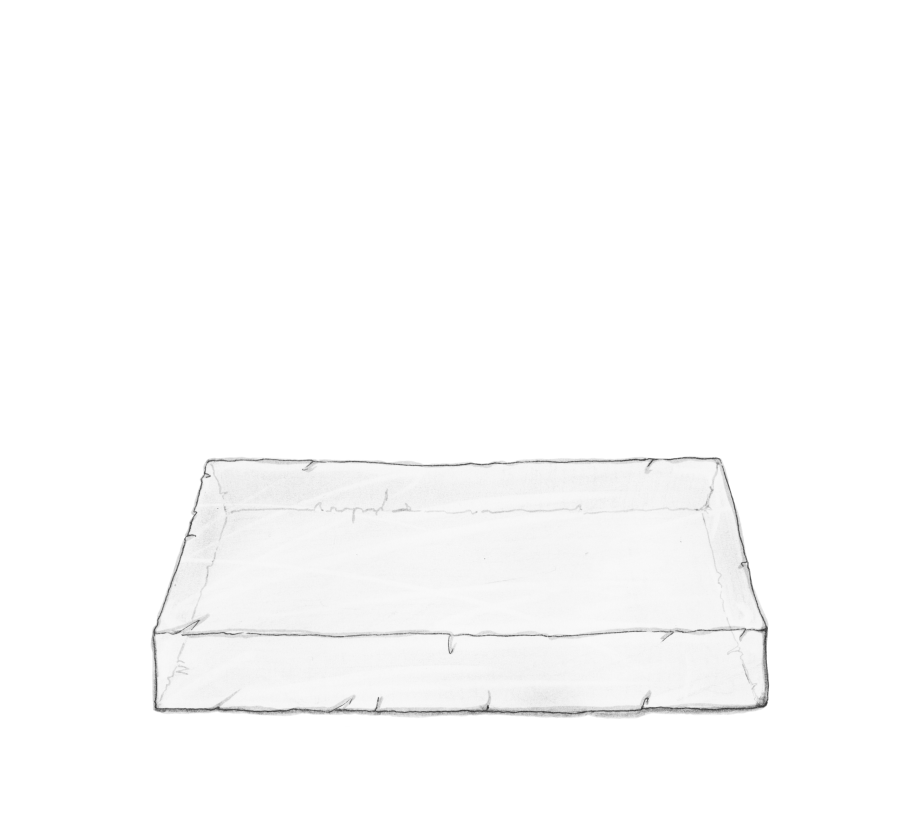第43話 『 まもる、朝陽 の中で…… 』
「自分たちに何を飲ませたんですか!」
食堂に声がこだました。かまうもんか。
他に利用客はみあたらない。
「まもるさん、明らかにおかしいじゃないですか! 急に怒ったり、食欲なくすなんて……」
「大丈夫ですよ」
しかし、正面に座る南先生はにこやかに繰り返すだけだ。表情からあどけなさは消え、逆に子供に諭す大人のような、辛抱と慈悲が溢れた顔だった。
「大丈夫、大丈夫って、逆に不安ですよ! じ、自分だって同じ薬を飲んでるんだし……」
「まもるさんの方はいたって順調なんです」
「ま、まもるさんの、方は……?」
微笑む表情のまま急降下した南先生の声色にひるんでしまった。
「ええ。むしろ、桜さんの方が心配です……」
「ど、どぉういうことですかぁ!?」
声が裏返った。
「知井さん、ここに横になりましょう」
「国立せんせい、ボク、大丈夫なんですか?」
「心配ないですよ、知井さん。心配ない。心配ない。とってもとっても順調です!」
「ボク、こ、怖いですぅ」
国立せんせいと部屋に戻ってきてからちょっとだけ、気持ちの悪さはおさまったけど、あんなにご飯がおいしくなさそうにみえたことなかった。
「いまは、ゆっくり休みましょう。明日の朝にはかなり落ち着いてるはずですから。知井さん、このお薬のんで今日はもう寝ましょう。とっても甘くて飲みやすいですよ」
「は、はい……」
ボクは国立せんせいがくれた、甘い液体を飲んだ。なんだか、とっても眠くなっ──
食堂で、南先生と話ていた……はず……。
しかし、気がつくとベッドの上だった。
薄目を開くと、天井にしらけた光が射し込んでいるのがみてとれた。
無意識にimaGeの視野を見上げる。
時計は『AM5:24』を示す。
まさに、放課後、ハッと保健室で目覚めたような焦り。
周囲にただよう、消毒液のような香りがそんな気分にさせた。
眠ってしまったのだろうか?
いや……眠らされたんだとしたら……。
この研究所がおかしいことは確定だ。
そうだ。ま、まもるさんは!?
身体を起こす。
カーテンに囲まれていた。
もどかしい思いでカーテンをあける。部屋全体はまだ薄暗い。
隣のベッドのカーテンは隙間なく閉じていた。
ここがまもるさんのベッドだろうか?
手を伸ば……
「ああああ!!!! いでぇぇぇぇぇ!!!!」
部屋の中を絶叫が満たした。
驚きで身体のあちこちがこわばったりゆるまったりした結果、最終的に肛門が甲高い音を奏でた。
「はい! 大丈夫ですよぉー」
国立さんの声がした。
「ゆっくり息しましょうねー、そーれ」
南先生の声もする。
「もうちょっ! もうちょっとです! がんばって! それ……」
聞こえてくる2人の声は、場違いなほど明るく、リズミカルに絶叫の主を励まし続ける。
「あががががががががぁぁぁ」
だが、絶叫はやまない。
声の方向に目をこらす。
部屋の1番奥のカーテンの中だ。
よくみると中で動き回る人の気配もある。国立さんと南先生だろう。
「出てきましたよ! それ! もっと力をいれましょう」
「あぁぁがが、ああ、あああああ」
本能を振り絞るような声……いや、これって、だ、だ、断末魔というやつじゃないか?
こ、これは……、本当にシャレにならない場所に足を踏み入れてしまったのかもしれない。
も、もしくは、ゆ、夢なのか?
いや、視野内のフィールド表示は『現実』のままだ。仮想空間が入り乱れるimaGeにおいて、この表示だけはどんなときでも正確に自分の精神位置を伝える。
つまりここは紛れもなく、現実世界。
あんなに苦しそうな声に張り上げる人……。
「あぁ、あぁ、うぐぼぉがぁ……ああぁッ!!」
ひときわ大きな絶叫の直後、なんともいえない、不気味な音がした。
トマトを素足で踏み潰したような、水を含んだ雑巾を床にたたきつけたような、耳に残る、不快な残響。
叫びは荒い息づかいに変わっていた。
「おおぅ、おおおぅ、おおおおぅ」
男性の野太い、獣のような息づかい。
「おめでとうございます! 見えますか? お疲れ様です! すごいすごいっ!」
国立さんの素っ頓狂な声。
「やったねぇ! おめでとうっ!!」
南先生の声もすこし興奮しているようだ。
「おぉ! ワシやったんじゃな」
「すぐに鳥目さんの成分を調べましょう!」
鳥目? 鳥目さんって!?
聞き覚えのある名前。
いや、ついこの間……。
そういえば、あの声は……。
ベッドを飛び出し、奥のカーテンへ走った。
震える手に、ぐっと力をこめ直して、カーテンを開ける、飛び出してきた国立さんと衝突しそうになった。
「おっと、失礼! 南先生、急いで!」
「はいっはーい。あら、桜さんは、まだ寝てないとダメだよぉー」
2人は小走りで駆けていった。
「いやぁ、まさかこんな
ベッドに残された鳥目さんは、豪快に笑っている。
「と、鳥目さん、無事なんですか?」
精気のある表情だった。とても直前まで叫び声をあげていた人とは思えない。
「無事もなにも、やり遂げた達成感と、爽快な気分にワシは感動しとるぞ!」
「か、感動ですか?」
「それにしてものぉ、
あの店で会ったときと変わらず、よく響く低音で笑う鳥目さんに、竜良村での出来事を話した。
「そうか、そうか、トモイリもちったぁマシになりそうなんだな」
セイジの近況を喜んでいるようだった。
「それで、オマエらは金がなくなって、ここに来たと」
「そ、そうなんです。あの……ところで、鳥目さん、なんであんなに叫んでたんですか?」
「ん? なんだオマエなんにも知らんのか?」
「は、はい……」
正確にいえば、説明を受けたような気もするけど、国立さんの話が長くて、わからないままに誓約書に
「ハルノキ、そりゃあ注意力散漫だな。これがもし本当に悪いヤツらの仕業だったら、オマエ、それこそ本物の玉とられてもおかしくねえぞ」
「は、はい……すみません」
でも、こうして鳥目さんが無事なところをみると、い、命はとられないようだ。
だが、身体は全く逆の反応を示している。いまさらになって震えが止まらない。
「なんじゃ? オマエ、震えとるぞ、ダメだ。身体を冷やすんじゃない。いまが1番大事なときだろ。ほらベッドに戻れ」
手払いしながら鳥目さんが立ち上がった。
「ど、どこに行くんですか?」
「ん? ちょっとな……、なんちゅうか、母ちゃんに連絡をな……謝ったり、礼をいったりせにゃあならんなあと思ってのぉ」
ポリポリと頬を掻きながら歩いて行った。
ど、どういうことだ?
気がつけば“教室”の中に取り残されていた。
カーテンの閉じられたベッドが、ひっそりと息を潜めるように並んでいた。
まもるさんは? どこだ?
鳥目さんの叫びにかき消された思考が蘇る。
冷静に考えてみれば、隣のベッドか。
管理する側にしてみても、被験者が並んでいたほうが監視するのが容易なはずだろうから。
予想通り自分の寝かされていたベッドの隣はカーテンが閉まっている。
そっと近づき、カーテンの隙間を覗く。
やっぱり。
まもるさんが、寝かされていた。
毛布にくるまり寝転ぶ姿は熊の冬眠を覗いてしまったような気分になる。実際に遭遇したことはないけど。
「ま、まもるさん……?」
呼びかけると、肩がぴくっと反応した。
「ぬぬ、んん? は、はるのきくん?」
よ、よかった。意識がある。
「だ、大丈夫すか?」
「アレ、ボク、寝てた……?」
目を擦りながら起き上がってきた。
冬眠から冷めた熊のような……仕草……
「ま、まもるさん?」
「んん? なぁに?」
「そ、その身体……ど、どうしたんすか?」
明るくなりはじめた、朝陽に照らされたまもるさんの身体は……。
「んん? なぁに?」
「身体、ふくらんでません?」
飛行機の中のスナック菓子のように、ぱんぱんに膨れあがっていた。
「ん、そうなの?」
まもるさんは寝ぼけた口調のまま自分の姿をみまわしているだけだった。
「ボクとっても眠いんだ…ぁ…」
そのまま横になり、また寝息を立て始めた。
に、二度寝している場合じゃないだろう。
明らかに異常だ。
普段から標準的な体格よりは恰幅がいい、いやそりゃ……平たく言えば“デブ”だけど、それにしたって……。
もしかすると薬が……。
言葉にすると急激に不安がむくむくと沸きあがってくる。
鳥目さんは無事だったけど、あの人は、特別なのかもしれない。
やっぱり、逃げるべきなのだ……。
“楽して稼ごう”なんていう魂胆がマズかった。
あの冷徹で高飛車なアシスタントプログラムの説教が身に染みた。
いや、それでもこれはまだ、笑える失敗の域なのかもしれない。
『もっともっと失敗してこいよ』
イナサクさんの言葉もリフレインしだした。
そうだ。
いま逃げ出せれば、これはきっと笑い話にできるはずだ。間一髪、危機を乗り越えた武勇伝にできるんじゃないか。
まもるさんを助けよう!
もう一度カーテンに手をかけ、まもるさんを起こそうと踏み出すと、後ろから肩を掴まれた。
食堂で南先生に掴まれたことがフラッシュバックする。振り返ると、今度は国立さんだった。
(いまは寝かせておいてあげてください)
小声で囁きに手の平で外へ出るよう促された。
優しくゆっくりと首をふるしぐさに、気持ちが一気に萎えていった。
廊下にでると正面の大きな窓から空がみえた。夏の1日のはじまりを告げるのにふさわしい晴天だった。
普通の状態でこの景色を目にしたなら、きっと心地よい気分に浸れたのかもしれない。
しかし、いまは違う。心に黒い雨雲のような不安が膨らんでいる。
「あの、国立さん。あの薬はいったい……」
「南先生からお聞きしましたよ。ずいぶんと不安になられているって」
曇天の隙間に一瞬、表れた晴れ間のように、国立さんの表情が射し込んだ。
「よく説明をお聞きになってなかったんですね、ボク、説明が下手なもので不安にさせてすみません。もう一度きちんとご説明いたします」
校舎の中央にある階段までたどり着くと、また丁寧な仕草で手の平が差しだされた。
「桜さん、階段は上れそうですか?」
国立さんが階上を示しながら尋ねてきた。
「へ? も、もちろんっすよ」
「それでは、屋上へでてみませんか?」
校舎の屋上──
階段をのぼる後ろ姿についていく。
一段踏みしめるたび、大きな鉄扉が近づく。
あの扉がきっと、屋上への入り口。
足を踏み入れてもいいのか?
喉が渇く。背中にうっすら汗が浮かぶ。
「じ、自分、学校の屋上なんて初めてっす!」
笑われるかもしれないが、前置きせずにいられなかった。いざ、屋上にでて“屋上未経験”がバレるのが少し恥ずかしかった。
「ハハハ、実は僕もあまり来ないんです」
予想外だった。
この人も屋上慣れしていないというのか?
自分の学生歴のどこを振り返ってみても、屋上を自由に使える学校なんて存在しなかった。
厳重な管理のもと“立入禁止”だった。
そう、そこには“校則”という壁がある。
校舎の屋上──
それは、絡みつく“制約”を易々と乗り越える
あれだけ気軽に誘ってきておいて「ボクも屋上慣れしてないっす」なんてことがあるのか?
「
昨日の夕方聞こえてきた“ブオーン”は練習中の音だったのだろうか。
「わたくし、人がたくさんいる環境がいまいち苦手でして」
国立さんが、耳元をカリカリとかいた。
「わかります。自分も人が多い場所はあまり好きじゃないっす」
「でも、桜さんを見ていたら一緒に登ってみようかなとおもいました。学校の屋上っていう響き、なんだかドキドキしますよね」
「そうなんですよ! なんていうか、クラスの人気者みたいなのがチャラチャラ遊んでる場所っていうか、自分はそういうのなかったんで」
校舎の屋上──
授業をエスケープし、または放課後に示し合わせ、ある者は許されざる嗜好品を嗜み、またある者は、異性との逢瀬を重ねる。
学生生活を、そして青春を、心から謳歌する人々が集う場所。いわば、
一歩、また一歩、近づく
「桜さんそんな風にはみえないのになぁ」
「そ、そんなことないっす! それよりも国立さんこそ、モテたんじゃないっすか」
国立さんは細長い指をドアノブに掛ける。
僅かな隙間から日光が入り込み、国立さんに降り注ぐ。スラッとした長身で、これだけ物腰やわらかく振る舞う人ならモテるに違いない。
「全く。全然ですよ。暗かったんです、学生のころから」
しかし、国立さんは自嘲気味に鼻を鳴らす。日光に照らされた横顔が少し哀しげにみえた。
過去の自分に照れ、そしてその自分をしかたなく赦すように。
ゆっくり扉が解放された。
暗がりで萎んだ瞳孔に白い光がさしてくる。
imaGeでVRにログインするときのようだ。
視界がホワイトアウト。
耳にはビートの効いたラジオ体操の
屋上の光だ。
ここが聖域、屋上……ラジオ体操?
なぜ?
いやそもそも、ビートが効いたラジオ体操ってなんだ。
混乱したまま凝視した。
視界が戻るにつれて、人影が浮かびあがる。
極彩色のレオタード姿の女性が鉄柵の前で、一心不乱に踊る。
髪を振り払うように激しく身体を回し、跳びはね、手足を極限まで伸ばしきる。
体格のよい肉感的な肢体が、まるで太陽への捧げ物のように躍動している。
「な、なんだよ……アレ……」
ラジオ体操は、こんなにキレのある動きなのか。竜良村でみた緩慢な体操はなんだったのか?
国立さんが顔をしかめたまま呆然という。
「ナツメさん、今日、朝練だった……の?」
ナツメというのが、あの
す、すごい。
降り注ぐ光が縁取る彼女の輪郭が目に焼きついてしまうようだ。
「も、戻りましょう。桜さん」
国立さんは、慌てながら踵を返したが
「ちょっと! 大学! なにしてんの?」
ビートをつんざくようなダミ声に怯えたように肩をすくめた。
ナツメと呼ばれた女性が腰に手をあて、憮然と立っている。
身につけているレ、レオタードのむ、胸元は、お、お、大きく盛り上がり、こぼれるようだ。
「ナ、ナツメさん! おは、おは、おはようございま……」
国立さんは挨拶すら最後までいえていない。
「なに覗いてんのよ!」
ナツメさんが、ズンズンと歩み寄ってきた。
「ち、違います! ち、ちが」
「アタシ“おはようレッスン”の日はここでアップしてるの知ってるでしょ?」
「あ、い、いや、その、忘れてました」
「ウソつきなさい! イヤラシイ!」
「い、いやいや、ち、違います!」
「あれ、アンタ、みかけない顔だね」
そ、そんな古典的なおてんば娘のようなセリフをいとも簡単に吐く人がいるのか。
ナツメさんの視線が自分にむけられた。
腰に手を当てたまま。いぶかしげに、窺うように、上目遣いでねぶりあげてくる。
しかし、視線の奥は楽しげで妖しげな光に満ちているようにみえる。
「なかなか、カワイイ顔してるね」
丸みのある鼻は、黒く塗りつぶしたら愛嬌のある、犬顔かもしれない。しかし、鋭い目元は愛玩犬ではなく猟犬だ。
こ、怖い。
「そんなにみたいなら、みてってみるぅ? あたしの“ステージ”」
ナツメさんはぷっくりした紅い唇の両端を、ぬらりと釣り上げた。
次回 03月30日掲載予定
『 まもる、アウト オブ まもる 』へつづく
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする