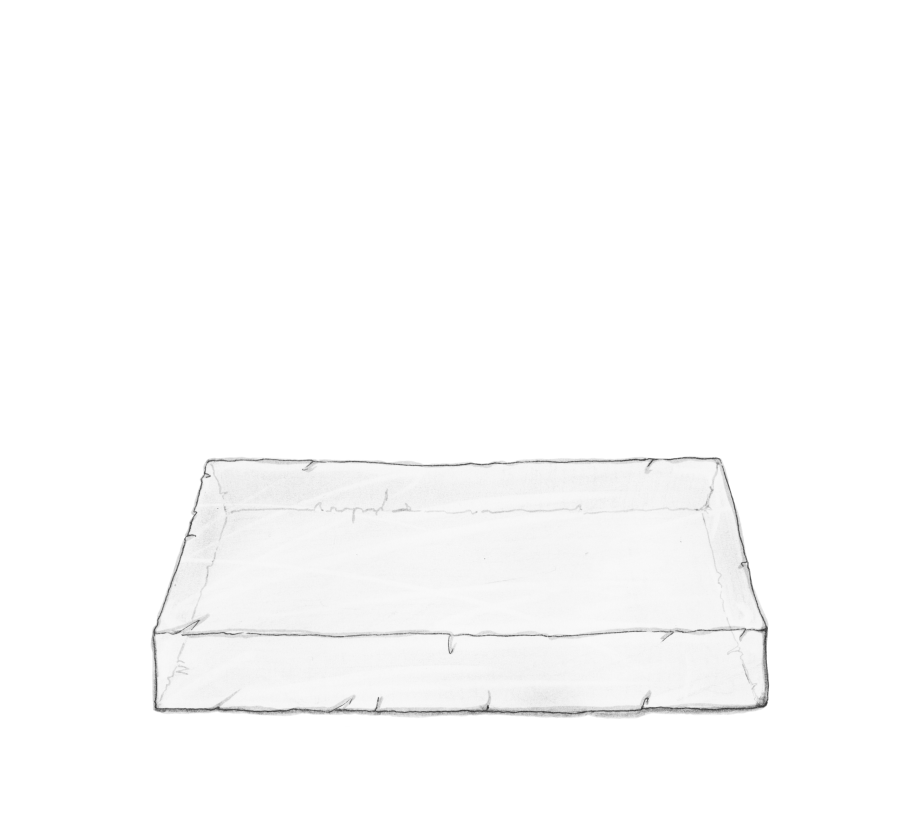第45話『 まもる、アウト オブ まもる02 』
「ハルノキくん、これおいしいよ!」
「まもるさん、それ何杯目ですか…というか、朝ご飯さっき食べたんですよね?」
さっきまで“教室”で寝ていたまもるさんは、予想以上に回復していて、ベッドの上からのんきに『TA-GO』の畑を眺めていた。
心配して損した気分になりながら、食堂へ行くことをつげると「ボクも!」とついて来て、こうして2度目の朝食をとっている。
昨夜の不調がウソのような食べっぷりだ。
「何杯目か、わかんないけどおいしいよ!」
これほど、山盛りご飯が似合う人はいないかもしれない。満面の笑みで米をかきこんでいく。
「なにをおかずにご飯たべてるんですか?」
「ぶへぇ?」
「おかず、もうないじゃないですか」
「だってお米がおいしいんだもん! おかわり!」
まもるさんは大きな電子ジャーのおかれた配膳台へ歩いて行く。
「食べ過ぎですよ」
そして、またご飯を山盛りにした茶碗を持って戻ってくる。この光景、何度目だろう。
「いくら食べてもお腹がすくんだよねぇ」
「今朝みたときよりも太ってません? さすがに運動した方がいいんじゃないでしょうか?」
「う、運動? 運動しよう? うーん、どうしよう。なんて」
頬をパンパンに膨らませたまもるさんのしたり顔に、暴力的な感情が芽生える。
「だって、そのお腹、どう考えてもおかしいですよ。なんか入ってるんじゃないですか?」
体育の授業でバスケットボールを詰めこんでいたクラスメイトの姿を彷彿とさせた。
「そうなんだよ! このお腹のお肉がすぽーんって取れないかなぁ」
まもるさんは、茶碗に盛られた米のようにせりだした腹を撫でた。
「とにかく、体育館いってみませんか? 自分、ダンスの師匠みつけたんですよ」
「ダンス!? ハルノキくん踊れるの?」
「当たり前じゃないですか! VRディスコでいっつも踊ってましたし、忘れてるかもしれませんけど、棚田さんの店のダンスコンテストで優勝しないと“クミコ”手に入れられないんですから、立派な親方についてちゃんと稽古つけてもらわないと」
「ぼ、ボクはいいよぉTA-GOやりたいし」
「だって、まもるさん、お金ないですよね?」
「ちょっとだけお小遣いもらったんだ」
「誰にですか?」
「国立先生! 頼んだらアルバイト代、少しだしてくれたよ!」
「なに前借りしてんすか? いや、マジで」
「だ、だって、ボクもTA-GOやってみたいんだもん……」
お年玉をそのままゲームに課金する小学生と変わらない。
「ダメです。とにかく体育館にいきましょう。TA-GOは禁止です」
「そ、そんなぁ」
校舎1階の東側の突き当たりの渡り廊下が体育館へ続いていた。重そうな鉄扉をそっと開けて中を覗き込むと、中央に人が集まっている。
ナツメさんと同じようなきわどいレオタードを身にまとった、お姉さんの集団。
色とりどりに咲いた花を眺めるような、胸が躍る光景だ。
「お! 来た! オイ! ハルノキ!」
目ざとくこちらに気づき集団の真ん中でナツメさんが手招きをした。
「はやく来いよ! 走れ!」
「は、はい!」
輪の中央に君臨するナツメさんは、深紅の花弁を広げるラフレシアのようにみえた。
……そういえば、まもるさんの気配がない。
しまった。
振り返ると、扉の隙間から、逆方向に小走りで去って行くまもるさんの背中が見えた。
「ま、まもるさ……」
「おい! はやくしろよ!」
追いかけることは許されなかった、いまはナツメさんの元へ走る以外の選択肢はない……。
「みんな、今日はこいつもレッスンに参加するからよろしくねー」
ナツメさんはがしがしと肩を叩きながら紹介してくれた。
「おい、自己紹介」
「じ、自分、桜とかきましてハルノキっす! お、親方に従事してりっぱなダンスを」
「おい、待てハルノキ。親方ってなんだ?」
床に座るお姉さん方がニコニコしている。
「い、いや、あのつ、つい……」
「だからアタシは力士じゃねえつってんだろ? 舐めてんのか?」
「も、申し訳ございません! な、なにとぞ稽…いや、レッスンを! ごっつぁんです!」
「フゥ……まあいいや、とりあえず着替えてこい。その格好じゃムリだろ」
「はい!」
背中に失笑のような空気を感じたのは気のせいだと信じたい。
「で、アンタなんか踊れんの?」
着替えを終えて戻ったが、お姉さん達は円座の隊形を崩していなかった。
「じ、自分、クラシックでオールドスクールなステップなら」
輪の中央で立たされていた。
あぐらをかいたナツメさんは小さく頷く。
「ほぅ、やってみなよ。音持ってる? あのスピーカーと
ナツメさんは親指を突き立て、背後にそびえるエアロスピーカーを指さした。
「ありがとうございます!」
視野内のページを右へ送り、imaGeの“通信”を呼び出してペアリング先を探す……
『DOS-KOI-summer EYE』
この空間内にある
「こ、この、ド、ス、コイサマーっていうヤツですか?」
「そうだけど。なんか文句あんの?」
「い、いえ……」
ナツメさんも少し、相撲に寄せているじゃないかと思ったが口に出すのはやめた。
「ほら、さっさとしろよ、みんな家事とかいろいろあって忙しいんだから」
「ハルノキくーん、あたし子供お迎えがあるから、なるはやでね」
ナツメさんの隣にすわった、細身のお姉さんがおしとやかに囃し立てる。
「そうだよ、リッちゃん“ケツ”あんだから、もっと“マケ”よオラ!」
リっちゃんさんの胸元も大きく盛り上がっている。目鼻立ちが整ったお姉さんの“盛り上がり”は見ていて非常に得した気分になる。
「ハルノキ! どこ見てんだ。ペアリングできたのかよ?」
「は、はい! できました、再生します」
大勢の視線を感じる。
こ、こんなにキレイなお姉さん達の前で、果たして踊れるのか? いままで、独りでひっそりと踊ってきた自分が人前で……。
頬が熱い。
ダメだ。迷うんじゃない!
視野内の再生ボタンを右目でタップした。
♪デー デ デ デン♪
いまだ! ジャンプ!
両足を大股に開いて跳ぶ。
ジャストタイミングで音にノれた!
着地。
大股を開いたまま、カニ歩き、カニ歩き。
よし、いいぞ!
♪デー デ デ デン♪
もう1回、ジャンプ!
着地!
決めのポイント。
指を突き上げて
よし!
もう1回!
♪デー デ デ ──
「あ、あれ?」
突然、ギュゥゥーン……とブレーキをかけたように音が萎んでいった。
着地した体勢で、急激に現実に引き戻された。
静まりかえった体育館。
もしカボチャの馬車が走り出した直後に、魔法が解けたとしたら、シンデレラはこんな気持──
「アンタ、舐めてんの?」
ナツメさんに胸ぐらを掴まれた。
そのまま高く、釣り上げられる。
こ、これは、ネ、ネックハンギングツリー。
「いまのなんだよ?」
ドスのきいた声だった。
「い、いや、往年の有名なステップを再現しようと……」
く、苦しい。
「
床に落とされた。咳がとまらない。
「動きが全然ダメ。それに、振りが違う」
「ち、違うんすか?」
「どうせどっかの動画みて思い込みだけで踊ってんだろ? あの曲は、冒頭からいきなりカニ歩きしないんだよ。そういう、アーティストのヒット曲だけ集めたプレイリストみてぇに薄っぺらいところが気に入らねえ」
「す、すみません……」
「アタシが踊ってやるから、ちょっとみてな」
ナツメさんが指を鳴らすと、その場にいた全員が立ち上がった。
ナツメさんを前列におき、他のメンバーは後列へ並ぶ。立ち位置に迷いはなく、たちまち
全員の立ち姿が美しかった。
「み、みなさん。ご、存知なんですか? あの曲を」
「舐めんじゃないよ。ここにいるみんな、過去100年分くらいの振りやステップは心と体に染みこんでんだよ」
ナツメさんが右手の人差し指をたてた。
「いくよ」
♪デー デ デ デン♪
全員が跳ぶ。
高さはビシっと揃っている。
左右の踵は交互に内側と外側を行き来する。
センターのナツメさんは、歯をむきだし強烈な笑顔で指さしてきた。
♪デー デ デ デン♪
大地を踏みしめるように力強く、
左右にステップを踏む後列のお姉さん。
みんな胸が揺れている。
いやらしさは感じない。
ただ、ひたすら、カッコイイ。
♪デー デ デ デン♪
クールにフレーズが繰り返される。
研ぎ澄まされたカミソリのように鋭く
幾本の手足がまるでひとつのように
淀みなく動く
グルーブは頂点へと向かい
突如──
やってくる変調。
ナツメさんが跳ぶ。
軽やかに着地して
カニ歩き、カニ歩き
ターンしてまた跳ぶ!
カニ歩き、カニ歩き
そのステップは複雑に刻まれる
「ストップ! summer time!」
ナツメさんが手の平を掲げ曲を止めた。
全員がピタッと動きを止めた。
ただそれだけなのに、鳥肌がたった。
「どうだ、ハルノキ」
ナツメさんが笑顔から仏頂面に戻った。
何度も、何度も観た映像のハズだった。
でも、リアルな空間でダンスを観ることは、これほどまでに心を動かされるものなのか。
「じ、自分に、稽古を、お願いします」
「じゃあ、ステージに上がりな」
ナツメさんは体育館の奥を顎でしゃくった。
「え、す、ステージ、すか? じ、自分、体育館のステージは、ちょっと苦手でして」
「ぁん? ダンサーはステージとリズムにノるのが仕事なんだよ、さっさといけ!」
ステージのうえに立つと急に腹が痛くなってきた。腸から胃にかけて何かが逆流してくるような痛み。マズイ。これはおそらく、小中高どこかの時代の発表会やら合唱コンクールやら、表彰式やら委員会やらの強烈なトラウマ……。
目の前まで移動してくれたお姉さん方の顔がみえる。この微妙な距離感もまた苦痛だ。
「ハルノキ! いくぞ!」
しかし、ナツメさんに容赦はない。
♪デー デ デ デン♪
「手と足が逆だ!」
指示にも容赦がない。
♪デー デ デ デン♪
「突き上げる指1本にも神経集中しろ!」
ゆ、指?
♪デー デ デ デン♪
「肘の角度!」
ひ、肘?
♪デー デ デ デン♪
「まともなターンなんかできるわけねーんだから、せめて、転ばねえように踏ん張れや!」
♪デー デ デ デン♪
「ラフな動きは適当に動いてるわけじゃねえんだよ! ラフに見えるように気合いいれてうごくんだよ!」
♪デー デ デ デン♪
「おら! 動け! ハルノキ! チッ、もうギブアップかよ……リッチャン、バケツに水くんできてくれない?」
顔面に衝撃的に冷たい水を浴びて目が覚めた。
「ハルノキ! 立てぇ!」
「お、親方……じ、自分どうして……」
「だから親方じゃねえつってんだろ! オマエ、途中で倒れたんだよ」
確かに、曲の途中から記憶がない。
「オマエ、ぜんっぜんダメだな。体全体に意識がいってねえんだよ。頭のてっぺんからつま先、肩から肘、指先まですべてが表現なんだよ」
「そ、そんなにダメっすかね。これでもVRディスコでは……」
「それならおもしれえもん観せてやるよ。ハマちゃーんOHPの電源入れてきてくれる?」
ハマちゃんと呼ばれたのは、青いレオタードを着たお姉さんだった。引き締まったウエストをくねらせてステージの袖に歩いていく。
「OHPって、
「は? なにそれ?」
「こ、この体育館の記録映像ですよね?」
「そうだけど。OHPはOHPだろ?」
「正式名称はオーバーレイホールプロジェクターといいまして、空間備え付けの立体記録映像を録画、管理、投影する……」
「あ、そういう正式名称とかいいから」
「ハルノキくんスゴイねそういう難しいことは知ってるんだね」
リッチャンさんに褒められた。
「でも、踊れねえけどな」
ナツメさんには鼻で
「ナツメちゃーん、電源いれたよー」
ステージの袖のほうから、ハマちゃんさんの声が聞こえた。
「んーと、3年のときのヤツどこだっけ」
imaGe視野内を探しているのか、ナツメさんの目が左右に動く。
「あ! コンテストのやつ?」
「うわ懐かしい」
「あれ、旦那がダセーんだよなぁ」
なにかのイベント映像だろうか?
「あった。ハルノキ観てろよ」
体育館の天井に巨大な再生アイコンが浮かぶ。
ステージの下に大勢の人が
ステージには10人くらいの男女が映しだされている。
「え、これ!?」
「高校時代のアタシたちだよ」
「ハルノキくんの真後ろにいるのがわたしの旦那だよ」
リッチャンさんがイタズラっぽくいう。
振り返ると、日焼けした筋肉質な男子生徒の顔があった。絡まれているような気分になる。
「卒業ダンスコンテストの映像だよ」
確かに陣形をとる制服姿の顔ぶれの中にはリッチャンさんやハマちゃんさん、他の全メンバーがいる。
「み、みなさん、わ、若いっすね」
面影はあるが、みんな表情があどけない。
自分が立っているのは、ちょうどセンターの位置だった。
真横には切れ長で黒髪の美少女がいた。
横顔は挑発的に観客の方を睨んでいる。
「こ、この子、めちゃくちゃ美人ですね」
「アタシだよ」
ナツメさんが自分を指さしていた。
「え、え、ナツメさん……このころメチャクチャ痩せて……」
突然曲が始まった。
トゥーンという突き抜けるような高音が体育館中に響く。
映像のナツメさんの右手がいきなり顔面に迫ってきて、思わずのけぞって尻餅をついてしまった。当時のナツメさんに殴られたような気分。
「オマエ、なに下から覗こうとしてんだよ」
否定しようとしたが、激しくステップを踏む当時のナツメさんの脚に視線を吸い寄せられた。
ス、スカートがきわどいところまでめくれる。
「アタシそのころノーパンで踊ってたからな」
「ま、マジすか?」
「ウソだよバカ」
本当にノ、ノーパンなら、殴られてもいいから覗いてみたいと少しだけ思った。
「ハルノキ、おまえ本気で覗こうとしてんだろ?」
「い、いやそんな」
現在のナツメさんの姿で現実を取り戻す。
「きめーな、大学みてーだわ」
「国立さんも踊ってるんですか?」
なぜか全員が笑った。
「みてみろよ」
ナツメさんがステージの真下に親指を向けた。
観客席の先頭には長机を並べた席がある。
中央に座っているのは、く、国立さん?
「あいつ生徒会長だったからな。そこで審査員してたんだよ」
キッチリと学生服の襟を絞め、まっすぐに壇上を見上げている。
視線はまるでスナイパーのように、ぶれることなく真っ直ぐステージへと向けられていた。
「いつみてもこの顔ウケるんだよね」
「絶対、ナツメちゃんのパンツみようとしてるよねーこの角度」
ハマちゃんさんが、国立さんの映像が座る場所からステージを見上げていた。
「しかも、足元でリズムとりながら」
言われてみれば確かに、長机の下で小刻みにつま先を動かしていた。
「まぁ、全然テンポあってねえんだけどな」
ナツメさんの厳しい分析。
「あ、あのナツメさん、自分はどうしてこの映像をみせられているのでしょうか……」
「ああ、そうそう。この映像さ、コンテストが終わったあとさ……」
ナツメさんが指先を振る。なにか、シーンを先送りしているようだった。
体育館全体の映像達が人間離れした速度で動き出していた。
「あった、ここだ」
ナツメさんが指の動きを止める。
どうやら、コンテストが終了したあとの映像のようだ。壇上で男子学生がひとり残っていた。
「く、国立さん!?」
「えっ! なにこれ!? 初めてみた」
リッチャンさんが国立さんの映像に反応した。
「アタシもこの間偶然見つけたの。録画の消し忘れだったみたいでさ、で、大学が……」
国立さんは体育館の後方を眺めるようにじっとステージ上で仁王立ちしていた。
そして、つま先をトントントンと動かし、お、踊りだした。
……いや……踊っているのか?
なんというか、すべての動きがバラバラで、だらしがないタコのようだ。
最後は飛び上がり猫背のまま指を突き出す。
「ギャハハハ、ナツメちゃん、なにこれ? やばくね?」
「やばいっしょ? やばいっしょ?」
お姉さん方も笑いは容赦がない。
「アイツ、なんで放課後に残って踊ろうと思ったんだろうな!」
「OHPの録画、切っとけっつーの」
「ヤバイ、お腹いたい!!」
周囲の爆笑につられ、発見者であるはずのナツメさんもむせ込むほど笑い、腹を抱えている。
「
「いつだったかさ、教室でノートにポエム書いてたの見つけてノート取りあげたときだっけ? あのときだけは、もの凄い早さで追っかけてきたけどね」
「ああ、腹イテぇ、ハルノキ、おまえこれくらいヒデーからな。もう少し本気で練習しろよな」
「え、な……なんですって!?」
待って欲しい。自分のダンスがこれほどの、いや、国立さんには失礼だけど、ここまで酷いというのか? そんなはずはない。
「なんですって? じゃねえよ! まずは現状をしっかりうけとめろ! よしもう1回いくぞ」
渡り廊下は、こんなに長かったのだろうか。
「イデッ!」
油断してスノコから踏み外した。
足が、いままで感じたことのない重さと痛みを発しうまく歩くことができない。
少しでも姿勢をかえようとすると、腹、背中、首、肩、腕、全方位の筋肉が全力で痛みを訴えてくる。
「な、なんだ、これ……」
子供のお迎えや夕飯の支度、各自が家事のために帰宅するまでレッスンは続いた。
地獄のような時間だった。
壁を伝ってそろり、そろりと歩く。
教室が1階だったことに心から感謝した。とても階段を使うことなんでできる状態ではない。
最後の力を振り絞って扉を開けた。
「あ! ハルノキくん! お帰り!」
まもるさんは、ベッドのうえからまだ畑を眺めていた。
教室の通路にスマートフォン置かれ、TA−GOの畑を埋めつくすほどびっしりと茂った葉っぱを
まて……。
葉っぱ?
「ま、まもるさん、もしかして相当、お金つかってませんか?」
「ん? なんでぇ?」
みえみえにシラをきる表情、一瞬だけ全身の痛みを忘れた。
「TA−GO、今朝まで更地でしたよね」
種を植えるだけでも金がかかる。いやそれよりもなによりも、TA−GOの時間は現実の時間とまったく同じ。
こんな短時間で植物が生長するはずはない。
ということは……
「ハルノキくん、みてよ!」
まもるさんは、ベッドから降りて、畑の隅に置いてある木箱を開け中から大きな懐中電灯のようなモノを取り出した。
「ジャジャジャジャーン! せーちょーそくしんライトぉ!」
やっぱり……。
丸々としたまもるさんの手が掴んでいるのは、TA−GOの有料オプション“生長促進ライト”。
「まもるさん、マジでいくら前借りしたんですか?」
「大丈夫だよ! これで明日の朝にはちゃんと実がなるっていってたから!」
「そんな話じゃないんですよ! これからの旅どうするんですか!」
「ちゃんと、旅先に届けてくれるって! しかも格安っていってたよ!」
「しっかり、取るんじゃないですか! セイジのヤツ絶対にぼったくりますよ! 送料。どーすんですか、俺、イナサクさんが運んできたら断れないっすよ!」
疲れているせいだろうか、この男が許せない。
「セイジに連絡してください」
「んーつながらないかもよ、もうすぐスキャンの時間だと思うから」
時計をみると、『PM 5:30』を示していた。6時間近く、踊り続けていたことになる。
「ダメっす、自分、もう寝ます」
「え! ご飯食べないの?」
「いりません」
もう面倒だ。ひとりで九州にいってやろう。自分のベッドに潜り込んで目を閉じると、瞬く間に強烈な睡魔が襲って──
「ウグッ……」
なにか聞こえた。
意識が戻った。
「え、いま、何時?」
教室は真っ暗だった。消灯時間はとっくに過ぎているようだ。
「ウグググ」
また、聞こえた。
隣のベッドからだ。
……まもるさん!?
「グググ、ウグググ、イデ、いだぃ…」
呻く声は次第にはっきりと聞き取れるようになっていた。
「ま、まもるさん?!」
飛び起きてカーテンをあける。
まもるさんが、お腹を押さえてもがいていた。
「いだい、は、ハルノギぐん、いだぃよ、お腹、いだいいいいいい」
「ちょ、ちょっちょちょ、ま、まもるさん?」
「うぐぐぐぐ」
「い、いま国立さんよんできますから!」
教室の扉に向かって走ろうとしたとき、国立さんと南先生が揃って駆け込んできた。
「来たみたいですね」
首に聴診器をかけながら国立さんがベッドへ駆け寄り、まもるさんの腹に聴診器をあてた。
「あ、これは……南先生はちょっと離れてて、桜さん、手伝って」
せわしない手招きで呼ばれる。
「今回は下からみたいだから!」
「下からって……」
質問を言い終えるまえに国立さんが、まもるさんのガウンの帯を解く。
あっという、間もなく、暗闇の中で
まもるさんの下半身があらわになった──
次回 04月13日掲載予定
『 まもる、アウト オブ まもる 03 』へつづく
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする