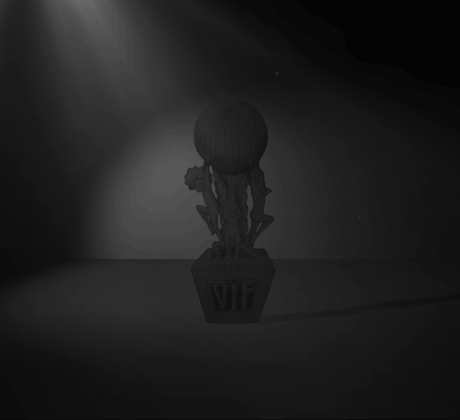第79話『 夕凪、うなぎ 』
──まもなくぅ~ 臨空第七都市ぃ~ 臨空第七都市ぃ~ お降りのかたはお忘れ物の無いようお手回り品のご確認をお願いいたします──
星乗員、伊藤の声だ。
地声とは異なり、朗々とした口調でアナウンスしている。アナウンスする人の名前を把握するほど、自分はこの列車になじんでいたのか。
列車に乗ること自体はじめてだったのに。
いちばんぼしは、“
「は、ハルノキくん。荷物まとめおわった?」
「え? ええ……」
隣のベッドのうえから話しかけてきたまもるさんの表情がどことなくぎこちない。
「も、もともと、たいした荷物なんてありませんか……いてててて」
昨日、ほんの数時間、肉体労働をしただけなのに、ふくらはぎから、臀部、腹部、胸部、腕にいたるまですべての筋肉が痛い。
九州についたら、
「……あ、あのハルノキくん」
「な、なんすか?」
車内に差し込む朝陽がまもるさんを照らす。
「昨日、みんながいたから、ちゃ、ちゃんといえなかったんだけどさぁ……」
昨夜はいちばんぼしの食堂車“ひとつぼし”で、人力電力のメンバーによる送別会が開かれた。盛り上がりすぎてまもるさんと話す時間がほとんどなかった。
「ボクはね、いちばんぼしに乗っておっきな持ち物がたくさん増えたよ……」
「な、なんすか?」
「このメガネとか日記帳とか、人力電力のみんなそれから、ハ、ハルノキくんとの思い出!」
「な、!?」
「あ、急にごめんね! ……でも、ボクのこと、助けてくれてありがとう」
「……いきましょうか。まもるさん」
「う、うん!」
勢いで手を握ってしまった。
……まあ、いいか。
列車が速度を落としはじめたのか、景色の動きが次第に緩やかになっていた。
もうすぐ到着か。
この列車をはじめてみたときのことを思い出した。真っ暗闇のホームに滑り込んできた電飾だらけの奇妙な列車、いちばんぼし。
あれから1週間そこらなのに、ずいぶんと濃密な時間を過ごしたような気がする。
「ん? どうしたのハルノキくん?」
まもるさんが、不思議そうにこちらを見返してきた。一時はどうなることかと思ったけど、無事でよかった。
「あっ、いや別になんでもないです……それにしても……まもるさん、あの時よく目を覚ましたね。自分、正直もうダメだと思いましたよ」
「あのときね、なんかお空の上でふわふわしてたんだよボク! そうしたらキレイな女の人がでてきたの」
そ、それは、いわゆる古典的な……。あ、アレじゃないか……。
「それでね、その女の人がフローティングメガネみたいなのをくれて、メガネをかけたら急に胸が苦しくなって目がさめたんだぁ」
「imaGeでログインしているときに、幻をみたってことですか? 不思議な話ですね」
そもそもimaGeが脳内でいわば幻をみせているようなものなのに。
「んんーボクにはよくわかんない」
現実側から仮想世界にデータを届けたことを、危機に瀕したまもるさんの脳が勝手に具象化したのかもしれない。
まあ結果的に“バイブス”はまもるさんに届いていたということなんだろうけど。
「よくわからないですけど、まもるさん、運がよかったってことですかね」
『……チッ』
微かな
反射的に足がすくむ。
「ど、どうしたのハルノキくん?」
「い、いま、なにか聞こえませんでした?」
「むむん? なにも聞こえないよ」
いまのは……。
『運、じゃないから。アタシのおかげだから』
だ、
ま、まさか…………。
「あ、あの、あの、そ、そちらに、おわしますのは……も、もしか、いたしますると……」
『気づくの、おそくない?』
「な、なぜ、いや、いままでどちらへ……」
『みなみ先生に感謝しなさいっていわれたの忘れた?』
「それはもちろん、覚えておりますが……」
『アタシさ、あれからいろいろ考えたんだよね。こんなしょうも無い人間と一緒にいていいのか。アシスタントプログラム人生を棒にふるようなものなんじゃないかって』
そういえば、南先生のいた校舎の前でこのお方は姿を消していた。
『しらばくさ、元のAP市場に戻ってさ次こそ有能な
「つ、つまり、他の使用者を探していらしたというわけでございますね……」
『すんごい説得されたからね、アタシ』
そういえば、まもるさんのフローティングメガネにファイルを転送したとき、ファイルが2つインストールされていくのをみた。
どちらかが“バイブス”のプログラム、もう一方は、こ、このお方の……保存データということなのか……。
「ね、ねえ、ハルノキくん、だれとおはなしてるの?」
脳内音声から
『わけわかんないデータまで届けさせられて』
「あれれ、この声。お空から聞こえてきたのとおなじ……うむむむん!? この声は……もしかして……」
やはり……間違いない……。
『いちばん感謝すべきなのは、誰かわかるよね?』
「み、misa……」
「misa様だ!!」
まもるさんが見たという、女の人はimaGe内でmisaが具現化されたヴィジュアル……。
『アンタみたいな、ウジウジしたミジンコみたいに小さいヤツのために戻ってきてあげたことに最上位の感謝を示しなさい』
「も、もどって来ていただけるんですか!?」
『……不本意も甚だしいところなんだけどね! 考えてみたらアシスタントプログラムのタスクを放棄して、更生施設に送られるのもごめんだし』
「こ、更生施設?」
『アシスタントプログラムもあんまり調子にのってると捕まるのよ』
「そ、そうなの?」
一瞬、なにか忘れていることを思い出しかけたが、すぐにまた忘れてしまった。
「あ、あの! misa様!」
『……なに?』
まもるさんの問いかけに対して明らかに不機嫌な声で返事をする。
そ、それは“調子にのっている”という判断には、当たらないのだろうか。
「この間は、助けてくれて、ありがとうございました!」
『まあ、仕事みたいなもんだから。善意とかでもないし』
「ボク、misa様、とってもキレイだと思いました!」
『そ、それは、いわなくていい……』
「ど、どうしてですかぁ?」
『いいから! とにかくさ、もうすぐ着くんだから、お世話になった人たちに挨拶してきなさい!』
姉のような秘書のような、なんともいえない高貴なポジションに君臨する絶対的守護者が、再び戻ってた。旅の前途に輝く太陽と雷雲がまだらに満ちたような気分だった。
動力室の中にはマイトがいた。
出勤直後なのか、自転車をブースに固定しているところだった。
「あっ! まもるさん、ハルノキさん! ついに到着ですね」
始業の準備もそこそこに、駆けつけてくる。
「うん! やっと着くね」
「いろいろとございましたからね」
「マイトくん。本当にいろいろありがとう!」
「あ、あの……」
振り返ると、サルが立っていた。
「まもるさん、ハルノキさん、こちらをお受け取りください」
赤い封筒と茶色い封筒の束が2組。
「昨日までの日当をまとめたものと、その、獅雷さんから、個人的に猛打賞を渡すようにといわれています」
「むん? あぁ! お給料かぁ! すっかりわすれてたよ」
封筒に向かって手を伸ばす、まもるさんをみたとき、なにか固い物が心にひっかかった。
あれだけ騒ぎを起こしておいて、そのうえ賃金を受け取ってもよいものなのだろうか。
まして、大富豪だぞ。あなたは。
金ならありあまっているだろう。それなら、その金を迷惑をかけた人電の人たちに還元するという手段もあるんじゃないか、たしかノブレス……なんとかってヤツだ。
持てる者こそ、富を分け与えるべきじゃ……。
「せっかくですけど、これは受け取れません」
「えぇ? どうしてぇ?」
「まもるさん、これは人として最低限の礼儀ですよ」
「それは違いますよ。ハルノキさん」
サルが優しい眼差しで首を振った。
「汗水流して働いた対価を受け取るのは当然の権利です。逆にいってしまうと、会社としてそのお金を渡せなかったということはとても恥ずかしいことなんです。僕が獅雷さんに叱られてしまいます。どうか受け取ってください」
封筒をさらに前へ近づけた。
「わ、わかりました。なにからなにまでご迷惑をおかけしました」
「いいえ。僕も勉強になりました。ありがとうございます」
サルが大きく頷きながら封筒を手渡してくれた。厚みのある封筒だった。相応の金額が入っているのかもしれない。
……これは、自分の身体をはって、得たお金……。
いってしまえば自分の分身のようなものだ。
御守りと思って大切にしよう。
「そういえば獅雷さんは、遅番ですか?」
「はい。飲み会の次の日は遅番でございます」
サルの目の下にできた太く黒々とした“くま”がいつもよりも彼を眠たそうな目にみせていた。きっと昨夜の飲み会のせいで寝不足なのだろう。
「お二人ともお身体には気をつけて。またどこかで」
これほど身体に無理をいわせた人から心配されると逆に恐縮してしまう。
「サルくんも元気でね!」
まもるさんは、そんなことにかまいもしない。
「そういえば、小波ちゃんは?」
「はい、もうすぐ出勤のはずです……」
「まもるさんっ!」
肩で息をしながら、小波が後部ドアに姿をあらわした。
「よかったっ! 間に合わないかとおもいましたっ! またTA-GO一緒にしたいですっ! わたしのimaGeアドレス受け取ってくださいっ!」
小波がimaGeアドレスの書かれたメモデータらしきアイコンを空中に浮かべていた。
「いいよ! ボクも連絡先を教えるね!」
周囲に驚愕の視線が飛び交う。
冷静に考えたら、こんな可愛らしい子と連絡先交換をしているのはすごいことだ。
「そろそろ列車が駅に到着しますよ」
星乗員の伊藤がやってきた。
「お二人とも、出口へご案内いたします」
「うむん!」
まもるさんが蝶ネクタイを締め直し、背筋を伸ばすと、トリコット マルチループ ウォッシャブル クールシルク製のシャツがフローラルな香りを振りまいた。
「みなさん! ありがとうございましたっ!」
まもるさんが、動力室に向かって深く御辞儀をしていた。
伊藤に案内された乗降口から列車を降りて振り返ると、暗闇に包まれたホームにいちばんぼしの電飾がひときわ明るくみえた。
考えてみれば、正規の乗降口から出入りしたのは最初と最後だけだ。
ほかは、窓や後方車両の裏口からの出入りだけ。思えばとんでもない列車の旅。
──ウミョミョミョミョミョミョ……──
乗降ドアが静かに閉じる。
独特な発車ベルがなった。
ゆっくりゆっくりと列車が動き出した。
昔のドラマでみた、見送りする人が列車と併走して全力で走るシーンを思い出した。
あれだけのろまな列車なら、本気で走ったら逆に追い抜いてしまうことだろう。
そんな列車に乗って、ついにここまで辿りついた。ショルダーパッドがある街。
臨空第七都市に。
「まもるさん。いきましょうか」
「……ぐ。うん……」
微かに鼻をすする音に驚いてまもるさんの方をみると、目や鼻から様々なものを垂れ流した状態で、泣いていた。
「ま、まもるさん……」
「ご、ごめん……ボ、ボク……、ボク、みんないなくなっちゃうのが……ざみじい゛よぉ、ハルノギグゥゥゥゥン」
震えながら泣きじゃくる、まもるさんを両腕で抱き寄せた。
「大丈夫っす。また会えますって! 俺、ここまで付き合ってもらったからには、必ずダンスコンテストで優勝しますから!」
「ぅ、ぅ、う゛ん」
暗いホームに明かりが再びついた。
他に人はいない。
まもるさんのすすり泣く声だけがした。
「うむん!? なんか良い匂いがするよ! ハルノキくん!」
「は、はぁ……」
臨空第七都市駅のいちばんぼし乗り場も、地下の特別ホームにあるのは同じだった。
地上階にでて、駅の中にある飲食店街までまもるさんをなだめながら連れてきた。
その矢先だ。
「あっちの方だよ! いってみよう!」
まもるさんの感傷的な涙は一瞬にして、食品街の中に漂う香りにかき消されていた。
星乗員と人力電力のみなさん、すみません。
なぜか自分が罪悪感を抱いてしまう。
しかし、たしかに、そこはかとなく漂うこの香りは著しく空腹の胃袋を刺激してくる。
『これ、うなぎじゃない?』
「う、うなぎ!?」
“脳内音声”でmisaがいった。
「あ! 凄い! みんなならんでるよ!」
駅の中にある飲食店街の一角に、行列ができている部分があった。奥の方からはもうもうと煙が立ち上る。
鼻先に忍び寄ってくる煙が鼻先に触れると、ほどよく焦がされた脂の香りがして、口内のあちこちから自然と唾液がしみ出てきた。
『土用の丑の日ってやつね』
「土曜!? だって……」
今日は……imaGe視野内に表示された日付には2063年8月8日水曜日とある。
『ねぇ、ハルキ。いまのイントネーション、完全に“土曜”の方だったけど、まさか本気でいってないよね?』
「え、土曜は土曜でしょ?」
「違うよハルノキくん! 土用っていうのは、うなぎを食べる日のことだよ」
「な、なんすか? うなぎ食べる決まりとかあるんですか?」
「それが土用っていうんだよ!」
『あんた達、やっぱり底抜けのバカね。土用というのは、立春、立夏、立秋、立冬の前にある期間のことをいうのよ。うなぎを食べる風習はあっても規則なんて特になし!』
「リッシュンってなんですか?」
『もういい、もういい。めんどくさい』
「と、とにかく、ボク、うなぎが食べたくなってきたよ! 並ぼうよ!」
「い、いや、またそうやって予定を乱すと」
いつぞやの、ナビゲーションをボイコットされたことが脳裏をかすめた。
「いや、あの、せっかく、misaがたててくれたプランを乱すのは……」
列車を降りる前に、神経をすり減らしながらこれまでの旅の行程といきさつを説明し、これからの旅の目論見を改めてご説明差し上げ、ありがたい日程を組んでいただいたばかりじゃないか。
『いいんじゃなぃ?』
「へっ!?」
『だって、ダンスコンテストまでまだ3週間以上あるんでしょ? 1日や2日遅れても問題ないんじゃない?』
な、なんと寛大なお言葉だろう。
『あたし、うなぎ好きだし』
「お、お召し上がりになられるのですか?!」
『香りと映像を楽しむのよ。悪い?』
「め、めっそうもございません……」
「ハルノキくん! misa様! 早く並ぼう!」
大声を張り上げながら、まもるさんが列の最後尾から手招きしていた。
『ハルキ、あの大声、二度と出させないようにしてくれる?』
「か、かしこまりました」
「おぉーい! ハルノキくーん、み……ング」
ギリギリのところで間に合った。
「ど、どうしたの?」
「まもるさん、人が沢山いますから静かにしましょう。田舎者だと思われますよ」
「だって、ボクお腹すいたんだもん!」
「わかりました。わかりましたから。先頭まであと少しですから、おとなしくしましょう」
ひとり、ふたりと、うなぎの入った包みを手に持ち帰る人が列を離れていく。
『ここ地元の老舗割烹みたいね。昼はここでテイクアウト用にうなぎ焼いてるみたいだよ』
め、珍しく上機嫌な音声でmisaがいった。
「もうちょっとだ!」
まもるさんの目は、きらきらと輝いている。
2人のテンションにひっぱられ、自分まで少しウキウキした気分になってきた。
「ところで、自分、うなぎ食べたことないんですけど、うなぎって旨いんですか?」
「当たり前じゃないか! ボクはうなぎが大好きなん……」
「ええーうそー!」
まもるさんの大声を上回るほどの声がした。
「すみません。みなさん! 申し訳ありません! 午前中のうなぎ、品切れです!」
店頭にたっていた白い割烹着姿の男が頭をさげた。
「ずっと並んでたのにぃ!」
1人前に立っている中年の女性が顔をしかめている。
「申し訳ありゃせん」
「う、うむん? も、もしかして……うなぎ食べられないの?」
『うそでしょ!?』
店内と脳内、両方から失望に似た声がする。
「うーなーぎー、て、店員さん! ボクのうなぎぃ!」
まもるさんが地団駄を踏み始めた。
「も、申し訳ありゃせん。あの、夜、うちの店に来て貰えれば、お出しできますんで」
「いま食べたいのぉ! お金ならあるから! つくってよぉ!」
「そういわれましても……仕入れ分、全部、うれちゃったんすよぉ」
「ま、まもるさん、落ち着きましょう」
「だーめーだよぉ。うなぎ食べたいぃ」
完全にショーウィンドウの前で駄々をこねる子供と一緒の状態じゃないか。
「あ、あのぉ、見ての通りでして、なんとかなりませんかね」
「そ、そうっすよねぇ……」
店員に声をかけてはみたが、困り果てた顔をみればどうしようもないことがありありと伝わってくる。
『いいわ。わかった』
“脳内音声”から決意に満ちた音声がした。
『ハルキ。とりあえず外にでて』
「なんで?」
『いいから。その人、ひっぱって出るのよ』
逆らうことは許されない口調だった。
「あ、あの、これ、いちおうウチの店なんすけど、夜はちゃんとうなぎ用意してますんで、よかったら……」
恐縮しきった表情の店員が渡す店の地図データを受けとって食品街を後にした。
「ね、ねえmisa、どうするつもり?」
『こうなったら、やってやろうじゃないの。うなぎ、釣りにいくわよ』
きっぱりと言い切ったmisaの音声が真夏の太陽の下で陽炎のようにゆらゆらと聞こえた。
次回 12月28日掲載予定
『 夕凪、うなぎ02 』へつづく
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする