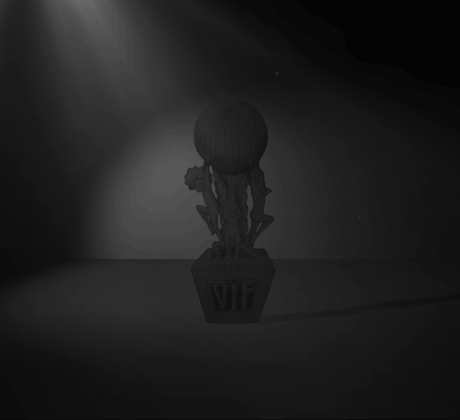第81話『 バディのボディ 』
日没──。
目の前を流れる緩やかな川が連なる大海のその向こうへ、太陽が静かに沈んでいく。
「ね、ねえmisa。もうすぐ日が暮れるよ」
『だから? ここからが勝負でしょ?』
あれからペットボトルは、ウンともスンともいわず、倒れる気配もなく夕陽の中で屹立した姿を保っている。
まわりに釣り人はみあたらず、唯一いた先客も堤防の先の方で帰り支度をはじめているのがみえた。
「これさ……、本当に釣れるの?」
『そうやってせかせかしてると釣れないのよ。まもるをみならって少しはドンと構えてみなさい』
まもるさんは堤防のへりに寝そべり、寝息をたてている。自分はこんなところで眠れるほど神経が太くデキていない。
「アンタらぁ、ちょっといいかい?」
頭上から声がした。
振り返って見上げるとそこには、釣り竿を担いだ男がたっていた。
さっき片付けしていた釣り人のようだ。
年季の入った麦わら帽子の下には陽に焼けたシワの目立つ顔が覗いている。
「は、はい?」
「あんたらさ、見かけねえ顔だね?」
優しそうなおじいさんだった。
「なに、狙ってんだい?」
「う、うなぎです」
「あぁそうか、そいつで釣ろうってのか?」
おじいさんがペットボトルを顎でしゃくった。
「そうなんですけど、全然釣れなくて」
「これからが時合だからなぁ」
「ジ、ジアイ?」
「ん? そうだよぉそろそろ魚が動き出す頃合いってことだぁ。イイ感じに釣れるんじゃねえのかぃ」
『ホラみなさい』
脳内でmisaが勝ち誇ったように呟く。
でも、地元の人が同じことをいってくれるのは、心強い。
「でも、おじいさんは帰るんですか?」
「ん? ああ、俺か? 俺わぁ、釣れなくても別に構わねえから。それに、そろそろ晩飯の時間だしなぁ。それじゃあ、頑張って釣ってくれ若い人」
「は、はぁ……」
「あ、そうだ。ところでよぉ……アンタら、ちゃんと“遊漁券”はもってんのかい?」
「なんすか? 遊漁券って」
『……ぁ……』
こんどは脳内で
嫌な予感がする。
「この川で魚釣る権利なんだけども……。なんだぁ? 持ってないの?」
「も、持ってません……」
「ありゃりゃりゃりゃ!」
おじいさんが大げさに顔をしかめた。
「そりゃだめだよぉ。捕まっちゃうよぉ」
「つ、捕まる!?」
「そりゃそうよぉ、みんなが勝手に釣りしちゃったら、川から魚がいなくなっちゃうでしょぉ? この辺の組合がその辺をちゃぁーんと管理してんだよぉ」
「そ、そうんなんですか……」
「その釣り道具買ったところでも売ってるはずなんだけどなぁ」
脳裏にポッと、人のよさそうな釣具屋のおばあさんの顔が浮かんだ。たしか“店主は釣りにいっている”といっていた。あのおばあさんは慣れない店番でうっかりしてしまったのかもしれない。
「おんや? その袋……」
おじいさんが“釣具屋ひろみ”とかかれた袋をみつめていた。さっき買い物をしたときにもらった袋だった。
「……ハハァ……バアさんまた忘れたな…」
老人が小声でなにか囁いた。
「あの? どうかしましたか?」
「いやぁなんでもねえよぉ。そしたらよぉ若い人、俺が遊漁券を売ってあげるよぉ」
「ほ、ホントですか!? ……あ、それならちょ、ちょっとだけ待ってください。まもるさん! 出番です! 起きてください!」
金銭の話なら、まもるさんを起こさなければ。
「……う、うむん? 釣れた?」
目を擦りながら、のんきに上半身を起す。
「まだですけど、釣りを続けるために、まもるさんの力が必要なんです」
「う……う、……うん?」
まもるさんは、まだ寝ぼけている。
「あの、遊漁券はこの人が買います!」
構わずおじいさんへ話しかける。
「そうかい? ありがとさん。えっとぉ
「デ、デーパス? スゥーズンパス?」
「デーパスは今日限りの券で、スゥーズンパスは今日から1年有効になるんだけどぉ、あれだなぁ、おすすめはスゥーズンパスだな、やっぱし」
「いや、自分らは……」
どう考えても今日限りの釣り人だと思う。
「スゥーズンパスは結局、デーパスよりも安上がりになるから。あれだ、あれ、コスパってやつがいいんだわ」
『ねぇハルキ、ちょっと値段聞いてみて』
脳内からmisaの音声。
完全にこの老人を怪しんでいるような響き。
「値段を教えてもらえますか?」
「うぅん? デーパスがぁ2千円で……」
「安い! じゃあボク、買います!」
「んん? あ、いやまってくれ、それは古い値段だったなぁ……ええっと」
おじいさんの視線がじろりとねめつけてくる。
「デーパスが御1人様1万円で、スゥーズンパスは割引で2人で10万円になるな」
『たっか! 絶対に足元みて、ふっかけてるわよ! ハルキ、抗議しなさい』
「は、はい。えっとあの、それは高すぎるんじゃないですか?」
「ん? あぁそうさなぁ。店で売ってるのはもっと安いんだけどもぉ、あれだ、前売券と当日券は値段が違うでしょうよ」
「た、たしかに」
『納得してんじゃないわよ!』
「あの、いや、そ、それ高くないですか?」
「いやぁ、そういわれるとまいっちゃうなぁ。これでもサァビス価格なんだけんどもなぁ……」
おじいさんが麦わら帽子に手をあてたまま動きをとめる。
「あんれ? アンタら! みてみ!」
ペットボトルの方を指差した。
反射的に振り向いてみると──
カタタタン──
ペットボトルが微かに揺れ──
カタタタタッ──カターン
乾いた音をたて、た、倒れた!
「ありゃりゃりゃ来たんでねぇの!?」
「うむん!? ハルノキくん!」
「えっ? えっ? どうすれば」
「ペットボトルを抑えるんだよ!」
まもるさんの声に弾かれるように身体が動いた。ペットボトルを掴む。
飲み口に巻き付けられた糸のずっとずっと先の方で何かが動いている感触があった。
「き、来てるっぽいっす!!」
「うむん! ゆっくり引っ張るんだ!」
「はい!」
『ハルキ! 逃したら許さないよ!』
脳内からも檄が飛ぶ。
目をこらすと10m位先の方で水しぶきがあがっている。
「おほぉ、やったなそれ! ガンバレ! ガンバレ! あ、そうだ。こんな時になんだけんども、遊漁券はどうするかい?」
「か、買うしかないじゃないか!」
「そんじゃあ、えっと……」
「むん! ボクがお金を払います!」
まもるさんがおもむろに、右手を差しだした。
「imaGeでお支払いできますかぁ?」
「スゥーズンパス?」
「よくわからないけど、はい!」
「あっ……いや」
間断の余地もなく、imaGe決済の音が夕暮れ空にこだまする。
止める暇なんてない。両手に掴んだ糸がビックンビクン震えているんだ。
「ありがとうなぁ~。よしそしたらその当たりあげちゃおう! それ、それ、ガンバレ若いの!」
「て、手伝ってくれないんですか!?」
「それしちゃったらおもしくねーべよ! ホレ、早くしねえと逃げられっぞ! それ、それ!」
「ハルノキくん! がんばるんだ!」
無我夢中で糸をたぐり寄せていくと、次第に水しぶきが近づいてきた。
「おいタモねぇかい! タモ!」
「ま、まもるさん、タモ!」
「な、なにそれ!?」
「若いの! もうそのまんま上げっちゃえ!」
「い、いいんすか!?」
「気合いだ! 気合い! ソォレ!」
おじいさんの合図にあわせて、糸をひっぱる。
バチンと黒い物体が堤防に叩きつけられ──
「ウワッ! ウワッ!」
そこには太くて長い、黒い物体がビッチビチに跳ね回っていた。
「こ、これどうすんの!?」
陸地で跳ね回るうなぎをどう処理すればいいのだろうか。
『あのビニール袋つかいなさい!』
「は、はい!」
「水いれろ! 水!」
全員が一斉に動いて黒い物体が水をためた白いビニール袋に収められた。
「やったなぁ! 若いの!」
「こ、これうなぎっすか!?」
「むむん! すごいよ! ハルノキくん!」
ビニール袋の中を覗き込──
『すごぉい!』
自分が認識するよりも先にmisaの音声が脳内に広がる。
『やったじゃないの! 凄いわよこれ!』
改めてみてみると、太巻きのようにずっしりと存在感のある、うなぎが袋の中でところせましと跳ね回っているのがみえた。
「どうすんだよこれ」
「大将に捌いていただこうかと……」
「いや、捌くとか捌かなねえとかの話じゃなくってよぉ。さっき川で取れたもんなんて泥臭くて食えたもんじゃねえだろ? それぐらいオマエだってわかんだろうがよぉ」
「そうなんすけどね……。あのお客さん今日の昼間に駅のほうにも来てくれてて、なんとしてもうなぎが喰いてえってきてくれてる方なもんで……」
「それにしたってよぉ。うなぎ屋にうなぎ持ち込みなんて聞いたことねえだろ?」
「そ、そこをなんとかぁ……。お客様たちは、こ、こんな時間まで、うなぎを釣ろうとされていたようなので……」
通された部屋の中央には、宙に浮かぶ水槽があった。“初見字幕”は“ホバー生け簀”という解説をしてきた。
“生け簀”なのかあれは。
わざわざ生け簀を浮かべるメリットが全く理解できない。
金持ちはこういうのを喜ぶのか。
「凄いよ! ハルノキくん! 生け簀が浮いてるよ! かっこいいなぁ!」
実際、ここにいる大富豪はご満悦の様子だ。
『なかなかいい感じの店じゃない』
体内音声に切り替えたmisaもまんざらでない様子の
じ、自分のセンスが、ズレているのだろうか。
「まだかなぁ! ボクたちのうなぎ!」
一匹目を吊り上げた後、さんざん粘った結果、釣れたのは結局あの一匹だけで、“スゥーズンパス”という怪しげな券を売りつけたじいさんは、いつのまにか姿を消し、釣り上げたうなぎをどうやって食するか思案を重ねた挙げ句、昼間に地図を貰ったこの店を尋ねることになった。
“うなぎ・割烹料理
そうか……浮屋だから生け簀を浮かべているのかもしれない。
純和風の座敷を所在なく見渡しながらふとそんなことを思った。
『ハルキ。なにソワソワしてんの?』
「い、いや、別に」
『考えてみたらアンタがこういう格式高い店にきた記録、全くないわね』
「そ、それならmisaだって一緒じゃないか」
『アタシはあんたの記憶以外にも蓄えているデータや経験が豊富なの。バカにしないでくれる?』
「ハルノキくんも、misa様もケンカしないでください! もうすぐ、うなぎが来るんだから!」
『ケンカってのはね、同じレベルの者同士がするものなのよ』
「うっムン!?」
突然、まもるさんが襖の方を凝視した。
まるで、自然界の異変をいち早く察知した野良犬のような鋭さだった。
「く、くるよ! に、匂いがする」
鼻をひくつかせ──
そのとき、襖が静かに開いた。
お重をもった女性と、脇には昼間、駅にいた男が正座をしている。
「ホラ! 来たよ!」
嗅覚も完全に犬と一緒じゃないか。
「昼間は申し訳ございません。本当にお越し頂けて、大変感激でございます」
お重が目の前に運ばれてきた。
蓋が小気味よい音をたてて開かれた。
ふわりと立ち上った湯気が鼻腔を刺激する。
「う、うむむむむん! いい香りだね!」
まもるさんの鼻が広がっている。
『フンッフンフン……』
脳内でも鼻腔をひくつかせるような音が聞こえた。
「ハルノキくん!」
まもるさんが、背筋を伸ばして大声をだした。
「は、はい?」
「食べよう! いただきます!」
言い終わるやいなや、お重を持ち開けむしゃぶりつくように、うなぎを食べ始めた。
店の格式とか、風情なんていうものはまったく関係がない。
「おいしい! すごいよ! このうなぎ!」
絶叫しながら口いっぱいに物をつめこむという器用な芸当を繰り広げながらまもるさんがもの凄い勢いでうなぎとご飯をかきこんでいく。
「おみごとな食べっぷりでございますね」
お店の人はあきれることもなく、ほほえましくその姿をみまもっていた。
「ハルノキくんは食べないの?」
「あ、いや、食べます」
まあ、たしかに、これは相当に高級なものなのだろう。うなぎといえば薄っぺらいものだと思っていたけど、お重のなかのうなぎは、肉厚で大きかった。まもるさんが、我を忘れるのもムリはない。
『まちなさい! ハルキ!』
箸をつけようとすると、こんどはmisaが大音声を上げた。
「え、な、なに?」
『もっと、目で味わいなさい!』
「え……」
『アタシは食べられないのよ!』
「は、はぁ……」
それから、しばらくの間、まもるさんが食べる気配を感じながら、うなぎを凝視するという奇妙な時間が流れた。
「もう、食べれないよぅ」
結局、まもるさんがひとしきりご飯をおかわりしつづけ満腹になるころまで、自分は箸をつけることが許されなかった。
『ゆっくり食べるのよ、ハルキ。あ! だめそんなに乱暴に箸をつけたら。もっとふっくらを楽しめる角度で!』
箸をつけはじめてもまだ、脳内でmisa様がうなぎを堪能されているところである。
「くるしいぃ……」
「まもるさん、ご飯何杯食べたんですか?」
「むん? 10杯くらい」
「い、一体、なにをおかずに食べてるんですか?」
いくらうなぎが大振りだといっても……。
「タレだよ! このお店のタレがご飯にあうんだもん! しかたないじゃないか!」
「た、タレだけで……」
「それから、このお部屋に広がる匂い! うなぎに囲まれているようなもんじゃないか! ボク、お腹がいっぱいじゃなかったら、まだまだご飯たべれるよ」
それなら、店の外でご飯を炊いていればいいのではないだろうか。わざわざ、釣りまでして食材を持ち込まなくても。
「それにしても……あの一匹だけでこんなに食べられるもんなんですね」
「うむん! おっきかったからねあのうなぎ」
「あ、あの……」
部屋の隅に控えていた男が遠慮がちに口を挟んできた。
この人はまもるさんがひたすらご飯をおかわりするのに付き添っていたのか。
なんという気の毒な人なんだろう。
「あ、あの……実は……」
とても言いにくそうに言葉を発しながら、隣りで給仕してくれていた女性に目配せをした。
女性はすっと立ち上がり、部屋を出て行った。
「どうかしましたか?」
「お客様があまりにも、嬉しそうにお召し上がりになりますので、お伝えしそびれてしまったのですが……」
そこへ割烹着姿の女性が戻ってくる。
手には、うなぎの入った水槽を抱えていた。
「あ、あれぇ!? そのうなぎ!」
さっき川で釣り上げたうなぎのようにみえた。
「はい……実は、板前がさばこうとしたんですが、どうにも、泥抜きが間に合わず、こうしてまだ泳いでおりまして……」
「そ、それじゃあ、いま食べたうなぎは」
「はい。当店が仕入れました、最高級天然うなぎでございまして……」
『……なんですって……?』
「ボク、どおりでおいしいと思ったよ!」
「あ、ありがとうございます。そ、それで、大変恐縮なのですが……お会計は正規の料金となりましてぇ……」
そうか、たしかにそうだ。
あれだけ食べたんだ。料金の心配をされても仕方がない。持ち込んだうなぎだと思っていたのが、実は最高級の天然うなぎでした。といわれたら、普通の客ならば支払いを渋るかもしれない。
でも、ここにいるのは、食に対して並々ならぬ意欲を持つ、大富豪まもるさんだ。
「うむん! もちろんお金は払うよ!」
「さ、左様でございますか」
男の表情がほっとやわらいだ。
『待ちなさい!』
ま、まずい。この場に納得していないお方がひとりだけいらっしゃる……。
『つまり、ワタシたちがした苦労は……ムダってこと?』
「む、ムダと申しますか」
『ムダでしょう! スグにうなぎ食べたくて、釣りまでしにいったのよ!』
「だ、だって、釣りに行こうっていいだしたのはみ、misaじゃないか」
『だ、だって食べたかったでしょ? あのとき、うなぎ! 夜になるまで粘ったのに!』
「そ、それは、時合っていうやつを待ってたからしかたないんじゃ……」
『でもお店の仕入れたうなぎ食べちゃったら結局むだじゃない! なによあのスゥーズンパスって、普通にお店にきたほうが結局、安かったじゃない! ああ、アタシとしたことが、う、うなぎに目が眩んだわ』
うなぎは、周囲の空気をものともせず、元気よく水槽の中を泳ぎ回っている。
「むむむむ」
まもるさんが、水槽に顔を近づけた。
後ろからみていると、お、お姉さんの胸元に突進していく変態にしかみえない。
「ちょ、ちょっとまもるさん?」
「ハルノキくん、misa様! このうなぎ、よく見るとかわいいよ」
『うなぎがかわいくてどうするのよ! 連れて歩くの!?」
「そうかぁ! じゃあボク、このうなぎくんを飼えばいいんだね?」
『は、はぁ!?』
「まもるさん、か、飼うって、うなぎをですか?」
「うん! いざとなったら非常食にもなるし」
「そ、それは、ペットじゃなく家畜なんじゃ」
「名前は……そうだなぁ……」
まもるさんが腕組みしていた。
こんなに真剣に物事を考えている姿をみたことがない。
「そうだ! ノボルくんにしよう!」
「ノ、ノボル……?」
「うん! “うなぎのぼり”っていうでしょ? だからノボルくん!」
『……フンッ……知井ノボル? 飼い主よりも出世しそうな名前ね』
「お兄さん、そこの水槽みたいなの、売ってくれませんか?」
まもるさんは、ホバー生け簀を指さしていた。
「そ、その大きさのものは、予備がございませんが……仕入れ用に使ってるホバー水槽なら余ってるかもしれません」
「それ、ください!」
「ありがとうございました!」
“うなぎ・割烹料理 浮屋”の看板の下で従業員さんが総出で礼をしていた。
まもるさんが、手を振った。
その周りを、宙に浮かんだ水槽がぷかぷかと漂い、水中のうなぎがくるくる回った。
なんだこの光景は。
まだ従業員さんたちは、頭を下げている。
まあ、飛び込みで入った客がウン十万円の飲み食いをしたうえに水槽まで購入して帰るのだから、それぐらいの送迎はあるのかもしれない。
「ハルノキくん今日はどこに泊まろうか?」
果たしてうなぎを連れて泊まれる宿があるのだろうか。
「それにしても今日は楽しかったなぁ!」
『釣りの時間は無駄だったけどね』
misaも少し機嫌が直ってきたようだ。
「ボクは、釣り楽しかったけどなぁ!」
なんという空気を読まない発言なのか。
酒は一滴も呑んでいないはずなのに、まもるさんは上機嫌に仕上がっている。
また、怒りを買ってしまうじゃないか。
「ねぇねぇハルノキくん!」
まさか、明日も釣りに行こうなんていいだすんじゃないだろうな。
「明日さ、街に買い物に行こ!」
「ン!?」
「ノボルくんのためにいろいろ買い物したいし、あとボクね、考えてたんだけど、misa様にお礼がしたいんだぁ」
『えっ!?』
「こんなにおいしいうなぎ食べれたのもmisa様のおかげだし」
『や、やめてよ、なんか気味悪いわ』
「ボクね、misa様と一緒にうなぎ食べる方法を思いついたんだぁ!」
まもるさんが、目一杯胸をはる。
一瞬、隣に浮かぶ水槽のなかで、ノボルも立ち上がったようにみえた。
次回 2019年01月11日掲載予定
『 バディのボディ 02』へつづく
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする