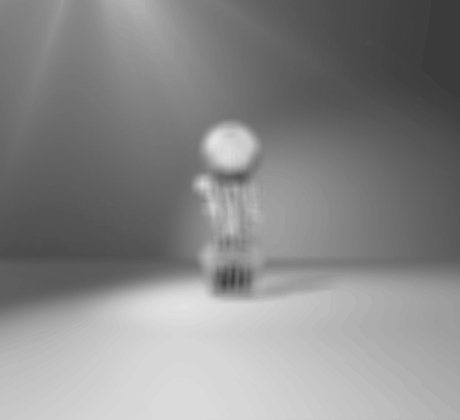第86話『盛り上がりは貴方の胸と肩に 02 』
「第七支部長はさ、いくつから吸ってるの?」
「い、いちおう、法律は守って20歳からだね」
「それは、タバコでしょ? 違うよ、おっぱいはいくつから吸ってるの?」
「お、おっぱい? そりゃ、生まれたころからに決まってるじゃないか」
「でしょう! 男に生まれたらさ、おっぱい吸い出してからというもの、その先ずぅーっと、おっぱいのこと考えてるわけじゃない? おっぱいのことについて思案するのって、生まれた直後から備わってる本能なわけで! いってみれば全員プロの鑑乳士なわけでさ」
「いや。それは違うんじゃないかな。全員が胸にばかり興味があるわけじゃない。現にわたしなんて最近じゃバストよりもヒップとかレッグのほうへ活動の拠点を移しているから……」
「それじゃなんのために今日ここにいるんだい! chibusaさんに失礼じゃないか。いいかい、chibusaさんが凄いのはさ、そこら中にいるの鑑乳士を黙らせる絶対的な美的様式にあるんだよ。10代、20代になったらさ、もう、おっぱいのことなんて四六時中考えてるわけじゃない。揉みたいとか、うずもれたいとか、もうありとあらゆる欲望の対象なわけでさ」
「……だ、だから全員がそうじゃ……」
「毎分、毎秒、常に脳内でぷるんぷるんしてるわけだよ。おっぱいが。それって、タバコをすぱすぱ吸ってるチェーンスモーカーみたいなもんでさ。タバコ吸ってたらもう味なんてわかんないわけじゃない? 味とかじゃなくていわばさ惰性で吸うようになるでしょ? 男たちのおっぱい感もやがてそうなっていって、女の子の裸をみてさ冷静に“あぁ釣り鐘型ね”とか分析できるようになっちゃうんだよ! でもね! それを捥ぎ取ってくのがchibusaさんなわけ。もうさ、重いタバコ吸った後なのにヤニクラが来ちゃうみたいなやつ、強制的なパイクラさせちゃうとこなんだよ」
「ちょ、ちょっと落ち着こ……」
「失礼いたしまぁっす! 追加のドリンクをお持ちいたしましたぁっ!」
「ほ、ホラ、ドリンクも来たし……」
「デリカーライチをご注文のお客様っぁ!」
「あ、ああ、わたしだ」
「ホットミルクをご注文のお客様っぁ!」
「うん。僕」
「まず、落ち着こう」
「……うん…………ちょ、ちょちょちょちょちょちょちょちょっと、キミ?!」
「は、はぁっいっ!?」
「キミぃ……わかってるね!」
「あ、ありがとうございまぁっす!」
「えっ? ここヴァーチャルだったよね? 現実でもこんなに完璧な再現ムリじゃない? かんっぜんに人肌じゃないの、これぇ!」
「おそれいりまぁっす!」
「キミ、名前は?」
「わたくしぃ、コージともうしまぁっす!」
「コージくん。うん、覚えとく。うん。キミ、やるなぁ」
「ありがとうございまぁっす! それでは、失礼いたしまぁっす!」
「ちょ、ちょっとボーイくん」
「はぁっぃっ!」
「……い、いやなんでもない……ご苦労さん」
「失礼いたしまっぁっす!」
「ねえ、支部長も触ってみて、これ、もう、かんっぜんに、人肌でしょ?」
「う、うんそうだな……」
「人妻さんのさ、熟れに熟れきった、しなだれかかるような肌を、ありありと想起させるでしょ?! 僕さ常に哺乳瓶にはこだわっててさ、ミルクの温度はいろいろ試してるんだけど現実世界でもやっぱり室温や湿度によって変わるんだよその日のベスト温度って。わかるでしょ?!」
「わ、わたしは、だから最近ヒップとかレングス系の方に主眼をおいてるから」
「いやぁ、このミルク、久しぶりに驚いた。うん。こういうことなんだよ。毎日繰り返すルーティンをぶっ壊してくれるような出会い。それをアートに求めているんだよ。最初のがつーんっていうインパクト、初期衝動ってやつ。ロックでもさ、前衛的な音がやがてジャンルで括られてくでしょ? その音がはじめて形容された瞬間のあれと一緒でさ。そういう驚きと体の下部から沸き上がってくる衝動があったんだよ。chibusaさんの作品には!」
「わ、わかったから、少し、ミルク飲んで落ち着こう。この部屋、外部音声オンに設定してるから、あんまり取り乱したらみっともないぞ」
「……ごめんねっ僕、つい、エキサイトしちゃって……今日ね、ちょっと緊張してるのかも」
「緊張!? キミが?」
「chibusaさんに会えたら、僕の考えてることを伝えてみようと思ってるんだ!」
通りを行き交う人びとはみな正面を向きタバコを吹かしながら歩いてく。
なぜ、素通りできるんだ。
あの建物を。
夜空の雲の切れ間からぽっかりと顔を出した満月のごとく頭上に輝く神々しい光。極彩色のネオンで彩られ、圧倒的な存在感でストリートを照らす、あの『ショルダーパッド』を。
「は、ハルノキくん? 震えてるよ?」
まもるさんに言われ、自分が肩を抱いていたのに気づいた。
「つ……ついに来たんだと思うと感慨ぶかいというか……武者震いのような……」
「そうだね! 長かったからねぇここまで」
テレポーテーションでたどりつけると思いきや、業者に欺され竜良村で農作業を強制され、バイトで激ヤセしてヒーローになり富豪になった後、とんとん拍子で大富豪まで登り詰めたにも関わらず、列車の中で死にかけ、挙げ句の果て無に一文なしまで落ちた、まもるさんがいうと言葉が重い。
「まもるさんなんて、天国と地獄、三往復くらいしましたもんね、よく無事でしたよね」
「ハルノキくんがいてくれたからだよ」
「まもるさん……」
『いや、いいからさっさと中に入れてもらえよ。このまま突っ立てたらアンタたち路上生活者とかわんないから』
misaのあまりにリアリティのある例えが、追憶にふけりかけた気分を現実に引き戻した。
「ま、まもるさん。行きましょうか」
ショルダーパッドの入口は通りにせり出す長い階段を昇った所にあった。
まるで天空につづくかのような階段を踏み──
「ああ、ちょっとぉ」
階段の左側に立っていたのは、日焼けした男。黒いジャケットに色をあわせた蝶ネクタイ……。
「失礼ですが、ご来店のお客様ですか?」
男のジャケット、いや、“肩”が揺れた。
遠近感を完全に失った異次元の“肩”。
尋常ならざる張り……、間違いない。
ショルダーパッドの黒服さんだ。
「じ、自分! ハルノキナツオと申します!」
「は、はい?」
黒服の表情がとたんに険しくなった。
「や、あの、棚田さんにご挨拶をしたくて」
「棚田……にご用ですか?」
「じ、自分、棚田さんにダ、ダンスコンテストの紹介をうけてまして」
男はすかさず、こめかみに指をあて、視線を逸らす。どこかへ連絡をいれているようだ。
「……ハルノキさんという方がお越しです……はい……棚田さん………はい……ええ……」
表情が険しくなっていく。
「あ、あの、きょ、今日、会うとは約束していないんですが……」
声をかけたがこちらを向こうともしない。
「はい、はい……はっ、あっ! っすか! あ、はい! さっすさっす! っかりしたー!」
男のテンションが途中から跳ね上がり、こちらを向いたときには白い歯をむき出しにした表情を惜しげも無くみせてくれた。
「お待たせいたしました! 棚田はただいま取り込み中のため中で待ってくれとのことです!」
「い、いいんすか!?」
「どうぞ! こちらです!」
黒服が陽気に右手を掲げたまま階段をのぼりはじめた。
こんなに、すんなりと……。
ディスコといえば、入口で厳しいドレスコードチェックを受けるものだと思っていたのに……、これ、いわゆる“顔パス”ってやつじゃないか!
もしかすると、母ちゃんがオーダーしてくれたこのトリプルドレープ、カスタムショルダージャケットのおかげかもしれない。
「そういえば、ハルノキさんのことは棚田がよく話をされておりましたよ」
「ほ、ホントですか!?」
「はい。面接であれほど好印象を持った青年はいないと……」
『その人、経営者としてやっていけてるの?』
misaがすかさず“
「それだけ“盛り肩ファッション”を着こなしてる方は、当店のコアなお客様にも少ないですよ」
ライトアップされた踊り場で振り返り黒服が笑う。黒く日焼けした引き締まった表情に、白い歯が映える。
「さっ、こちらからお入りになって受付で棚田を呼び出してください」
「わかりました!」
闇夜に浮かび上がった白亜の扉が開く。
巨大な壁のように迫ってくる。まるで異界へ誘うかのように、隙間が少しずつ広がる。
「ご来店、ありがとうございまぁっす! 盛り上がりはアナタの胸の奥と肩の上に。バブリーディスコ ショルダーパッドへよぉっこそぉっ」
受付で控えていた黒服のよく通る声がした。
こ、この人はもしかしてあのときの……。
「あ、あの……棚田さんに面会を……」
「はぁいっ! 承っておりまぁっす! 棚田はぁ、ただいまぁ、立て込んでおりまぁっす。そちらへ掛けていただきぃっ少々お待ちくださぁっぃ!」
間違いない。あの絡みつくような独特の発声。以前にVOICEで話したときの店員さんだ。
胸元に金文字で「KOHJI」とかかれた黒いネームプレートがみえた。
「あ、あの自分、ハルノキ、ナツオです!」
「わたくし、コージっともうしまぁっす!」
「ぼ、ボクはマモル!」
「お二人とも、ヨロシクおねがいいたしまっぁす!」
「あ、あの! コ、コウジさん……」
「おそれいりまぁっす! 店内ではぁコウジではなくコージ、でお願いしまぁっす!」
だ、だから、アルファベット表記に“H”が入っているのか……。
「こ、コージさん、あの、以前、VOICEで話したの、コージさんですよね?」
「そうでしたかぁっ?」
「はい! なんていうか、特徴のある話し方なんで、覚えてます!」
「ありがとうございまっぁっす!」
コージさんが頭を下げたとき、背後がにわかに慌ただしくなった。
大きなサングラスを掛けた女性を3人のスタッフが取り囲みながら誘導していった。
「なんだか忙しそうだね」
まもるさんがノボルに餌を食べさせながら、のんびりと呟く。
「あの、棚田さんは……」
「まもなく参りまっぁす! ラウンジへご案内いたしますのでそちらでお待ちくださっぁい!」
「chibusaさんに意見をぶつけるって、なにを言おうとしてるんだ?」
「うん……chibusaさん、最近、迷ってるんじゃないかと思うんだ」
「ま、迷ってる?」
「方向性が変わってきちゃってる。そりゃね、初期衝動の衝撃が凄いほど、次にそれを乗り越えるのは並大抵のことじゃない。自分自身が生みだした“新たな衝動”を乗り越えていくのがアーティストの宿命だとは思うんだ。自分の壁をどう乗り越えていくのか試行錯誤してね、いや、僕がいうのも、相当おこがましいけど」
「そ、そうだな確かに相当おこがましいな。彼女は世界屈指のバウンスアーティストだぞ?」
「わかってる! でもね最近のchibusaさんの作品は違う! 『ノースリーブの隙間』『胸びらきデコルテ』『桜殺し』の“カシミヤ三部作”だした頃なんてさ、もう完全に神がかってたでしょ? セーターの緩やかな質感のなかで、暴れ惑うように躍動する重厚な乳房のバウンス。着衣であるが故の衣服の素材、質感、しずる感まで全部完璧に操って望郷とかさ、はたまた衝動的な興奮とか、ベッドのうえでのたうち回るようなもんっもんとする熱情で世界中の人間のこころをぐわーっと鷲摑みしちゃったじゃない!」
「だ、だからそれからも同じ、いやそれ以上の評価をうけてるじゃないか」
「違う! 『休息』『Blur-bra』『止まり木に咲いた華』『解放』『G ~G曲線上の女神習作~』そして『G曲線上の女神』この頃の作品のバウンスは、四六時中脳内から離れなかった。それこそ本当に脳内再生を繰り返して、ひと晩明かしたことなんて一度や二度じゃない! それがさ、『パフィーニップル』とか『微と美』あたりから今の路線にいっちゃたんだよ。あれじゃあダメなんだ。なぜあの躍動感と重量感を捨ててしまったのか。ぷるぷる、ぷるっんぷるっん、ブルンッブルン、ボフンボフン、ゆっさゆっさ、たゆんったゆん、タップンタップン、もうさ、オノマトペだけでさ脳内にイマジネーションが華開くわけでしょ? スペクタクル! オノマトペクタルだったんだよ! だった。だったのに! 今のchibusaさんの作品に、僕の心は揺れない!」
コージさんに連れられ通されたのは、ディスコフロアへ続く通路の手前にあった妖艶な空間。
背の低いソファが円卓を取り囲むように並ぶ。一番手前のテーブルには“Lounge-310”という小さなプレートが置いてあった。
曲線を描くように窓際に配置された座席はどこからでも夜景を眺められるつくりのようだ。
窓に映るのは、地上を一望する高層階からの夜景。
「いらっしゃい……」
窓と平行に伸びるシンプルなバーカウンターの中にいた長身の女性が、グラスを磨く手を止め、ぽつりと呟いた。
「ノゾミさっぁん! 2名様、ご案内でぇっす! お願いしまぁっす!」
落ち着いた空気の中へ、コージさんの声がハキハキと流れ込む。
「そちらへどうぞ……」
カウンターの女性は、コージさんとは対極のクールな声で、窓際の一番奥の席を示す。
髪をアップにして束ねているせいか、切れ長で涼しげな目元が際立つ顔だった。
「それからっぁっ、ノゾミさっぁん! 先ほどはミルクの温度設定、ありがとうございまっぁっす! お客様、ご満悦でしたっぁ!」
「ぁ、そう……」
「それでは、しばらくお待ちくださっぁい!」
この場とテンションが噛み合わないままの、コージさんは持ち場へと戻っていった。
「ここ、すごいね! ハルノキくん」
まもるさんがキョロキョロと辺りをみわたす。
「か、カッコいいっすね」
ラウンジには光量が絞られたほの明るい球体がそこかしこからに浮かび、絵画のような額装が施されたエアロビジョンにはフロアや個室の様子が映しながら宙を漂っている。全体的に、心地よい静けさ広がっている。
『内装のセンスはいいわね』
misaも気に入った様子だ。
「あそこにも、いろいろ飾ってあるね」
まもるさんはラウンジの奥にあるショーウィンドウのような場所を指さす。スポットライトがあたりそこだけが別世界のように輝いていた。
「あ、あ、あ、あれは……」
キラリと光る物に惹かれ、思わず席を立った。
「う、うぉぉ!」
光の中心には、3人のソウルフルな男たちがミラーボールを支えている姿をかたどった黄金色の物体、台座に“VIP”と“2063.08.31”と刻印されたレリーフ。
「ダンスコンテストの日付……こ、これはダンスコンテストのトロフィー!? い、イカス! あ、あれ……」
まるで優勝者が浴びるスポットライトを先に浴びているかのように輝くトロフィーの後方に、段ボール箱がいくつか置かれていた。
その中のひとつから小麦色に焼けた肌を思わせる褐色のビニールが飛び出ている。
も、もしかしてあれは……ク、クミ──
「さわんないで」
背中に氷を放り込まれたような寒気を感じ、手を引っ込め振り向くと、ノゾミが研ぎ澄まされたナイフのような視線をこちらへ投げかけていた。
「勝手に触られるとアタシこまるんで」
「す、すみません!」
「で、注文は」
「はっ、え?」
「注文は?」
そうか、たしかに飲み物のひとつも頼まないのは、きわめて不自然だ。し、しかし自分たちにはもうお金がない……。
「ねぇ、注文」
カウンターの女性は瞬きを止めたまま真っ直ぐにこちらを見据えてくる。
「あ、あの……」
「な、に、飲、み、ま、す、か?」
ひとことごとに言葉が威圧的に飛ぶ。
よく考えてみれば、この女性はなぜ、客に対してここまで高圧的な態度を取るのだろうか。
『ハルキ、正直に謝りなさい。お金がありませんって』
脳内音声からは嘲笑気味の
「ハルノキくん、ボク、メロンソーダ!」
そして、財政崩壊を理解できないまもるさん。
「いやぁ、お待たせいたしました」
追い詰められた場面に現れた、ヒーローのような声がした。
ラウンジの入口に立っていたのは、見覚えのある人影。
「キミが、ハルノキくんでしょ?」
その姿は、VR面接のときにみたあの姿そのもの。優雅で気品あるドレープを描くイカしたジャケット。首元を彩る極太の純金ネックレス。
「た、た、棚田さん、ですよね……?」
「そうだよ。やっぱりハルノキくんか! はじめまして!
「は、はじめまして! た、棚田さんも! むしろ、現実の方が、バブリーっす!」
「ハハッ、いちおう、バブリーディスコの支配人だからね」
ジャケットのサイズ感もあってか、大柄なシルエットで棚田さんは近づいてきた。
カウンターへ目をやると、ノゾミは満面の笑みで微笑んでいた。
「棚田さぁん! お疲れ様でぇす!」
「やあ、ノゾミちゃん。お疲れ様。コーヒーもらえるかな、あ、ハルノキくんたちにも」
「はぁーい」
まるで声まで笑顔にしたような対応だった。
『あの女の子、なかなか見所あるわね』
なぜそういう評価になるのか理解できない。
「すっかり待たせてしまって申し訳なかったね、ちょっとVIPルームがたて混んでてね」
「び、VIPルーム!? あ、あるんですか?」
「ハハッ、そりゃあ、あるよディスコだから。うちのは、VR-VIPルームになってるから現実とかけ離れたゴージャスな部屋だよ」
「み、見てみたいっす! VIPルーム!」
「もちろん、みせてあげるのは構わないんだけど、今夜はちょっとムリかな……だいぶ豪勢に盛り上がっててね……」
棚田さんが空中の1枚のエアロディスプレイへ視線を向けた。
「シリコネスタ協会っていう、道楽家の中では有名な会の幹部さんたちだよ」
………し、シリコネスタ……協会……?
どこかで聞いたことのある名前だ。
「さらに今夜はうちの店にとっても、大切なお客様が来てるからね」
エアロディスプレイの中で動く2体のアバターがみえ──
「え!?」
そ、そのうちの1体に視線をもぎ取られた。
「あ、あれは……」
深海で静かにうねる海藻のような長髪。
全ての光を吸収するかのごときサングラス。
「ん? ハルノキくんもしかして知り合い? なんて、まさかね」
ま、間違いない……。
“人生忘れようにも忘れられない顔ランキング”があったらNO.1の座を30年は独占しそうなヴィジュアル……。
「あ、あれは、と、豊川……豊……」
次回 2019年03月01日掲載予定
『 ボーイ スカウト 』へつづく
──ガガ エマージェンシー エマージェ……トモイリ! ちょっとコイ!!──
「お、おい、エマージェンシーコール、途中できれたぞ」
「いやぁ、イナサクは最初っからキレてたぞ。ぶははは」
「元禄さん、酔ってる場合じゃないっすよ」
「なんでだよ! 村はじまって以来の好景気だぞぉ? 今日も朝からフィーバーでいいじゃねえかよ!」
「で、でも、あのイナサクさんの怒り方、ただごとじゃなかったすよね」
「呼ばれたのはトモイリだろ? そこで寝てるから起こしてやれぇ」
「や、お、起きて……ます……」
「なんだぁおまえ、起きてたのか」
「いま、自分呼ばれてたっすよね?」
「あぁ、んだな。イナサク相当、キレったな」
「い、い、い、い、行かないと、マズイっすよね……やっぱり……」
「当たり前だ。元禄さんはともかく、俺たちまでとばっちりくらうじゃねえかよ。さっさと出頭してこい」
「しゅ、出頭って、んな犯罪者みたいなこと言わないでくださいよ、は、はははは」
「トモイリ。なんで呼ばれたかわかってんな」
一瞬の間を開けるだけでも、アウト。
機嫌を損なったときのイナサクさんを、間近で観察してきた自分なりの結論だ。
「オッス!」
「なんだ。いってみろ」
「オッス! ………………オッス! ……オ」
「馬鹿野郎!」
左頬が右頬にくっついたかもしれない。
だがひるんではいけない。
膝をついたらもう一発くる。
「オッス! すみません!」
「……まもるの口座が凍結された」
「えっ!?」
「どうすんだ………TA-GOの売り上げ」
「あっ……あの」
「未回収の分、オマエの売掛だぞ」
「そ、あ、え?」
「とりあえず昨日のボーナス全部だせ」
「つ、使っちゃいました……」
「そうか……じゃあ! 今すぐまもるから回収してこい!」
「オ、オォッス!」
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする