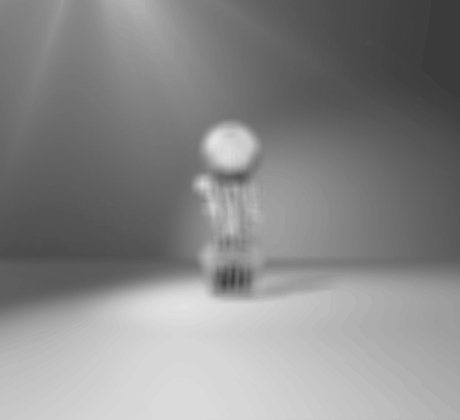第87話『 ボーイ スカウト 』
「あれかなぁ、やっぱりさ、入口で待ってた方がいいのかもしれないね。うん。心意気っていうのかな、熱量。だよねこういうの。真剣さアピールしてなんぼなのかもしれないよね」
「と、豊川くん。急にどうしたんだ!?」
「よく考えてみたらさ、いくら支部長が顔見知りのお店でもさぁ、なんか偉そうじゃない? あのchibusaさんが作品をつくりにくるお店だよ。ここ。僕なんかがどっかりとソファに腰かけて部屋に呼びつけるなんておこがましいよね。うん」
豊川が立ち上がろうとしていた。
さっきまであんなに作品をけなしていたというのに。
「やっ、豊川くん。逆に考えようじゃないか。こっちがへりくだりすぎたら向こうにナメられるかもしれないぞ。ここは、でっしり、ドーンと構えてたほうがいいんじゃないか?」
「僕、ナメられるの嫌いじゃない。それに、そろそろ、
「ご、ゴール?」
「おしっこガマンするのってさ、ちょっと、気持ちいいじゃない? だから僕、いつも限界まで耐えることにしてるんだけど、お店着いたときがちょうど折り返し地点だったからそろそろGOALに到着するころなんだよね」
「ログイン前に、トイレいってないのか!?」
「だから僕、フロントで待つことにする!」
「ま、まぁ、まぁ、まぁ、き、きっともうすぐ支配人がchibusaさんを連れてきてくれるから」
「ほ、ほんとに?」
「間違いないって。店に入るときシッカリ頼んどいたから! と、とりあえず飲もう!」
なんという下品な会話なんだ。
上質な静寂をたたえるLounge-310へ、毒々しい二人の会話が流れこんでいた。
なぜ、外部に音声を“聴取可能”にした状態で、あんな会話ができるんだ。長い海藻のような髪を振り乱す、あのアバターをみたのは『豊川個人事務所』へログインしたときだったか。
ビジネスオフィスのカテゴリであるにも関わらず、ログイン時には“アダルトコンテンツを含みます”と警告されるVRルームだった。
チクリンともども、いかがわしいVRルームを所持する人間たちは、なぜ現実世界の容姿を隠さないのか疑問を抱いた覚えがある。
「やっぱり、あの人、まともじゃない……」
「ね、ねえ、ハルノキくん。あの男性とホントに知り合いなの?」
棚田さんがなにかを推し量るような顔でこちらをみていた。
「ちょ、ちょっとした……知り合いです」
大丈夫だろうか、あんなおかしな人間と知り合いだと名乗っても。
「そうか、それじゃ、ちょっと頼まれてくれないかな」
「へ? 頼まれる?」
「この中に、お二人がいるんだけどさ……」
その部屋はメインフロアを上から見下ろせる位置にドカンと構えていた。
スモーク状態になった総ガラス張りの壁の一角がドアになっている。
「本当は、別のお客さんに勝手にみせちゃいけないんだけど……ちょっと中を覗いてみてくれないかな」
棚田さんが、ドアをそっとあける。
「え!」
中には大きなコの字型のソファ、そこに豊川の本体と、支部長と呼ばれた男の本体が横たわっていた。豊川は大股を開いて仰向けにのけぞって……。
「ええ!?」
豊川の股に目を向けたときドアを閉められた。
「あ、あ、あの人……」
「う、うん……」
「も、も、もう、漏れてたじゃないですか!」
「そうなんだよね。ハハハ、さ、さすがに、まずいよねぇ、ハハハハ。かれこれ5時間くらい籠もってて……ハハ、まいったよね」
「これ……もう、セキュリティ・ポリシーに連絡したほうが……」
「いやぁ、いちおうもう1人は常連のお客さんだし、できればそれは避けたいんだよねぇ」
「じゃ、じゃあ、どうすれば……」
「chibusaさんを連れていって、満足してもらうのがいちばんいいんだろうけど……」
「あっ、いたっ。棚田くん!」
突然背後から女性の声がした。
振り向くと、胸元が大きく開いた紺碧のサマードレスドレスに身を包んだ女性がたっていた。
エントランスで大勢のスタッフに誘導されていた人だ。
「チーちゃん!? 出てきちゃったの?」
棚田さんが、頭をかきながら彼女へ近づく。
「退屈だったから」
「ご、ごめんね、休めるところ、事務所くらいしか空いてなかったからさ、ハハハ」
さりげなく左手を握りエスコートしてきた。
「ちょ、ちょっと、アレだけど紹介しちゃっていいかな? こちらはハルノキくん。今度のダンスコンテストに出場するために、はるばる
「
この人が、豊川が待ち続けている女性か。
それにしても、棚田さんはいま、チーちゃんと親しげに……。
「あ、あの、もしかして、棚田さんの、彼女さんですか?」
「フフ、なかなか鋭い少年ね。たぶん、棚田くんの元元元元元元元元彼女くらいだと思うわよ。ねっ棚田くん?」
チブサさんがイタズラっぽく、目だけで棚田さんを見上げた。
「や、やだな、そんなに無節操じゃないよぉ。大学時代のサークル仲間だよ、ハハハハハ」
「そうね、とぉっても仲の良かった仲間だったわよね」
「や、やめてくれよ、もう。誤解されちゃうじゃないか」
「あら、アタシは別に平気よ。誤解や非難されるのなんてしょっちょうだもの。慣れっ子よ。それに、棚田くんとなら誤解されてもいいかなぁーなんて、アハハッ」
「オイ、オイ」
二人は見つめ合い、はにかむように笑う。
「大学時代とは違うんだから。チーちゃんいまじゃ、世界的アーティストでしょ?」
「棚田くんだって、こんなに素敵なディスコの支配人じゃない」
まるで、台本でも用意されているかのような、息の合った掛け合い。
正統派トレンディドラマから抜け出してきたような空気感。
「で、アタシは、いつVIPルームにつれていかれればいいの?」
「そ、それが……うん………お願いしたいんだけど………あそこには……」
確かにあの地獄絵図のような部屋に大事な友人を招待する気にはなれないだろう。
「なによぉ! 今日は早く終わらせて飲み行こうっていってたじゃない! アタシ、今回は棚田くんに頼まれたからきたのよ? じゃなきゃ、頼まれ仕事で作品つくったりしないんだからね」
「わかってる……ハルノキくん! 悪いんだけど一緒にあの部屋にログインしてくれないかな」
「じ、自分すか!?」
突然、ドラマの世界に引き摺り込まれた。
「知り合いなんだよね? お願いね? ね?」
「い、いや、自分、そこまで深い知り合いというわけじゃ……」
む、むしろ、敵のような存在なのだが。
「もうひとりの支部長さんは常連さんで、羽振りのいい方だから、顔を立てときたいんだよ……お願い!」
「VRゴーグル、お持ちいたしましたっぁ」
VRリクライニングソファが5台横に並んだ個室で待機していると、コージさんが左手に黒いトレイを持って現れた。
「お、ありがと。あ、ねえ、今日のお客さんの入りはどう?」
中央のソファにもたれていた棚田さんが頭を上げコージさんへ声をかけた。
「今夜もたくさん、ご来店いただいおりまっぁっす!」
「そうか、じゃあこの後も頼むね」
「はっぁい! お疲れ様でっぇっす!」
棚田さんへ黒いトレイを手渡し、コージさんは颯爽と部屋をでていく。
「今のがコージくん。うちのシフトリーダー」
「さっきラウンジに案内してもらいました」
「あっそうか。彼はね仕事できるんだよ。テキパキしててね」
棚田さんはチブサさんのVRソファの角度を調整しながらトレイに載っていたVRゴーグルを取り上げた。
「チーちゃん、これよかったら使って」
「ワタシ、自分のじゃないとダメなの」
チブサさんは薄いVRゴーグルを持ちあげた。シンプルで美しい曲線のゴーグルが、白くて細い指によく似合っていた。
やっぱり、世界的なアーティストの持ち物はゴーグルひとつとっても洗練されている。
「そっか、ハルノキくんは?」
「じ、自分もこれが……」
「おっ! すごい! フローティングメガネ! いいの持ってるね!」
「キミ、なかなかいいセンスしてるわね」
チブサさんも上体を起こしこちらをみた。
「い、いや、あの、さっき一緒にいた、まもるさんのご厚意で手に入れたものです」
「そういえば、まもるさんは一緒じゃなくて、よかったのかい?」
「大丈夫です。あの人はジュースと食べ物がある場所にいればおとなしくしてますから」
まもるさんは、いまごろLounge-310で、カウンターから睨みをきかせるノゾミの視線に怯えながらメロンソーダでも飲んでいるだろう。
「それじゃあさ、2人ともスタッフ用のログインルームからで申し訳ないんだけど、VIPルームへアクセスしてくれるかな」
あの地獄のような部屋からのログインでなかったことだけが不幸中の幸いだと思う。
視野内を確認する。視界の中央に宝石を盛りに盛ったギラギラした『VIP』アイコンが浮かびあがってきた。
「棚田くん。このアイコン、あんまり品がよくないわね。なんか主張しすぎだと思う」
「ハ、ハハハ、どうもねお客様はみなさんこういうギラギラしたのが好きみたいで……と、とにかくアイコンをタップしてくれないかな」
アイコンをタップする。
視野がホワイト……ではなく黄金色に輝いた。
そのまま視界がゴールドに染まっていく。
ほ、ホワイトアウトならぬ、ゴールドアウトなんてはじめてみた──
──ゴールドイン、ゴールドアウトのエフェクトはいつものホワイトアウト、ホワイトインよりも、心なしか光が強い感じがした。
ログインが完了し目を開いても、まだ視界がぼやけている。
戻りはじめた視界にいちばんはじめに映ったのは、うねる海藻のような髪の輪郭。
焦点があうと、いきなり豊川と目があった。
「うぅぅん? ハルノキくん?!」
奇妙に口をゆがめて豊川が腰を浮かせた。
サングラスが妖しく光る。
「ご、ご無沙汰してます……」
「ちょ、ちょ、ちょ、なんでキ、キミ……」
「お待たせいたしましたぁ!」
豊川の
棚田さんのアバターは、面接のときに見たイカツく肩パッドの効いたジャケット姿。
「棚田くん。待ってたよぉ」
豊川の対面に座っていたアバターが両肩を持ちあげながら陽気に笑った。頭上には『渋井川 長三郎』と表示がでていた。
もしかすると“支部長”というのは、“渋長”からきているのだろうか。
「いやぁ、支部長、もぉしわけございません。ちょっとお店の方が立て込んでましてハハハ」
「ち、chibusaさん!」
豊川が
「はじめまして! わたくし! 豊川豊です! 上から読んでも下から読んでも、豊川豊です!」
豊川はまるでロデオするカウボーイが暴れ馬にまたがるように激しく上下に揺れながら、御辞儀をしていた。
「ちょっと、アナタ。近い」
覆い被さるほどの至近距離によった豊川、迷惑そうな顔で上半身を少し反らしている女性型アバターの頭上に『chibusa』と表示がでていた。
チブサさんの名前はああいう綴りなのか。
姿も現実に近い容姿をしていた。なにかしらの分野において頭角をあらわにする人物は仮想空間でも堂々と素顔をさらすものなのかもしれない。
「うぅぅぅぅぉぉぉおおおお! なんと、凜々しいお姿! いつも、作品拝見してます!」
「と、豊川くん落ち着こう。みなさん、びっくりしてるじゃないか」
支部長が豊川を羽交い締めにして、ソファへ座らせる。
「いやぁ僕、chibusaさんがデビューしてからずぅっと、もうずぅっと作品、頭の中で垂れ流しですよぉ」
今、現実では尿も垂れ流しにしている豊川が堂々と両手を広げた。
「chibusaさんのバウンスは、ブインブイン“動く”という行為で、僕たちのハートをググっと“掴む”んで、グィングィン揺さぶってくるんです!」
広げた両手が豊川の胸元でしゃかっしゃかと動く。声には熱が込められていく。
「僕は、あの衝撃にやられた人間です! 素晴らしきバウンス。揺さぶられる全身のリビドー。騒ぎだす全身の細胞! chibusaさんの作品なしでは生きられないんです!」
「あ、あの……ところで、chibusaさんの作品ってどんなものがあるんですか?」
「な、なにをいいだすんだ? ハルノキくん? 正気かい? キミ!」
少なくともアナタよりは……といいたくなったが我慢した。
「chibusaさんは“揺れ”というシンプルな動作を完全にアートの領域へ昇華させた稀代のバウンサーだ! ……ちょっと待ってハルノキくん!」
待つも何も、いまこの人の話に追いついていけている人間がいるのだろうか。
「なんでハルノキくんが一緒なの?!」
「じ、自分ですか? ……いや、自分は……ダンスコンテストに……」
「そうじゃない! なぜ、chibusaさんと一緒にログインしてきたの?!」
「そ、それは……」
棚田さんと目が合った。
「ハ、ハルノキくんは、豊川様とお知り合いだとうかがいましたので……」
「違うわ。アタシのボディーガードしてくれてるのよ。危ないヤツがいるようにみえたから。この部屋」
chibusaさんのアバターが、豊川との間に入ってくれた。
「失礼だけど、アナタこそ何者?」
「僕は豊川豊です! チクラーです!」
「なに、それ」
「chibusaさんの作品にクラクラきてる僕たちのことです!」
「センスない。辞めて、それ」
「お、恐れ入ります! 僕、本人の前でチチクラーとかいっちゃいましたね。いやぁ参ったなぁ」
あれだけ冷たい嘲笑を浴びてなお、豊川はへらへらと笑いながら顔を赤らめた。
「朝一番のリニアにのってきたかいがありましたよ。やっぱり、熱意って大切ですよね」
「熱意なんていつか醒めるものよ」
「僕のは醒めないです。はい。もう、燃えさかってますから」
「それじゃそのまま灰になるまで燃えてたらいいんじゃない? そろそろワタシ失礼するわ」
「あ、、chibusaさん! 待ってください! 折り入ってお話が!」
豊川が直立した状態で固まる。
極度のなで肩が、引き締まり口元は嬉しそうに吊り上がっていた。
chibusaさんはその姿を一瞥して、あさっての方向へ顔をそらす。
「chibusaさんの作品を譲っていただけないでしょうか!」
「ヤダ」
「お金ならあるんです。ひとつだけでも……」
「ヤダ」
燃えさかる炎のような豊川の興奮へ、まるで暖炉の薪でもくべるようなテンションのchibusaさんが、どんどん豊川を煽っていく。
「ど、どぅして、ですかぁ?!」
「アンタのことが気に入らないから」
「ぼ、僕がですか?」
「作品の解釈は自由。でもアナタからは邪念しか感じないわ」
「そんなことは、ありません!」
「そもそもバウンスはね、あんた達の欲望を満たすためのものじゃない」
chibusaさんがついに、立ち上がり豊川へ音声を浴びせはじめた。
「じゃ、じゃあ、せめてchibusaさんのサインだけでも……」
「絶対にヤダ。アナタには、作品を売らない。サインもしない。絶対に」
「ちょ、ちょっと、チーちゃん」
棚田さんがchibusaさんをなだめはじめた。
まるで男の子を苛めすぎた妹をかばう兄のように心配げな表情の棚田さんを眺めていると……。
(キ、キミ、ちょっといいかね……)
後ろから声をかけられた。
支部長が神妙な表情でたっている。
(ちょっと話がある)
声を潜めたままの支部長からVIPルームの端へ手招された。
(単刀直入に聞く。キミは、豊川くんとはどういう関係だ?)
(ど、どういう関係といいますと……)
(友好的な関係か、敵対的な関係かということだよ)
どう答えるのが正解なんだ。
(正直に答えてくれ。客の頼みを聞いてくれないのか?
(じ、自分、この店のスタッフじゃないんで)
(なんだ? ボーイくんじゃないのか?)
(は、はい……自分、いま就活中でして……)
(よし、それなら、わたしから棚田くんに頼んでこの店で働けるようにしてあげよう)
(ほ、ホントですか?)
(だから正直に答えてくれ)
(はい。どちらかというと敵対関係です)
(そうか。よし、それじゃあキミに折り入って頼みがある)
(な、なんでしょうか)
(この店のラウンジの隅にビニールがはみ出した段ボール箱がひとつある)
トロフィーの後ろにあったクミコらしきビニールが飛び出ていた箱のことだろうか。
(それを奥の完全に外からみえないところに、移してくれるように頼んでくれないか)
この人はクミコの存在を知っているのか。それならなぜ、豊川に知らせないんだろうか。
(あれを、豊川くんにみられてはいけない)
(でも、段ボールに入ってるんですよね?)
(あの男を甘く見ちゃいけない! クミコの衣装の端切れがちょっとでもみえただけでアイツはみつけだす! 彼はそういう男なんだ!)
支部長が強い怨念が籠もったような眼差しで壁を睨んでいた。
(頼む! 早くログアウトしてくれ! 彼の注意がchibusaさんに向いているうちに)
支部長の恐ろしく力の入った眼力に押されて、ログアウトをした。
ゴールドイン──ゴールドアウト──。
現実には戻ってみたが、どうすればいいのかわからなかった。どうやって、あの段ボールを動かせばいいんだ。
あそこには、地獄の番犬ケルベロスのような睨みをきかせるあの女性が立っているというのに。
「……アタシの作品を所有することは許さない!」
ふと横をみると、chibusaさんが現実側の身体も動かしながら声を発していた。
通常、仮想世界側の動きは現実側に影響を及ぼさないものだけど、よほどの興奮状態らしい。
棚田さんも額には大粒の汗が浮かんでいる。
そろそろ誰かが、豊川を
豊川がクミコの存在に気づいてしまったら自分で手に入れようとするのも明白だ。
立ち上がりLounge-310へ急いだ。
「お姉さん! おかわり!」
「……チッ」
あからさまな舌打ちが聞こえた。
まもるさんのテーブルには、大量に空のグラスが転がっている。この短時間に一体、何杯飲んでいるんだ?
「このメロンソーダおいしいね!」
まもるさんが脳天気にグラスを振る。
「あ、ハルノキくん! お帰り!」
最悪のタイミングで呼びかけてきた。
鋭い視線を感じる。
「あちらのお連れ様が、迷惑なんですけど」
客をハッキリと迷惑扱いするノゾミは、先ほどよりもさらに不機嫌にみえた。
「た、大変申し訳ありません。しかし、ただいま至急な用事がございまして」
とにかく箱をどこかへ移さなくては。
カウンターの前を通りすぎ、トロフィーの飾られたスペースの奥へ手を伸ば──
「お客様ぁ、そちらに手を触れるのはお辞めくださいと申し上げたかと思いますよぉー」
カウンターの中から威嚇するような声がする。
「これ以上の迷惑行為を繰り返されるのであれば、退店していただきます」
それはVIPルームで熱弁をふるうあの人に言って欲しい。
「あ、あの、こちらのお店の常連さんから、そこのダンボールを片付けるようにいわれまして」
「どちらのお客様でしょうか?」
「あ、あのエアロビに映ってる髪が長くないほうの方です……」
ディスプレイ内では、ちょうど豊川がchibusaさんに平手で打たれているところだった。
豊川が深々と一礼して、反対側の頬を差しだしている横で支部長が立ち尽くしていた。
「あの渋い方?」
「そ、そうです」
「なんで早くいわないの!」
「え!?」
「すぐにダンボールをこの中へ!」
ノゾミはカウンターの奥にある冷蔵庫をあけ手招きした。
「い、いいんですか?」
「当たり前じゃない! あんなに渋い人が困ってるんだから!」
「……から、僕は! せめて、サインしてもらいたいだけなんだよぉぉぉ」
ラウンジが面する通路の奥のほうから豊川の声がした。イヤシちゃんを欲しがっていたときのことを彷彿とさせる駄々をこねているようだ。
「わかったけど今日はいちど帰ろう。なっ! 豊川くん! 飲み過ぎだぞ」
「あれぽっちのホットミルクで僕が酔うわけないじゃないか!」
支部長のなだめる声も近づいてきた。
そして、数人のセキュリティ・ポリシー。
全員が金色のスパンコールがびっしりと縫い付けられたトレンチコートを身につけている。
こ、この地域のセキュリティ・ポリシーはあんなにハデな制服なのか……。
「は、ハルノキくんじゃないか! 僕、なにか悪いこといったかなぁ!」
ズボンに大きな染みをつくり豊川が歩いてくる。セキュリティ・ポリシーも困惑した表情を隠せずにいる。
「と、とにかく、本日はお家に帰りましょう」
「僕はね、諦めないからね! chibusaさんが微笑んでくれるまでお願いするんだからね!」
「わかった、わっかたから帰ろう」
支部長が豊川の肩を抱いた。
「ちょっと外まで送ってくるから、キミ、ここで待っていてくれ」
支部長と黄金のセキュリティ・ポリシー達が豊川を連れ、歩いていった。
「いやあ、キミ本当にありがとう」
豊川をセキュリティ・ポリシーに引き渡した支部長がラウンジに戻ってきた。
「どこに隠したんだ?」
不思議そうにトロフィーのほうへ目を凝らす。
「この中でぇーす!」
まただ。棚田さんにみせたあのとびっきりの笑顔でノゾミが冷蔵庫の中からダンボールを取りだした。
「おぉ、そうか! 見事な連携プレイだな」
「い、いや、自分はなにも……」
「支部長! いろいろと失礼をいたしました」
棚田さんがラウンジに戻ってきた。
少し疲労の色が表情に滲んでいる。
「いや、こちらこそすまなかった」
「ハルノキくんも、いろいろとありがとう」
「あ、あのchibusaさんは……」
「明日からに備えて、今日は先に休ませてもらいました」
「そ、そうですか」
「まさか、本当にセキュリティ・ポリシーを呼ぶことになるとはね、まいったね、ハハハ」
棚田さんが支部長に頭を下げながら笑っていた。胸元の金ネックレスが頼りなさげに揺れた。
「いや、仕方がない。彼があそこまでエキサイトしたらもう素人では手に負えないんだ。まあ、ひと晩で出てくるかもしれないが、少し反省させたほうがいい」
「そうなんですか……弱ったなぁ、明日から大丈夫かな……チーちゃん」
「そういえば、明日に備えるって、明日からなにかあるんですか?」
「ん? 実はね……ダンスコンテストに向けてチーちゃんにドーンとスゴイ作品の制作をお願いしてるんだけど……、明日もあの人が来たら、制作どころじゃないよねぇハハハッ」
確かにあの人の並外れたメンタルならば、どんなことがあっても目的に向かって這い上がってくるだろう。まして、chibusaさんの作品にあれほど陶酔している人が、目の前で創作活動に入るアーティストをみたら何をするか……。
「それなら、この彼を用心棒にしてみたらいいんじゃないかな?」
支部長に肩を叩かれた。
「は、ハルノキくんをですか?」
「彼、なかなか機転がききそうじゃないか」
そういえばさっき口利きしてくれる約束をしていた。……バタつきすぎたせいで忘れていたが、この店で働かせてもらえなかったら、この先、本当に路上生活者になってしまうかもしれない。ここはなんとしても食い下がらなければだ。
「そ、そんなたいしたことしてないですけど、で、でも、た、棚田さん、じ、自分でよければ……用心棒やりたいっす! あ、あの、自分、VR空手、初段っすから」
「なんなら、わたしが彼の分の給料を支払っても……」
「いえいえ。彼には最初からここでボーイとして働いてもらいたいと思ってました」
──えっ?
「ハルノキくん。ぜひショルダーパッドで働いてくれないかな?」
棚田さんが、ふんわり笑った。
次回 2019年03月08日掲載予定
『 トックトック 』へつづく
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする