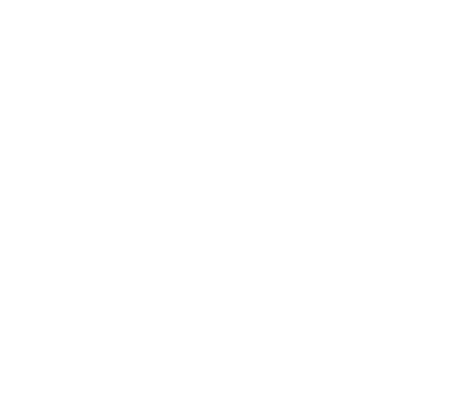第103話『 マイティーベース 01 』
瞳孔を無理矢理こじあけ、網膜に殴り込んでくるヴァイオレットオレンジのスリーピース。
ワイドな肩幅、挿色になっているのか、ネクタイはシックなネイビーブルー、模様はペイズリー。
手に白いコースターを握り、気取った足取りで近づいてくる渋井はショルダーパッドにマッチするギンギラギンにさりげない“バブル紳士”だった。
「このコースターをくれたのはキミ?」
Lounge310のロゴが入った丸いコースターをカウンターの上へそっと置く。
「は、はい……あ、アタシです……」
ノゾミは遠慮がちに、むしろ怯えたように小さくうなずく。
「僕から声を掛けようかと思ってたんだけど、まさキミの方から来てくれるなんてね」
「えっ……!?」
ノゾミの頬が紅らむ。
渋井は細い金の指輪をつけた右手の人差し指で“1”を示す。
「まず、ウイスキーを1杯頼むよ。ダブルで。キミもなにか好きな物を……」
いつのまにかカウンターを挟んで向き合う2人を、夜景の広がるレストランでワイングラスを傾けるような雰囲気が取り巻いていた。
「なにしてくれてんだよ! マイクおシャカじゃねえかよ!」
「な、ナンプラさっぁん! こ、このお方はっぁ……」
豊川さんはずぶ濡れの髪を垂らし全裸のまま、じっとナンプラさんの方をみつめている。
「シゲルくん、復活させる方法、教えて」
「ぁ? まずオマエ誰だ!」
「僕は豊川豊。上から読んでも下から読んでも豊川豊です。」
「お、おま…………、豊川豊クンか!?」
豊川さんはサングラスを抑えながら頷いた。
「シゲルくん“ブレイク”しちゃったんだよね」
「ふん。下手クソだな」
「ほら、僕、聴くの専門でリズムプレイに慣れてないじゃない?」
「オレは、おまえらみてえな
ナンプラさんがタバコに火を点けた。
「豊川豊クン、オマエが全国のテクノブレイカーたちの希望を打ち砕いたんだ。なんでいきなり水槽から出てきやがった」
「気がついたら、ログアウトしておりまして」
豊川さんがしおらしく頭をさげた。
「どうか、僕のシゲルくんをすくっていただけないでしょうか」
「オレはプロフェッショナルだ。番組が絡まねえところじゃ喋らねえ」
「すぐに、番組を再開していただけますか?」
「できるわけねだろ! どうすんだよこれ!」
豊川さんはゆっくりと周りを見渡した。
「このマイク使えないんですか?」
「オメエが水浸しにしちまったからな! もういい、どっちにしても今日はもう喋る気分じゃねえ! コージ、撤収だ!」
「放送が途切れたままだとマズいでっぇす!」
「自動放送にでも切り替えろ。しばらく番組は中止だ。部屋片づけとけ。棚田さんにバレねえようにな」
ナンプラさんはそれだけ言い残し、自動ドアに向かって歩き出した。
「あ、な、ナンプラさっぁん!」
「オレは帰って寝る。あとは──ウゴッ!」
「が、ガムテープ張ったままでっぇす!」
自動ドアに顔面から突っ込んだナンプラさんが、ドアを蹴飛ばしてからテープを剥がして出て行った。
外からもう一度ドアを蹴る音がした。
カウンター越しの2人を濃密な空気が取り巻いているようにみえた。
「キミ、ここにいつもいるよね?」
「えっ!? 覚えててくれたんですか?」
「もちろん。毎日仕事で彼氏とか心配しないの?」
「か、彼氏なんていません! す、好きな人ならいますけど!」
「へぇ! そうなの。もしかして、ハルノキくんとか?」
「そ、そんなガキ眼中ないです! わ、わたし、年上の落ち着いた男性が好きなんですっ!」
耳まで紅くなっていた。
「ハハハ、そう。大人の恋ってやつ、狙ってるのかな」
絞り出すような低音ボイス、グラスを傾ける横顔。どっしり広がる肩と少しだけ哀愁ある丸みを帯びる背中、これが大人の男ってヤツか……。
あのノゾミさんが、飼い慣らされた小型犬のように、瞳を丸めカウンターにもたれかかっていた。なんだ、あの媚びたような笑顔。
「キミに頼みたいことがあるんだけど」
「な、なんでしょっ!?」
「このラウンジにダンサーの女の子がきたら紹介してほしいんだ」
「……え…?」
「今度のダンス大会で優勝を狙っている」
「つ、つまり? その、えっと」
「ダンサーを探しているんだ。スカウトを手伝ってほしい。お礼ならちゃんとするよ」
「お、お礼なんて……」
「タダで女性に仕事をたのむなんて僕にはできないからね」
「し、仕事……ですか……」
「大切な仕事だよ! 僕はどうしても次の大会で優勝しなければならないんだから!」
ノゾミさんの表情が陰った。
「女性からの方が警戒心も薄いだろう?」
しかし、渋井さんは気に掛けていないようだ。
「……わ、わかりました」
「後でimaGeに僕の連絡先送っておくよ。それじゃあ頼むね、ありがとう!」
渋井さんは一気にグラスを空けて席を立つ。
「そうだ、ハルノキくん」
「自分すか?」
「PARKさ、ありったけいただこうかな。さっきの部屋に在庫持ってきてよ」
「ぜ、全部っすか!?」
「僕の連れがPARKは見かけた時に買っておきたいってさ」
それだけ言い残して渋井さんは颯爽とラウンジを出ていった。
ノゾミさんを振り返ると、カウンターの1点をみつめ、捨て犬のような目をしている。
「の、ノゾミさ……」
「うるせえ! さっさと仕事に戻れ! こっちみんな!」
うつむいたまま顔を上げてくれなかった。
何てことをしてくれたんだ。ナンプラぁ。
ラジオの音は唐突切り替わり、環境音楽を流し続けている。
番組を中断して自動放送に切り替えるなんて、完全に放送事故じゃないか。
途切れる間際のあの騒ぎ、おそらく豊川の入っていたTMRになにかが起きた音。
ソファに掛けておいた上着を抱える。
早く店に戻らないと。
しかし、立ち上がってはみたものの猛烈に胃が痛み、再び座ってしまった。
ソファと床に体が根をはったようになる。
面倒くさい。
次から次と、なぜ今日はこんなにトラブル続きなんだろう。
もう、今日はこのまま寝ちゃおうかな。
今日は店にナベくんも居るし……。
彼に任せちゃおうかな……。
ひとしきり飲んだコーヒーは眠気醒ましにはならなかったらしい。
胃の中で暴れまわって、猛烈にこのまま寝てしまおうという気分を盛り上げてきた。
考えてみれば、ナンプラもコージくんも結局ここに戻ってくるんだから、店に戻る必要ないんじゃないかな……。
朝靄がたちこめる薄暗いセントラルパーク。鬱蒼とした雑木林が広がっている。
パークさんは起きているだろうか。
なんとしても、“ガムネコ”付きのPARKを手に入れて現金を手に入れなければ……。
タンジェントと競馬観戦できない。
前借りを頼もうと棚田さんを待ったが昨夜は結局店にあらわれなかった。
さらに、コージさんが豊川を連れて店を出て行ったという噂が流れ、バタついた現場をまわしていたナベさんは不機嫌そうで、とても前借りの話を持ち出せそうになかった。
広場を横切り、小高い丘を登るとスカイブルーのビニールハウスがみえてくる。
ここが正念場かもしれない。
「まもる、ここ、線が途切れてんぞ!」
「は、はいぃ!」
心配するまでもなかった。
もはや定番となりつつあるやり取りが、粗末なテントのような小屋から漏れてきた。
早朝からなんというテンションの高さだろう。
入口の隙間からのぞくと、まもるさんは“みかん”という文字の入ったダンボールを机にして、上から覆い被さるように座り額を拭っている。
「丁寧に! 女性らしい線を意識しろ!」
「は、はいぃぃ!」
手に彫刻刀のような物を持ちなにか彫り物をしている。
「そこぉっ! 誰だぁ!」
しつけの足りない犬が吠えかかってくるようにパークさんがシートの中から飛び出してきた。
「なんだ。オメェか」
「お、おはようございます……」
喉元に牙を突き付けられたような恐怖。額に冷たい汗が滲む。
「取り込み中だ。後にしろ!」
「ぱ、PARKが欲しいんですけど」
「なにぃ? 昨日ツーカートン持ってったばっかじゃねえかよ」
「そ、それが、即日完売でございまして」
「なんだと……!?」
「そうかそうか、やるな! ロッカ飲むか?」
「い、いえ、結構です……」
シートの中に通され、PARK即日完売のいきさつを説明するとパークさんの表情は和らいだ。ガムネコの話を持ち出すなら今だろうか。
「ほっか……ほっか」
小刻みに頷きながらタバコに火を点ける。それにしてもこの家……いや、これを家と認めてしまってもいいのかは疑問だが……そこら中に、いちどは“投棄”もしくは“破棄”されたであろう物体が所狭しと並んでいる。この空間は第2の人生を過ごす物達の最終到達地点なのかもしれない。
「パークさん! みてください!」
もう何度“新たな人生”を歩んでいるのかわからない、まもるさんの脳天気な声がした。
「みせろ」
まもるさんから受け取った物体をパークさんは真剣な眼差しで睨む。
「まもる……」
「は、はい……」
「オメェ、腕あげたなぁ!」
「ありがとうございます!」
「よし! これならいける! まもる、紙片、ロング!」
「126×148ミリです!」
「そぉうだ! 早く切れ」
「はいっ!」
返事もそこそこにまもるさんが、こんどはカッターナイフで白い紙を切りはじめる。
「あ、あの……先ほどから一体なにを……」
「ハルノキくん! ここがいちばん大切なところなんだから、静かにして!」
人としての尊厳をむしりとられたような気分だ。まもるさんの持っているカッターは定規も使っていないのにまっすぐ紙の上を滑る。
「パークさん!」
「オメエ、こっちの腕もあがったな」
受け取った紙をパークさんが折っていく。
PARKの外箱のようだが幾分細長くみえる。
「筆入れぇっ!」
マジックが紙の上に走る。
そうだ、いま頼めばネコを描いて貰えるかもしれない。
「あの、パークさ……ん?」
しかしマジックは『PARK』の文字を書きおえてもまだ動きを止めない。
キュッキュッと力強くその先の文字を刻む。
PARK……WILDE……?
WILDEってなんだ!?
「まもる! ダイコンハンコ!」
「はいぃぃ!」
さっき睨んでいた白い物体。
ダイコンだったのか。あれ。
輪切りのダイコンは黒いスタンプ台に押しつけられた後、紙の上に押しつけられ、ゆっくりと持ちあげられた。
PARKの箱に筆記体の英文字が印字されていた。サインのようだ。
「……みろ! ハルノキ」
パークさんは、誇らしげに箱を掲げる。
「PARK WILDE chibusaシグネチャーモデルだ!」
「な、なんすか……これ……」
「オレがchibusaさんに差し上げたPARKを一般向けに調合し直したもんだ」
「chibusaさんにPARKを?」
「昨夜こちらにお見えになった」
「こ、この家にですか!?」
「おう。オマエがいま座ってる辺りに、先ほどまでいらしてたんだ」
一体なにを思ってchibusaさんはこの家に。
「箱にサインしてくださいって頼んだら、気前よくサインしてくれたぞ」
「ボクがそのサインをハンコにしたんだ!」
「なかなかだろ? サインが入るとよ」
前歯にタバコを挟んだパークさんが、箱を持って近づいてきた。
立ちこめる副流煙が鼻に入る──。
タバコ吸いたい──。
突如、猛烈にタバコへの欲求が膨れあがった。
「あの、パークさん、タバコ……」
「おう、普通のPARKでいいんだよな。いまつくるから待ってろ」
「いや、その前に……自分にタバコを1本いただけないでしょうか?」
物乞いにタバコ乞いするのはいかがなものなのか。でも、どうしてもタバコが吸いたい。
「オメェ、吸うのか?」
「は、はい、いただけないでしょうか?」
「ん? ホラ」
ポケットから取り出されたくしゃくしゃのPARKを受け取る。
「あ、これ、最後の1本ですけど……」
箱の隅っこには、枯れる間際の朝顔みたいなタバコが1本残っているだけだった。
「ん? あぁ? いいぞ吸え」
「あ、ありがとうございます!」
なんて気前がいんだろう。最後の1本なのに。
左脇からブリタニカルを出す。
ゴッシャンッ
「オメェ、タバコ持ってねえくせに、ライターだけはいっちょめえだな」
「ども……」
煙を吸い込む。
広がってきたぁ!
起き抜けの脳に染みこむような痛覚!
「しかしなぁ、問題はコストだよなぁ」
パークさんはPARK WILDEの箱をあちこちから眺め苦い顔をしていた。
「どうしたんすか?」
「このモデルよ、サインが入ってんのがポイントなんだな。でもダイコンハンコ、どんどん乾いてくから、もって2日。そのたびに作り直しが必要だ。ハンコつくる手間も考えたら少しでもコストを下げねえと儲けが薄い。どーっすかな」
「それ、消しゴムとか使ったらいいんじゃないですか?」
「なんだと?」
「ちょっと前に自分の友達が『履歴書在中』ってハンコつくってくれたヤツがいたんすけど、かなり細かくつくられてましたよ」
「……おまえ、天才じゃねえか!?」
「……すか?」
「もしかして、タバコ吸うと脳みその回転よくなるんじゃねえのか!? オメェ」
「いやそれくらいは……」
「もっと吸え! もっとねえか、コスト削減する方法!」
「ちょっとみてもいいっすか?」
PARK WILDEの箱を手に取った。
前後左右に隙間無く詰まったタバコ。
……んっ……?
「パークさん、コスト減らすのってようは材料けずればいいんっすよね?」
「なんだ、もう閃いたのか!?」
「はい。グワっと」
「なんだ! いってみろ!」
「その前に、パークさん。取引してもらえませんか?」
「取引ぃ?」
「自分、これから競馬をするためにどうしてもお金が必要なんすけど、これから話すアイディを採用するなら、イラスト付きのPARKをワンカートン用意してもらいたいんです」
「ずいぶんと自信があるみてぇだな」
「いや、まあ」
「わかった……。話してみろ」
「うっす。まずタバコの箱開けたときに入ってる本数を数えてから吸い始める人いますかね?」
「わざわざ数えるヤツなんていねえだろ」
「っすよね。で、1本ずつ吸っていくわけで、いちいち吸ったタバコの本数なんて覚えてないっすよね? さっきパークさんも最後の1本だって気づいてなかったし」
「確かに、そうだが、それコストに関係あんのか?」
「箱の左右を……こうやって内側に折り込めば、2本分の空間が埋まるから2本入れなくてもいいじゃないすか」
思った通り。
PARK WILDE を2本箱から抜き取っても、上からみるといつものようにタバコは箱につまっているようにみえた。
「お、オメェ……なんて……けしからん……オメェ…けしからんぐらいに冴えてんな!!」
「……すか?」
「したら、あれだろ? ツーカートンで20箱だから、2本ずつぬいたら2箱分浮くってことだろ!?」
「っす」
「オメェ、それ売れば売るほど儲かっちまうやつじゃねえか!?」
「そうなっちゃいますね」
「タバコ、もっとやる! もっと考えろ!」
「うっす」
パークさんが新しいPARKの封を開け、さしだしてきた。
次回 2019年10月25日掲載予定
『 マイティーベース 02 』へつづく
「旦那ぁ! 朝っすぅ!!」
時間も空気も読まない蒔田の声。
まだ5時前だ。
これがニワトリなら即座にシメられてしかるべきだ。
午前3時まで飲んでおいて、なぜこの人はこんなに元気なんだ。
「教習、長丁場になるんで朝メシしっかりくいやしょう!」
「あ、大丈夫っす。自分、農家なんで、朝は強いっす……」
セイジの声もかさっかさに掠れている。
「さ、さきに、メシくってきていいすよ」
「それが……あっし、ひと足さきにメシ食いにいってみたら教習生と一緒じゃねえと、朝メシだせねえなんていいやがるもんですからね、旦那のことを起こさねえとダメだなと思って、ささ、メシいきやしょう! あったけえ味噌汁がまってやすぜ!」
畳のうえをなにかが引きずられるような音がする。セイジは半分寝転んだまま手を引かれていった。
「う、うう……」
「旦那ぁ! おかわりどうすか!」
「いや、いいっす」
白目のままセイジは首をふる。
食堂の席についてからいちどもまともな目をしていない。
「そっすか? じゃあ、あっしが!」
お膳に並べられた旅館のような朝食だった。
正統派の和食が、蒔田さんがいるだけで、これほど外道に感じてしまうのか。
「しっかり食わねえともたねぇっすよ! 旦那の申し込んでる“ウルトラビッグバンコース”は、ハードっすからね!」
「う、うっす」
「早くかっ喰らわねと一限目はじまっちまいやすよ!」
「一限目、何時、からすか」
「6時っす!」
「あ、もうはじまる、の?」
「あっしはメシ終わりやしたんで先にいってやす! 旦那! 教室で待ってやすから!」
蒔田さんは疾風のごとき速さで味噌汁を飲み干し食堂から飛び出していった。
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする