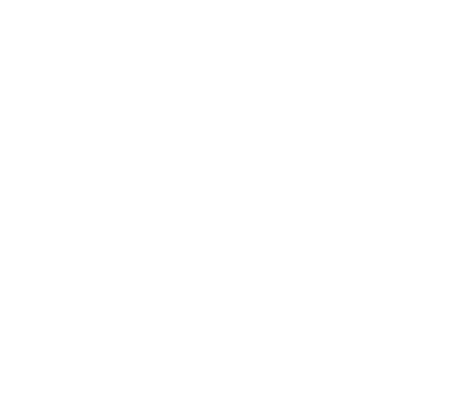第118話『 クニ、タチぬ 03 』
<< ブレぇーん☆バスタぁ!>>
“DOS×KOI”のダウンロードが終わると視野内に現れたロゴマーク。甲高い音声が
“ブレぇーん☆バスタぁ”は運営会社か?
判断する前に文字がフェードアウトして、次のロゴがでてくる。
<<chibusa バウンス スタジオ>>
「これは…」
chibusaさんの……。
「おっ? 始まったかぁ?」
いまどきインストールまでにこれほど時間がかかるなんて………まあ、まもるさんのボロスマホに“江照”を入れたときよりはマシか。
「DOS×KOIは初回ロードが長げぇ。なんでかわかるか?」
「…データが重いから…すか?」
「青春が詰まってんだよ! ブハハハハ! おやじ! ビール!」
間髪いれず、瓶ビールが運ばれてくる。
それ、4本目じゃないか?
「パークさん、飲み過ぎじゃ……」
「ぁあ? ロッカに比べりゃこれしきのビールなんてこたぁねえ!」
公園の脇を流れる川の水を丁寧にろ過し、丹念に密造された蒸留酒ロッカ。存在もイリーガルならば、アルコール度数も度をこしているのか。
グラスにビールを並々と注ぐパークさんに重なり、視野内では丸文字のロゴが浮かびあがる。
<<青春ビートエクストリーム!>>
音声と共に視野の手前までロゴがいきおいよく迫ってきた。
<<DOS×KOI!>>
キラキラした女子数人の掛け声に合わせてハートがドゥーンと突き上がり、ド派手なロゴが視野内を占拠する。
「こ、これがDOS×KOI……」
“DOS×KOI”のロゴを挟んで立つ、男女のシルエット。胸から星が飛び出す男子の影に目が行く、もしかして、これ……。
「ナツオ、オレにも画面みせろ」
「あ、はい」
パークさんにも見えるよう、テーブルの中央へエアロディスプレイを立ち上げディスプレイ側に表示を切り替える。
「なつかしいじゃねえかぁ。ホントに復刻してんだなぁ」
パークさんは目を細めつつ、ビールの泡を舐めとるように、チビリとグラスを傾けた。
「この右側の男子生徒がクニタチってんだ」
…やっぱり、これが、クニタチさん。
「DOS×KOIはクニタチの学園生活を中心にして進む。ストーリーイベントごとに生徒達が困ってる生徒を“応援”するんだが、その応援シーンがリズムゲームになるって寸法だ」
「DOS×KOIって相撲から来てるんじゃないんですか? 番付とか、横綱とか」
「そいつぁ、運営の後付けだな。ホントのDOS×KOIの意味は、“2つの恋”」
「2つの…恋?」
「おぅ! DOSはスペイン語の“2”。DOSのKOIでDOS×KOI、だった」
「だった。すか?」
「β版で配信されたミルクリームエモーションは、クニタチが女子に告ってフラれて、そっから甘酸っぱく揺れ動く恋心を抱えながら這い上がってくクニタチのラブサクセスストーリーになる予定だったらしいんだが、誰も“ミルクリ”をクリアできなくてクニタチは告れなくて、いきなり方向性が変わっちまった。焦った運営の“ブレバス”は当時キッズたちのスラングで使われてた相撲用語を、これ幸いとばかりに取り入れたらしい」
イイ感じに酔いはじめたのか、パークさんの語りがどんどん饒舌になってきた。
「クニタチが好きな女子は誰なのか。コイツは未だに論争が絶えねぇ。DOS×KOIプレイヤーたちが集まるとケンカしはじめるくれぇの謎だ!」
「別に誰が誰を好きでもいいんじゃないっすか……」
「なんだ? オメェ冷めてんな?」
「そ、そんなことないっすけど」
「さては、オメェ、修学旅行で真っ先に寝る口だろ?」
「ど、どうして……」
わかったんだ。修学旅行はかーちゃんに無理矢理いかされただけで、楽しんだ記憶はない。
「夜中によぉ、クラスのヤツと誰が好きだとか、オマエこそ誰なんだよ。とか、そういう話はじまると、寝るだろ?」
「…好きな子とか、いなかったすから」
「かーっ! クニタチと一緒!」
そろそろ酔ってきたんじゃないか、この人。
「クラスに1人はいるよな! 最後まで口を割らねえヤツ! ぜってぇ起きてるクセに、好きな女子とかいるクセに、知らねえ振りしてそのままホントに寝ちまうヤツ! ゲーム版でもアニメ版でもクニタチが、修学旅行でおんなじことしてんだよ! …ビール!」
すごすごと5本目の瓶ビールが運ばれてきた。
「も、もうその辺で……」
昼間の定食屋で飲んでいい酒量を超えている。
「豊川ってヤロウは気に入らねえが、クニタチを男にしてやりてえってのは、ちっとだけ理解してやれるわ! ミルクリをクリアすりゃ、クニタチの告白がみれるんだわ!」
「で、でも、そんなに大事なストーリーなら、β版だけじゃなく、他のストーリーに組み込めば良かったんじゃ……」
「ナツオ…そうはいかねえんだわぁ……」
パークさんが唐突にテーブルに突っ伏しはじめた。まるで、人生の悔恨を吐露するような勢い。
「DOS×KOIはよぉ、一部の運営オリジナルストーリー以外、ほとんどリアルなんだわぁクニタチやナツメ、ミナミ先輩、アイツらの青春がびっちり詰まってんだよぉ」
「じ、実話ってことですか?」
「やってみりゃわかる」
「クニタチさんは告白してフラれたってことですよね」
「現実がどうだったかはわからねえが、一説じゃクニタチは告白できなかったからミルクリのエンディングは存在しねえ。だから絶対クリア不可能なんじゃねえかともいわれてる」
DOS×KOI、2つの恋、
胸から星が飛びだした男子は、もしかすると、想いが溢れそうになるのに耐えきれず胸を押さえているのかもしれない。
国立さんが見せてくれた、硬くて冷たい金属のようなタマゴ。
“数十年分の恋心”が詰まってるといっていた。
もしかすると、ミルクリームエモーションは最初から“無理ゲー”なのかもしれない……。
「いいかげん、クニタチの結末みてえじゃねえかよ、なあ?」
パークさんがビール瓶を逆さにして振る。
「オレもよぉ、いい加減、仕舞ぇにしてえよ。ナツオぉ」
「そ、そこまでいうなら…」
パークさんも出場すれば…、と言いかけてやめた。
この人は、ドーピングの過去を背負い、ゲーミングアスリート界から追放されている……公式でない場所でも参加はできないのかもしれない。
「よぉし! 行くか! ナツオ」
パークさんが立ち上がる。足元がよろけて、テーブルにもたれかかった。
「ど、どこにっすか?」
「オレらのホームだ! 練習すっぞ!
「あ、歩きゲームはマナー違反じゃないですか! それにリセマラとかしないんですか……」
この手のゲームは、初期キャラでいかにレアで強力なキャラを引き当てるか。引き当てるまで、インストールと消去を繰り返す、古来の伝統、リセットマラソン、“リセマラ”が肝……。
「麻雀で役満ねらうときに、ドラの数、気にするかぁ? ぁ?」
「よ、よくわかりません……」
「パーク様の必勝哲学にリセマラの文字はねえ! 行くぞ、DTC!」
そのまま、店の外へでていく。
「ま、待ってください!」
「あ! ちょ、ちょっと! お金」
カウンターからあわてて店主もでてくる。
「す、すみません」
「ちゃんと払えよぉナツオ! セキュリティポリシーに直行直帰になっちまうからなぁ! ブハハハハ!」
より陽気に、日射しのように眩しくバカっぽいオーラをサンサンと放射しながらパークさんは店の外に立つ。背後に見える青い空。
いつのまにか太陽も本気を出し始めたようだ。
「ナツオ! ハイヤーは!? まぁ、いい。歩くぞ! 家に着くまでに“12時ポエム”くれぇは読んどけよ!」
上機嫌どころか空に放たれた風船のようにふわふわしながらパークさんは歩き出した。
マナー違反だとは思いつつ、エアロディスプレイを出したまま歩く。
“12時、ポエム”というエピソードがゲームストーリーの第1話らしい。
国立さん、いや、“クニタチ”が高校に入学式した直後、クラスに配布されたのは、し、試験段階のimaGe!?
……imaGeの開発がはじまったのは、“エデル”が世界に影響力を及ぼしはじめるずっと前、エーデルフロートを発見して上空都市計画がはじまるよりも以前のことだと大学の授業で聞いたことがある。まさにいま自分が見つめているエアロディスプレイをはじめ、VRの“感覚再現”、“
……この辺の時代背景も事実に基づいているなら国立さんやミナミ先生、結構な歳だったんだな。まあ、見た目なんていくらでも若くできるか……。
クニタチはクラスメートたちを密かに蔑み、授業中にポエムをしたためる。
12時丁度が“ポエムの時間”? だから、12時ポエム……。
imaGeを誰よりも使いこなそうと躍起になり、imaGeに詳しいことに対する優越感を抱き……。
……あれ……これ……。
「パークさん、DOS×KOIってどこまでが実話なんですか?」
「野暮なこと聞くんじゃねぇ! だいたいリアルだ」
だとしたら、これがほぼ事実なんだとしたら……クニタチさん、相当な“陰キャ”じゃないか……。研究所にしていた古い校舎の屋上を“聖域”と呼んでいたのも、納得だ。学園ヒエラルキーの最下層に生息する男子にとって、屋上侵入というアウトローな行為は羨望の対象であっただろう。
白衣に身を包み飄々とした、国立さんの姿に胸が締め付けられる。
……自分の前では、ムリして明るく振る舞ってくれていたんじゃないだろうか。
これほどの“イタみ”を伴う学園生活をよく無事に乗り越えて、あれほどの研究所を……この強烈に感じる共感と羨望の気持ちを“尊敬”と呼ばずしてなんと呼べばいいのか。
それから、“ナツメ”も“リっちゃん”も、間違いない。あの人達がモデルだ。そして、この女子キャラのグラフィックスを描いたのが当時のchibusaさん。
みずみずしいキャラの動き。際立っている、胸元の
chibusaさんの描く高校生バージョンのナツメさん………。
「な、ナツメさん……!」
「お? なんだナツオ! オメェさっそくナツメ派に決まりか!?」
ナツメさんの映像にパークさんの前歯トンネルが重なる。
「い、いや、違うっす…」
目を逸らした。
ナツメさんのリアル、獰猛さを知っていてもなお、見目麗しい姿は眼福の限り。
chibusaさんの才能に感服だ。
いまは、ナツメさんだけを観ていたい。
ナツメさん……。
自分はこんな美少女にダンスレッスンを……。
ナツメさ──。
ドゥデェーン
いや、この音! 不吉なんかじゃない!
「お、おい! ナツオどうした?」
気がつくと足を止めていた。
なんというタイミング。視野内に到着していたのはナツメさんからのメッセージ!
この偶然は、もしかすると運命的なラブストーリーへの序章ではないだろうか。
視野内のメッセージを開封す──
『今夜19時
チャットフィールド
旧校舎、体育館裏にて待つ
byナツメ』
……瞬時に現実が追いついてきて、むりやり引き戻された。
さっきVOICEでいっていた
“byナツメ”って……。
ゲームの方のナツメは、毅然と挙手をして先生にもの申しているところだった。ティーンエイジ・デフォルメ・ゲーム版ナツメさんとのビジュアルギャップがもたらす焦りのような不安が、じわじわ横腹の辺りに効いてくる。
文字に込められた想いが重い……。
川の向こうにパークさんの根城、
「ちょこっと留守にしただけでも懐かしく感じるもんだよなぁ!」
橋を渡り少し歩いて公園の入口についた。
パークさんは、なぜか入口で公園内に向かって一礼してから、大声を張り上げた。
「いま、けぇったぞ!」
すると、入口の側の草むらから数人の男達の顔がでてきた。
「ぱ、パークさん!」
驚いて声をあげたのは、マンジュウと呼ばれていた人だ。
「帰ぇって来たんすか!」
「ったりめぇだろ! ここがオレのホームだからな! ブハハハハ!」
「みんな心配してやした! 広場行きましょう!」
マンジュウの先導で広場まで行くと、かなりの人数の人達が輪になりシャドーボクシングのように腕を前後させていた。
「いきまぁーす! シュッ! シュシュッ!」
中心にいるのは、まもるさんだ。
「シュッシュシュ シュッシュシュ!」
あれは、確か“
なんで、あんなに大勢で……。
「まもるが言い出したんす。パークさんが帰ぇってくるまで、みんなで素摘みしましょうって」
「ほぉ……」
「アイツ、一生懸命フォルテッシモロングの吸い殻集めてたんすわ。おい! オメェら! パークさんが帰ぇって来たぞ!」
マンジュウの声に素摘みの集団が一斉に反応し駆けよってくる。
「おう、オメェら、すまなかったなぁ」
「パークさん、あっしらはどうなっちまうんすか!」
「安心しろぉ。シグネチャーモデルのパブリシティはバッチリと押さえてっから」
「ホントですかぃ!」
「ナツオがうめぇこと立ち回ってくれたからな」
「いや、自分はそんな」
「謙遜するじゃねぇ!」
パークさんに背中を叩かれよろけてしまった。
周囲から笑い声が起こる。
「おい、まもるも来いよ」
マンジュウの呼びかけに返事がなかった。
いの一番に駆けよってきそうなものなのに、まもるさんだけがなぜかパークさんを囲む輪から離れた場所に立っていた。
じっとこちらをみつめる、というよりは、に、睨みつけるような表情で。
「あ、あれ、まもるさん?」
「ん?」
まもるさんが、そっと背中を向け、ふわりと浮かんだ。
「おい、まもる、どこいくんだ!」
パークさんも気がついて叫んだが、まもるさんは振り返りもせずに空へと飛び上がっていった。
「なんだぁ、便所か?」
誰も気にとめていないが、遠ざかっていく後ろ姿に不穏な予感を感じた。
パークさんの出所のことを、まもるさんに連絡を入れていなかったな。
まさかそれで、拗ねて…いや、まさか……。
「よぉし! そしたらよぉオメェら!」
パークさんがひとしきり大声で場を取りなした。
「今日から本腰いれてシグネチャーモデルの生産にはいる! オメェらはしこたまモク摘みだ!」
一同が“へいっ!”と返事を残し四方に散る。
まるで、密書の任務を確認し全国に散る忍者のようだ。
「よし。ナツオ、アイツらが戻るまで練習すっぞ!」
パークさんが親指で公園の奥を指した。
「木陰に行くぞ! ついてこい」
「あれ、家で練習するんじゃないんですか?」
「大会の練習は広いとこでやらねえとな!」
広場の隅っこに移動すると、パークさんは木陰のベンチに座りタバコに火をつけた。
「エアロディスプレイだせ」
「は、はい」
「声が小せぇ!」
「は、はい?」
「こっからは、稽古だ。魂込めて返事しろ! それからオレのこたぁ親方と呼べ!」
ベンチの上で胡座をかくパークさんの表情は、まさに相撲の稽古をみつめるように険しい。
本気、ということか。
「まずは、練習モードからいくぞ。基本も〜しょんってのを選べ」
「こ、これっすか?」
画面の“基本も~しょん”というタイトルをタップする。

「おい!」
「は、はいっ!」
「なんだそのタップは! 野暮ってぇな!!」
「タ、タップが野暮ったいというのは……」
「素人ってのはどうして、もっさりタップしやがんだ? そんなんじゃダボとチムが一緒に来たときにもたつくだろ!」
「だ、ダボ? チム?」
「マジか? おまえ、そっからから?」
「み、未経験なもので」
「かぁっー、未体験なのは四股ネームだけにしとけよ。DTC」
「そ、その名前、やめてもらえませんか?」
「だって、オマエ、四股ネーム“D・T・C”にしてるだろ」
「これはとりあえずです。後で変えようかと」
「四股ネーム変更はゲーム通貨で三千両かかんぞ。まあいい。画面みろ! 指の使い方教えてやる!」
パークさんが立ち上がりエアロディスプレイを引き寄せ、両手で挟むような格好で胸の前に高さを合わせた。
「スマホじゃねえとヤリにきぃな」
舌打ちしながら親指をディスプレイに打ち付けるように上下させる。悪態はついているが、立ち姿は背筋がスッと伸び、両足は肩幅に開かれムダのない流れるような自然体だった。
「みとけよ。この画面だとイチゴとウシが“ノーツ”だ。コイツがこの手前の線に重なったタイミングで叩く」
降りてきたイチゴを親指でタップすると画面の中で星が散ってはじける。
「シングルノーツをそのまんま叩くのが
イチゴとウシを交互に叩いていく。
「練習モードの
エアロディスプレイを戻された。
「へっぴり腰じゃ叩けねえぞ」
「こ、こうですか」
「だから、もっさりしてんだよ、指が!」
パークさんがベンチの座面に指を押しつけた。
「いいか? ナツオのタップはこんな風に第1関節全部がベタァーっとついてんだ」
ベンチに押しつけられた親指の先が白くなっていく。
「ポリ公の書類に拇印押すんじゃねえんだからよ、ここはもっと、すがるく指先でタップだ」
今度はベンチにトンッっと親指が置かれた。
「爪と指先の間で弾くイメージだ。オメェ、爪が長ぇな爪切れ」
胸ポケットからボロボロの爪切りが出てきた。
「後で、こ、今晩、切ります」
「夜は爪きっちゃダメだ! 明日の朝にしろ」
「は、はい」
「とにかく、指が接する面積を少なくして素早く動かせ! そうすりゃ、際でぇとこに差し込んでくる“チム”にも対応できる!」
「あ、あの、チムというのは…」
「c・h・i・m、
パークさんがベンチの座面を擦るようにして親指を垂直に立てた。
「他にもパッセとグッドスがあんだけど、オメェにはまだ早ぇ。まずトゥルーとダボだ。それらしく見えるようになるまで稽古いくぞ。それ、どぉーすこい、どぉーすこい」
指先で……。
「こ、こうっすか?」
「もっと爪の先で!」
「こ、こう!?」
爪で弾くようにタップする。
「そうだ。その感覚をよく覚えとけ!」
「はい!」
「そのまま、リズムキープだ!」
──2時間後。
「それ、どぉーすこい。どぉーすこい」
パークさんの掛け声は衰えない。どこにそんな体力があるんだ。
太陽はてっぺんから、じりじりと照らす。
「ぱ、パークさん、す、少し休憩を」
延々と叩き続けたイチゴとウシのケンケンパが目の中でチカチカとサイケデリックな幻覚のように点滅しはじめている。
「基本の運指はバスケのドリブルみてえなもんだぞ? 身体に染みこむまで続けろ」
「ちょ、ちょっと休憩を」
視界が少し暗くなった気がして、そのまま意識が遠のいた。
「…おぃ、ナツオ、起きろ、おぃ」
タバコの匂いがして目が覚めた。
ブルーシートが張られた天井。どうやら、パークハウスに運ばれたらしい。
「情けねぇなあれしきで」
「面目ありません」
パークさんは奥の布団の上でタバコをふかしている。
「まあ初日だからこれくれぇにしといてやる」
「ありがとうございます」
「明日から毎日通い稽古だ。朝5時に集合だ」
「ご、5時!?」
「オメェ、並大抵の練習でバレねえようにコトが運べると思ってんのか?」
確かに、大会で優勝するためには、そのぐらいの練習量が必要なのかもしれない。
……ん。
「パークさん。“コトが運べる”というのは、どういうことですか?」
「いくらなんでも、それらしくみえねえことにゃ、スグにバレちまうからな」
バレる……?
「運指のフォームをビシッと仕込んで、あとはコイツの出番だ」
パークさんが、ベニヤ板製のテーブルのうえに黒いリュックサックを載せた。ドサっと音がして板が軋んでたわみ、ホコリが舞い上がる。それは、いつもタバコ摘みに使っているリュックとは違うもののようだ。
「またコイツに日の目を見せてやれるとはなぁ」
パークさんは、子供をあやすようにリュックのてっぺんをやさしく撫でた。
次回 2020年06月19日掲載予定
『 クニ、タチぬ 04 』へつづく
「江田くん。とりあえず、特区だ」
海峡を過ぎると蒔田さんは助手席にもたれるようにしながら呟いた。
「特区ですか?」
「あぁ……」
まるで、ひと夜限りの女性を抱いた後、バーボンを片手に葉巻でもくゆらすような声だが、この人の頭の中には金のことしか詰まっていない。
「セイジさんを見捨てて次はなにをしようとしてるんですか」
「見捨てるなんてネガティブな捉え方をすべきじゃない。複数の
それっぽい単語をならべたすっかすかの企業理念みたいなことをいいだした。
「ようは、豊川グループにスマートフォンを売りつけた方が金になると判断しただけですよね」
「なんだ。江田くん、ハンドルを握ると人格が変わるタチか?」
「元からこうですが」
金持ちを前にすると丁稚口調に豹変する男にいわれる筋合いはない。
「なぁに、古いスマートフォンを探すだけだ。簡単な山じゃないか。ソイツをかたづけてスグにセイジの旦那を迎えにいきゃあいいんだ」
今度は盛大に
「オレは、特区にいってドリームを掴む。スマホだけじゃない。後ろにあるブツも捌いて、それを元手にレンタカーを返却する。そして、この旅が終わったら、ゆっくりと自分を見つめ直そうと思っている。江田くんもう少しだ。だから特区に入ったら起こしてくれ」
そういって、目を閉じるとそのまま寝息をたてはじめる。
誰か、このわかりやすいフラグを広げたまますやすやと眠る男を、ひと思いに狙撃でもしてくれないだろうか……。
車窓の外に目立ちはじめた背の高いビルにスナイパーでも潜んでいないだろうかと祈りつつアクセルを踏む。
特区のビル群、欲望の摩天楼が入道雲のようにフロントガラスにもたれかかってきた──。
>>続きを読む
掲載情報はこちらから
@河内制作所twitterをフォローする